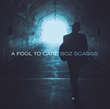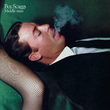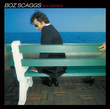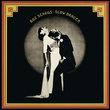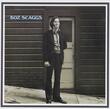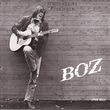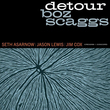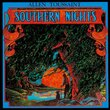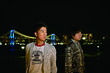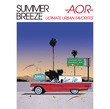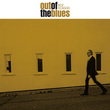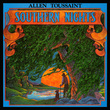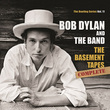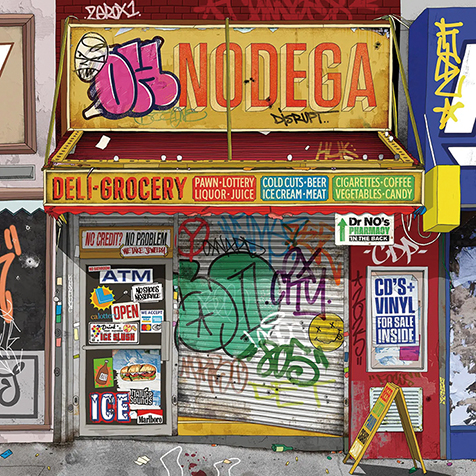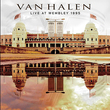『Silk Degrees』(76年)などの傑作を連発し、70s AORの代表的なアーティストとして知られるボズ・スキャッグス。“We’re All Alone”などのヒットでここ日本でも親しまれているヴェテランだが、近年は『Memphis』(2013年)と『A Fool To Care』(2015年)という2作で自身のルーツであるブルースへと回帰。その3部作完結編となるのがこの度リリースされた『Out Of The Blues』だ。
本作のリリースを記念して、コンピレーション〈Light Mellow〉シリーズの監修や執筆で知られるAOR~シティ・ポップ・マスター、金澤寿和にボズ・スキャッグスへの取材を依頼。ボズのキャリアを振り返りつつ、ニール・ヤングのカヴァーも含む新作を紐解いた。 *Mikiki編集部
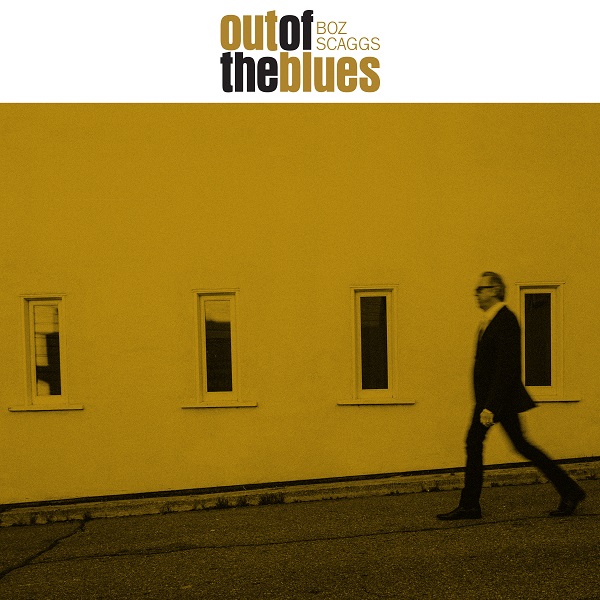
ボズ流AORは一夜にして誕生したワケではなかった
ボズ・スキャッグスから3年ぶりとなる新作『Out Of The Blues』が届いた。この作品は、彼が自らのルーツに回帰した3部作の最終章と言われている。ソウル〜R&Bの名曲カヴァーをタイトル通りの所縁の場所でレコーディングした2013年作『Memphis』、内容はそのままにナッシュヴィルで制作した2015年作『A Fool To Care』、そして今作がその総括。
だが日本の音楽ファンの多くは、そうした方向に向かうボズを意外に思っているのかもしれない。我が国でのボズは、出世作となった76年作『Silk Degrees』と日本独自にヒットした甘いバラード“We’re All Alone”のイメージが強く、それ以来40年以上も〈AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)の先駆者〉として位置づけられてきた。
実際その後続作『Down Two Then Left』(77年)や『Middle Man』(80年)もその流れで人気を博し、後に“Rosanna”や“Africa”のヒットで知られてグラミーを総舐めにするTOTOが、実はボズの『Silk Degrees』でバックを務めていたことも、彼のAORイメージを強固なモノにした。
そのボズの持ち味は、ソフィスティケイトされたブルー・アイド・ソウル。でもこうしたボズ流AORは、一夜にして誕生したワケではなかった。
初期のブルースからAORの金字塔『Silk Degrees』へと至るキャリア
彼は初期スティーヴ・ミラー・バンドの在籍を経て、69年に米アトランティックから本格デビュー。最初のアルバムはマッスル・ショールズでレコーディングされ、デュエイン・オールマンがガッチリとサポートしたブルース色濃厚な内容だ。アルバム・タイトルも原題は『Boz Scaggs』だが、邦題は〈ボズ・スキャッグス&デュエイン・オールマン〉と、まるで共演作のような体裁になっている。
その後はサンフランシスコで自分のバンドを率いたり、シンガー・ソングライター色を強めたりしながら、74年にモータウンのプロデューサー:ジョニー・ブリストルと組んでソウルフルな『Slow Dancer』を発表。そこでの経験や成果を新しい白人スタッフと共に再構築し、小洒落たイメージで表現したのが『Silk Degrees』だった。
これが大きなヒットになり、ドレスコードつきのコンサートを開くなど、当時の音楽シーンのトレンドセッターにのし上がったのである。ボビー・コールドウェルやルパート・ホームス、クリストファー・クロスらの商業的成功は、ボズのヒットなしには生まれ得なかったのだ。