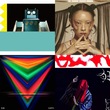活動休止とメンバー・チェンジを経て新生したGEZANが2年ぶりのアルバムをリリース! 多様で多面的な感情を束ねた〈ドキュメントの集合体〉、その芯にある思いとは?
ジャンルやシーンを越境していく活動でエッジーな音楽家/リスナーに支持される4人組、GEZANが新作『Silence Will Speak』を完成させた。数々のオルタナ/パンク名盤を手掛けたことで知られるスティーヴ・アルビニが録音した本作。その出発点には、バンドが主催する野外のライヴ・イヴェント〈全感覚祭〉があり、特に、Campanella、KK mangaのハマジ、ENDONのLOSS、odd eyesのカベヤシュウト、OMSBという強面の面々をフィーチャーしたことでも話題の先行曲“BODY ODD”は、同日の記憶を元にイメージが出来上がっていったという。
「念頭にあったのは、去年の〈全感覚祭〉で“wasted youth”をやっているときに観ていた光景。演奏していたのは自分たちだけど、それ以上にあの場所にいた出演者や友達、お客さんのムード——その景色が一個の答えになっていた。4人での演奏を基本だと思っていたのに、それ自体も崩壊していくような、はじまりみたいなものがあって。今年の(10月に開催する)〈全感覚祭〉は〈Tribal Scream〉というテーマなんだけど、“BODY ODD”はあれだけややこしい人たちが一本のマイクをリレーしていること自体がトライバルだよね」(マヒトゥ・ザ・ピーポー、ヴォーカル/ギター:以下同)。
マヒトの意味する〈トライバル〉を翻訳すると、それは〈多種多様な存在が共生しうる世界〉と言い換えられるかもしれない。『Silence Will Speak』で表現されているのも、一面的でないさまざまな感情だ。形骸化したシステムへの怒り、燃えるような夕陽を目にしたときの救われる感覚、〈終わってしまった〉人への慈しみ……。
「今回、歌詞にも書いたけど、持っていちゃいけない感情とかないと思う。ただ、以前の作品にはコンセプトもあったし、そのなかで不必要な感情や色は使えなかった。絵に喩えると、綺麗な空を描きたかったら、黒は邪魔だとか。今回は、自分のなかでの黒色というか、いわゆるヘイトと言われるような感情や感覚でも存在を許したいという気持ちがあった」。
強烈な咆哮で口火を切る冒頭曲“忘炎”をはじめ、アルバム前半はきわめてハードでヘヴィーな作品。アルビニ印と言うべき刺々しくロウな耳触り、不穏さ漂う重低音が、その印象に貢献していることは間違いない。だが、バンドが彼に求めたのは、その質感以上に〈音への態度〉というものだった。
「アルビニは、そこで鳴っている音に対してのリスペクトがあるんだよね。彼のスタジオはオープンリールでの録音で、卓もすべてアナログ機材。だから、編集も早送りや巻き戻しとかそういう世界なわけ。その場所で起きたもの、もう取り返しがつかないもの……そういう替えのきかないものを尊重しているのが、今回アルビニに頼んだ理由だね」。
こうした一回きりの音への態度は、マヒトの死生観を反映しているとも言えよう。近年、彼は〈ドキュメント〉というフレーズをしきりに使っているが、今作もまた有象無象の生を宿した、いわば〈ドキュメントの集合体〉でもあるのだ。
「たとえば火星とかから見たら俺の一生とか、そんなものホントに一音みたいなものじゃないですか。それって別にネガティヴではなくて、もうちょっと綺麗な言葉で言えば自分が世界の一部でいるっていう感覚。自分の後にも前にも世界はあって、自分は50~60年光るだけのただの灯っていう」。
人気曲“Absolutely Imagination”の先にある光景を〈新世界〉として描くアンセミックな“DNA”を折り返し地点に、終盤は一転センティメンタルなムードに。マヒト特有の弱きものへ眼差しが胸を打つ。
「アルビニの音にリスペクトがあるっていうのと一緒で、俺はリスペクトのあるものが好き。難しいけれど、俺も自分と違う人のことをリスペクトしていたいとは思うんです。誰もがどんな形で存在していたっていいと思う。よく〈人生、失敗した〉とかなりがちだけど、ホントは全員オリジナルの生き物なのに、なぜか同じゲームに参加させられているだけじゃないかな。自分としては、もうそういうのは一抜けたっていうか。俺はもう俺で、勝手に幸せになる。いまは絶望する理由なんてたくさん用意されているけど、いかにそこへとピントを合わさずに、自分が本来持っている視線に立ち返られるかが大事なんじゃないかな」。