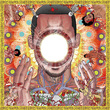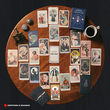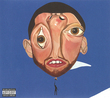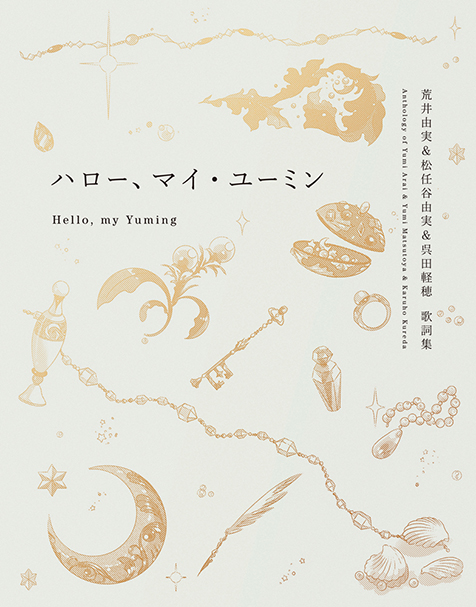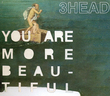フライング・ロータス(以下、フライロー)が主宰するレーベル、ブレインフィーダー。今夏〈SONICMANIA 2018〉では〈Brainfeeder Night〉が大きく賑わっていたことも記憶に新しいことだろう。 ジョージ・クリントン御大からサンダーキャット、ドリアン・コンセプト、ジェイムスズー、そして3Dセットで観客をトリップさせたフライローと注目株のロス・フロム・フレンズまでが集結し、まさにレーベルを体現する一夜だった。そんな〈from LA to everywhere〉な拡張を続けてきたレーベルが設立10周年を祝し、2枚組コンピレーション『Brainfeeder X』をリリースした。
LAのプロデューサー、ティーブスの“Why Like This?”に始まり、2つの新規リミックス(ロス・フロム・フレンズによるサンダーキャット、そしてフライング・ロータスによるブランドン・コールマン)で締められるディスク1では、これまでの10年を総括。対してディスク2には、新鋭音楽家たちの楽曲や未発表・レア曲などが収められており、レーベルの新たな側面を見せつつ、未来を予見させる内容となっている(フライロー監督のブレインフィーダー・フィルム『KUSO』で使用された楽曲も聴くことができる)。
『Brainfeeder X』のリリースに際してまず確認しておきたいのは、ブレインフィーダーは日本との縁が深く、かつ日本で大変人気の高いレーベルであるということだ。では、それはなぜなのだろうか? どうして僕たちは、このレーベルに強く惹かれるのだろうか? そこでMikikiでは、ブレインフィーダーの日本盤の制作やイヴェント企画を一手に請け負うレーベル、ビートインクのスタッフにインタヴューを実施。レーベル・マネージャーの若鍋氏と宣伝担当の白川氏とともに、10年の足跡を振り返った。

VARIOUS ARTISTS 『Brainfeeder X』 Brainfeeder/BEAT(2018)
サンダーキャットの『Drunk』という象徴的な作品
――〈洋楽が売れない〉という風潮があるなか、ブレインフィーダーは日本で大きな支持を集めてきた印象です。そのあたり、実際どうなんでしょう?
若鍋「ビートが長年扱ってきたエレクトロニック・ミュージック系でいうと、やはりUSがマーケットとして大きいのと、ワープやニンジャ・チューンといったレーベルはUKが本国というのもあり、USとUK、それからヨーロッパの各国がマーケットの中心になっていて、そこに日本も含まれる。そのなかで、ブレインフィーダーは、どんなリリースでも日本が上位に顔を出しているので、レーベルとしての人気が定着しつつあると言っていいと思います」
白川「たぶん、時代とも合っていたと思います。ブレインフィーダーが設立された2008年というのは、ワープやニンジャ・チューンが立ち上がってから20年近く経った頃で。2000年代に入ってジャンルが細分化していくなか、それぞれのレーベルが試行錯誤していた時期ですからね」
――2000年代のワープは、バトルスなどのロック・バンドと契約したり、新しい展開を見せていましたよね。そこからビート・ミュージックの新鋭として台頭したのがフライローでした。
白川「そうそう。時代がそういうふうに変わっていくなかで、ブレインフィーダーのアーティストは、音の表情もそれぞれ全然違う。〈一つのお皿にいろいろな料理が乗っている〉みたいな感じが、好奇心旺盛な日本のリスナーと上手くマッチしていった印象です」
――特にヒットしたのはどの作品ですか?
若鍋「やっぱり、サンダーキャットの『Drunk』(2017年)ですね。ファースト(2011年作『The Golden Age Of Apocalypse』)とセカンド(2013年作『Apocalypse』)も好調でしたけど、ポテンシャルを考えたらまだまだだと思っていたので。近年になってレーベルのブランド力が上がったのと、アーティストのキャラクターが認知されたタイミングが重なったことで、象徴的な作品になったのかなと思います」
白川「あとは直前に、カマシ・ワシントンの『The Epic』(2015年)が出たのも大きかった気がします。フライローの登場でLAのビート・シーンが盛り上がりを見せたあと、カマシのようなジャズにも注目が当たったことで、LAコミュニティーの横の繋がりでもさらに底上げがあって。それが全世界的なトレンドにも繋がっていきましたしね」