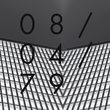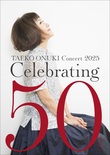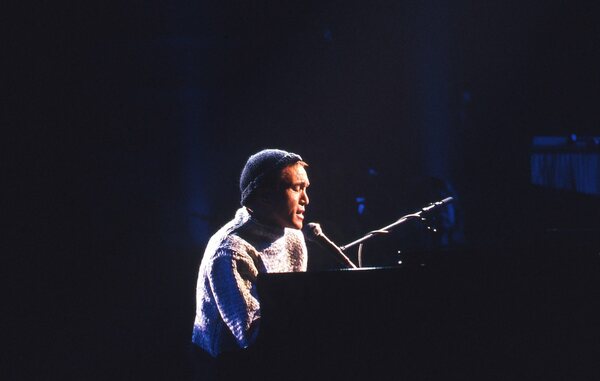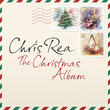〈ユキヒロ終わり〉は共通言語
――今日、大井さんはSIMMONSのドラム・パッドを持ってきてくれたんですよね?
大井「高橋さんといえばSIMMONSですからね。見てください、まずこの見た目、最高じゃないですか? いま、電子ドラムっていろんなメーカーから出ていて、大抵は生のドラムをモディファイした形状だったり、サウンドにしても〈どれだけ生ドラムに忠実か?〉が求められたりしていますけど、僕が電子ドラムに求めているのはそんなことじゃない。このハニカム構造に、電子ドラムとしての誇りを感じるんですよ。

厳密にいうとこのSDS1000は、高橋さんの使用モデルと全く同じではないんですけどね。高橋さんが使ってたのは確かSDS-Vだったかな(YMOの83年作『サーヴィス』などで使用)。とはいえSIMMONSを購入したのは間違いなく高橋さんの影響です」
――プレイヤーとしては、どんなところに影響を受けていますか?
大井「わかりやすい例で言うと、やっぱり〈ユキヒロ終わり〉ですかね(笑)」
――曲がドラムのフィルで終わるという、YMO独特のアレンジ。
大井「そう、それです(笑)!」
網守「DAOKOのリハーサルでも普通に〈ここはユキヒロ終わりで〉っていう会話が飛び交ってて(笑)、それが共通言語としてどの世代にも通用する状況は面白いですよね※」
大井「失礼を承知で言いますが、よく高橋さんって〈本当はドラム上手い〉みたいな言い方されるじゃないですか。リンゴ・スターでも未だにありますよね、〈彼のドラムは上手いのか?論争〉ってやつ(笑)。僕は高橋さんもリンゴも、とてもクレバーな素晴らしいドラマーだと思っています。どんなスタイルに対しても寄り添ったプレイができるというか。〈このスタイルしか叩けません〉みたいなタイプのドラマーではないところがすごいなと思う。でも、YMOは全員そうですよね。テクノじゃない音楽も、普通に演奏できるところに魅了されます」
――実はYMOって凄腕のスタジオ・ミュージシャンの集まりで、ライブとか途轍もなく上手いんですよね。当時は〈ピコピコ〉なんて言われてたけど、さっき網守さんが言ったように作品ごとに全く違う音楽をやっていたし。
大井「しかも、音楽ジャンルを飛び越えるだけじゃなくて、お笑いまでやっちゃいますからね(笑)。〈トリオ・ザ・テクノ※〉とかいま観ても笑える。ある一線を超えちゃったプロフェッショナルって、自分のイメージとかに対して寛容になれるんでしょうね。音楽だけ素晴らしい人はたくさんいると思うんですけど、全方位的に突き抜けた存在ってなかなかいない」
※TV番組「THE MANZAI」で、〈トリオ・ザ・テクノ〉の名で漫才を披露していた

網守「いまの時代じゃ考えられないですよね。当時の日本がそういう空気だったのかな。アンビヴァレンスで、表現規制もいまほど厳しくなくて。スタッフもみんな若かったらしいですよね。当時のYMOのツアーの集合写真を見たことがあるんですけど、そこに写っているメンバーやスタッフ、全員30代以下なんですよ。僕ら、そういう現場を経験したことないじゃないですか」
――以前、岡本太郎記念館の館長・平野暁臣さんにインタビューをした時、大阪万博(70年開催)のコンテンツづくりの中枢を担っていたのも30代の若者たちだったと聞きました。
網守「もちろん、インディペンデントなシーン、ユース・カルチャーは若者が中心ですけど、いわゆるメイン・ストリームがそういう空気感だったのは、単純に羨ましいです。それと同時に、あれだけメジャーな存在になっても批評精神を持ち続けていたこともすごい。現代は批評もすっかり消費対象になってしまったし、音楽はベタでエモいことが重視されてるように僕からは見えてるんですけど、YMOは作っている音楽を自らネタ化して簡単に消費させない構造を作っていたと思うんですよね。YMOを聴くことは、もちろん音楽を楽しむこともあるけど、そういう社会の構造や時代の雰囲気そのものを聴くことでもある気がしますね」