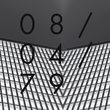アングルを変える手法
そうした数々の端緒を掴んだ髙城は作品制作を敢行。ceroのサポートを務めるドラムスの光永渉やヴィブラフォン/コーラスの角銅真実、キーボードの伴瀬朝彦やサックスのハラナツコといった親交の深いミュージシャンに加え、SOIL &“PIMP”SESSIONSの秋田ゴールドマン(ウッドベース)、松井泉(パーカッション)、中山うり(トランペット/コーラス)、武嶋聡(クラリネット他)、田島華乃(ヴァイオリン)、高田漣(ペダル・スティール)といった第一線で活躍するプレイヤーをフィーチャー。さらにヒップホップとダンス・ミュージックを横断するビートメイカーにして、過去に“ロープウェー”でコラボレーションを行ったsauce81を共同プロデューサーに迎えたファースト・アルバム『Triptych』は完成した。その残響にフォークやブルース、ジャズやソウルが香るルーツ・ミュージックに根ざした楽曲の数々を聴き進めていくうちに、ゆったりとした流れから時間感覚や遠近感が失われ、幻想的な風景がゆらゆらと立ち昇る。
「この作品の音楽性それ自体、オーセンティックなものなんですけど、通常ではあり得ない混沌としたアングルから表現することで、禍々しさや不気味さが香ってくる作品にしたくて、そのためにsauce81に声をかけさせてもらいました。例えば、シェイカーやタンバリンは、通常、遠いところでさりげなく鳴らす楽器ですけど、彼はそれを耳の真横で演奏しているかのように大きい音で鳴らしたり、バンド音楽をやっている人にはない音響感覚、バランス感覚を持っていて。“ロープウェー”の作業もまったくストレスがなかったし、今回の作品でも自分が求めるイメージを具現化するために必要不可欠だったんです」。

Shohei Takagi Parallela Botanica Triptych KAKUBARHYTHM/ソニー(2020)
ダメージ・ジーンズのようにあえて汚すように加工した独特な音の質感と、地場が狂ったように感じられる音響構築が大きな特徴である本作。そのヒントとなったのは、アメリカーナにアンビエントの発想を持ち込んだプロデューシングによって、エミルー・ハリスの『Wrecking Ball』(95年)やウィリー・ネルソンの『Teatro』(98年)をはじめ、数々の傑作アルバムを生み出したダニエル・ラノワ。そして、90年代にロス・ロボスやその派生プロジェクトであるラテン・プレイボーイズなど、メジャー・フィールドで先鋭的な音響実験を繰り広げたプロデューサー・チーム、ミッチェル・フルーム&チャド・ブレイクのサウンド・アプローチだったという。
「ローファイというと、今はチープな機材を用いたベッドルーム・ミュージックの音質を指しがちですけど、ミッチェル・フルーム&チャド・ブレイクに感じる〈ローファイ〉というのは、例えば、音から荒れ果てた荒野のような風景をイメージさせるために、クリーンに録った音をアンプやエフェクターを通して加工したり、汚してみたりっていう、もっと抽象的な、概念的なもの。だから、単に音質が悪いという話ではなく、キッチュなものだったというか、いかがわしさ満載のエキゾ音楽やモンド・ミュージックがそうであるように、ポスト・モダン的に表現のアングルを変える手法だったんですよね。当時、高校生だった僕はその意図がわからないなりに、彼らが手掛けた作品から立ち昇る独特なムードを感じていたことを思い出して、自分も今の時代において異なるアングルを提示できないかなって」。