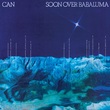70年代のドイツ・ロック・シーンを象徴するバンド、カンの全アルバムが2020年に再発されたことは、ここ日本で大きな話題になった。2021年4月には、それらの作品のストリーミング・サービスでの配信も解禁され、より多くのリスナーが彼らの音楽の魅力に触れることができるようになっている。
そんな好タイミングに、カンの伝説的なパフォーマンスを最先端の技術でよみがえらせる〈CAN:ライヴ・シリーズ〉が始動。その第1弾として、ライブ・アルバム『Live In Stuttgart 1975』が5月28日(金)にリリースされる。
今回Mikikiは、〈Jazz The New Chapter〉シリーズの監修者として知られる音楽評論家の柳樂光隆に、カンの音楽と『Live In Stuttgart 1975』での演奏を分析してもらった。〈フリー・ジャズ〉というキーワードから出発し、スタジオ・アルバムとは全く異なるカンのライブ・サウンドを深く覗き込んだ先で見えたものとは? *Mikiki編集部
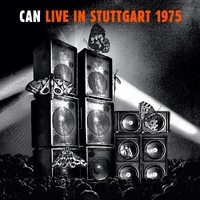
CAN 『Live In Stuttgart 1975』 Spoon/Mute/Traffic(2021)
カンはフリー・ジャズなのか?
カンについての資料やテキストを見ると、〈フリー・ジャズ〉という単語が必ずと言っていいほど出てくる。僕はスタジオ・アルバムのCDならほぼ持っている程度にはカンのことが好きだったが、カンはなんとなく聞き流せるのが好き、みたいな感じで好きだったこともあり、ディテールについてはあまり考えたことがなかった。ただ、今回、突然その部分が気になり始めてしまったので、そこにフォーカスして聴いてみて感じたことから始めたい。
どうやらドラマーのヤキ・リーベツァイトの出自がフリー・ジャズ畑だったというのが、〈フリー・ジャズ〉という単語が出てくる理由らしい。たしかにカンに加入する前の60年代にはドイツのフリー・ジャズの巨匠マンフレッド・ショーフのグループで活動していたことがあるし、アレキサンダー・フォン・シュリッペンバッハによる欧州フリー・ジャズの名盤『Globe Unity』(66年)にも参加している。それらのアルバムはごりっごりにヨーロッパのフリー・ジャズのサウンドなので、ヤキ・リーベツァイトがフリー・ジャズ・ドラマー〈だった〉のは間違いない(ちなみにアメリカのフリー・ジャズでは、60年代後半からはルールやコンセプト、編曲やアンサンブルを意識した作品が増えていたので、そういった〈ポスト・フリー・ジャズ〉みたいな流れとの呼応という話なら理解できる。例えば、フリー・ジャズのシーンにいたサックス奏者のマリオン・ブラウンが75年に発表した『Vista』にはのちにアンビエント作品で知られることになるハロルド・バッドが参加していて、音楽的にもミニマル且つアンビエントな要素がかなりある作品になっていたり、ヒッピー経由のインド音楽の要素も色濃く、カンにも通じる部分がある)。
フリー・ジャズとは対極にあるビートや演奏
ただ、それとカンを結び付けて、フリー・ジャズとの関係を語ることに関しては無理がある見解だと言わざるを得ない。カンを聴いたことがある人ならわかると思うが、カンでの活動においてはヤキ・リーベツァイトのドラミングはまったくフリー・ジャズではない。なんなら1ミリもフリー・ジャズではない、とさえ言える。カンでのヤキ・リーベツァイトの演奏はひたすらミニマルだ。よく言われることではあるが、まさに半分人間で半分マシーンという感じで、同じテンポで同じパターンを叩き続ける。ここにはジャズ成分はほとんどない。カン以降のヤキ・リーベツァイトに関しては、むしろフリー・ジャズとは対極にある演奏をしていると言っていいのではないだろうか。
そして、そんなミニマルなビートがあれば、バンドの演奏もそれと無関係とはいかない。ヤキ・リーベツァイトのビートがあり、そこに合わせてゆったりとグルーヴし続けるベースがあり、そこに様々な即興演奏を重ねることで、あの延々に聴いていられるような心地よさが生まれる。
そこでそのリズムの上に乗っているものを考えてみると、それらもまたフリー・ジャズと呼ぶのがふさわしいのかわからないものばかりだ。そもそも即興=フリー・ジャズなわけではなく、フリー・ジャズだと言われるような即興には敢えて〈フリー〉と呼ばれるような抽象度の高さや無軌道さがある。どんなに過激な即興に聴こえていてもチャーリー・パーカーはフリー・ジャズにはなりえないし、ジミヘンだってフリー・ジャズではない。言うまでもないが、基本的にカンのメンバーの演奏はロックの文脈にあるものだ。サイケデリックなヒッピーのロックの延長にあると言っていいとは思う。たまに“Aumgn”(71年作『Tago Mago』収録)みたいな特殊な曲もあるにはあるが。
なので、正直、僕はカンのどこにフリー・ジャズ性があるのかはよくわからないと思っている。とはいえ、ジャズと関係のある要素が全くないとも言えない、とも思っている。