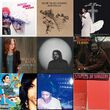94年に最初のコンピレーションアルバムをリリースしてから、2024年に30周年を迎えた『Free Soul』。これを記念して、『Legendary Free Soul ~ Supreme』『Legendary Free Soul ~ Premium』という2作のCDがリリースされた。さらに今回、橋本徹(SUBURBIA)が監修・選曲を担う7インチシングルのシリーズ〈Free Soul 7inch Collection〉がリリースされる。その第1弾は、11月3日(日)の〈レコードの日 2024〉の対象作品として発表される6タイトル。ジャクソン・シスターズ、オデッセイ、テリー・キャリアー、コーク・エスコヴェード、ジャクソン・ファイヴらの人気曲が集まっており、連続して12月21日(土)にも6枚のリリースが決定している。
今回はこの〈Free Soul 7inch Collection〉について、音楽評論家の柳樂光隆(Jazz The New Chapter)が橋本に話を聞いた。2人が選ぶ〈7インチ化したいFree Soul的6枚・12曲〉の記事とともに楽しんでほしい。
フリー・ソウルは〈なんでもあり〉だけど〈なんでもいい〉わけじゃない
――フリー・ソウルが30周年ということで、橋本さんはいくつか取材を受けているじゃないですか。そこで〈フリー・ソウルとは何か?〉〈フリー・ソウルが何を変えたか?〉といったことは話されていたので、今回は7インチをリリースするということもあり、選曲の基準について伺いたいんです。
「パーティーではその時に各DJがかけたいものをかけていただけなんだけど、僕がコンピレーションCDに入れるような曲のテイストが一つの大きな柱ではあったかな。ただ実際は、〈Free Soul Underground〉とかの現場はもっと自由で、毎回超満員だったから、なんでもありの世界で。
それと、コンピCDとクラブの現場は関連しつつも独立して存在していて、特に初期はそれぞれで楽しまれていたという事実もあると思う。〈Free Soul Underground〉に遊びに来ていたけどコンピCDを買っていない人はいたし、いわゆる渋谷系の人や小箱クラブで遊んでいた人とフリー・ソウルのCDを買っていた層は、まったくかけ離れてるわけではないけれど、ちょっと違ったかなと振り返ってみて感じるかな。CDの認知度が上がるにつれて、そこが一つに合流していった印象はあるけど。
94年頃の現場は山下洋が4番でピッチャーという感じでロック寄りのテイストもあったし、ダンスクラシックやディスコクラシックの要素が入ってきた時期もあるし、90年代だからヒップホップの要素も当然入ってきたし……そういう雑多な雰囲気がフリー・ソウルの礎になったんだよね。現場ではもちろん90年代前半のUKソウルやアシッドジャズはかなり定番だったけど、コンピCDではストライクゾーンを絞って選曲していたから70年代のソウルミュージック周辺のグルーヴィー&メロウな音楽を集めていて」
――でも枠組みはあったわけですよね。
「うん、ある程度はね。ただ現場では、7人のDJがその枠を広げる試みをあの手この手でしていた感じで。例えば二見(裕志)さんがドラムンベースをかけ始めたり、小林径さんがブルース・スプリングスティーンの“Blinded By The Light”を突然かけてみたり。当然、僕のコンピでの選曲が屋台骨になっていてフリー・ソウルのイメージを代表していたけど、パーティーでは7人の個性で自由に選曲していたんだよね」
――とはいえ、〈この範囲から出たら行きすぎ〉という境界線はあったわけですよね?
「僕自身は感じていたね。ちょっとベタすぎたり、尖りすぎた選曲でお客さんが引いちゃったり、現場感に合わなかったりするのは違うなと」
――僕も「Jazz The New Chapter」シリーズで〈ここからここまではあり〉という枠組みを決めて仕事をしているんですよね。
「フリー・ソウルでは、その観点はコンピCDにはかなりあるね。これ以上80sっぽいものは入れたくないとか。飛び道具的にジプシー・キングスの“Djobi, Djoba”をCDに入れたことがあって、最高だけどギリギリだなって思った。そういう曲は、現場では盛り上がるけどね。ノーランズの“I’m In The Mood For Dancing”とかも、ハッピーだけどギリギリ(笑)。ジャズ系ならロニー・ジョーダンやトーキング・ラウド系はいいけど、US3はNGとか。シェリル・リンの“Got To Be Real”とかアルトン・マクレイン&デスティニーの“It Must Be Love”とかエモーションズの“Best Of My Love”とか、スウェイビートのダンスクラシックは人気だったし、僕もCDに入れたことがあるけど、DJでかけたことはほとんどない。そういう感覚は現場では空気でわかるし、それが感じられないDJはつまらないよね。
僕は〈なんでもあり〉とよく言うけれど、〈なんでもいい〉わけじゃない。今となっては当時感じていた微妙なニュアンスの違いがわかりづらいかもしれないけれど、そういう音楽性と精神性、ポップとスピリチュアルな何かの両立はすごく大事だった。
他のイベントで〈選曲がダサいな〉と思っても、フリー・ソウルのレギュラー7人はそういうハズし方は絶対しない信頼感がある人たちだったのは大きいね。二見さんがドラムンベースをかけ始めた頃、オーディエンスにとってはハズしだったかもしれないけれど、自分はそれを求めていた感覚があったし」
――ロニ・サイズや4ヒーローはフリー・ソウルとも親和性があったわけですしね。
「そう。それは実際、歴史に証明されたわけで。それと当時の渋谷や下北沢の空気感は、むしろポピュラリティのある曲をかける時の方が気を遣ったかな。逆にCDで、現場でかけなかった曲を勇み足で収録したこともあって、例えば今回のラインナップだったら“君の瞳に恋してる”(ボーイズ・タウン・ギャング“Can’t Take My Eyes Off You”)はそういう曲かも。“グリグリ”(リセット・メレンデス“Goody Goody”)は二見さんがかけていて、グレッグ・ナイスも入ってるから『Free Soul 90s』シリーズに入れたけど、僕は現場ではかけなかった。持ち時間45分のDJで回している中で、無理にそこまで行こうとはしなかったんだよね。
和モノの混ぜ方も同じで、大貫妙子の“都会”は自然と混ぜられたけど、“真夜中のドア”(松原みき“真夜中のドア〜stay with me”)は意識的にという感じで。そうやって一線をこえて外側へ行くのは、やっぱり二見さんが多かったかな。で、他の誰かは〈これは違うよ〉みたいな顔をしていたり(笑)」
――フリー・ソウルのメンバーの間にも緊張感はあったわけですね。
「みんな素晴らしいDJだし、他人と同じことはしたくないから、僕が考えるフリー・ソウルそのままの選曲をしようとは思っていなかっただろうね。いちばん年長の径さんが70年代のロックをかけてきたら僕もデヴィッド・ボウイの“Starman”を敢えて混ぜてみたり、連想ゲームで幅が広がっていったというか。当時はCDだけでなく、盛り上がっている現場があったからそういう精神性は自然と大事にしていたんじゃないかな。
初期の〈Free Soul Underground〉の音楽性はもろイギリスの流れを汲む感じで、80年代はスタイル・カウンシルが好きだった人たち、その流れでUKソウルやアシッドジャズが好きだった人たちが、レアグルーヴの東京版的に70年代のグルーヴィーだったりメロウだったりするソウルミュージック周辺をかけるイベントだった。それが96、97年頃になるとピュアな時代が終わって拡散していって、ヒップホップやダンスクラシック系の人も自然と混ざって脱線・拡大していく時期になった。それこそMUROくんとかと一緒にやるようになったり。フリー・ソウルのコンピも90年代後半になってくると様々なテイストが混ざって、パーティーオリエンテッドになっていったから、初期の爽やかな感じの方が好きだっていう人もいたりしたね」