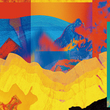エスケーピズムには行かないで、前を向く
――アルバムのオープニングナンバー“U b u g o e”から、そんな感じですね。音を削ぎ落としたトラックのなかで、研ぎ澄まされたビートがメロウなグルーヴを生み出していく。
「この曲はビートとアコースティックギターで作っていたんですけど、どんどんギターが溶けていったんです。エフェクティブな使われ方をするようになった。まるで自分のアイデンティティーが瓦解していくような感じでした。ブレイクビーツとかチョップしてビートを作っていくのは『HEX』(2018年)ぐらいからやってきたんですけど、それが自分の血肉になったというか、すごく自然なかたちで曲に取り入れられるようになった。バンドにベースが入ったことも大きいですね。ベーシストのマーティ(・ホロベック)が持っているグルーヴ感と僕の歌のリズムを擦り合わせながら作っていったんです」
――途中で入ってくる、黄昏れたトランペットが効果的ですね。
「〈主人公は今、幸せじゃないんだろうな〉と思いながら曲を作っていました。この曲の気怠さや悲しさは今年の年明けに感じたことからきていて。虚無感のなかで1年が終わって年が明けたとき、誰も外に出ないし実家にも帰らない正月を迎えた。そのときに思ったんです。今年はオリンピックも始まるし、これからはウイルスとの闘いじゃなく、人間の恨みや恐怖と闘わなくちゃいけないんだろうなって。自分はそういうものに参加したくないし、そういうことに苦しんでいる人たちに向けた音楽を作らなければいけない。空っぽの東京のフォークミュージックを作ろうって」
――その気怠さって、日本だけではないですね。最近のUSインディーのサイケデリックなサウンドって、どこか感覚を麻痺させているようなところがあって。
「わかります。アメリカやヨーロッパの音楽シーンは日本よりも大変ですもんね。亡くなっている人の数も日本とは桁違いだし、リリースされる海外の音源を聴きながら〈元気ないな〉って思ってました。そこで、僕たちはエスケーピズムには行かないで、
――ネットやメディアも、ある意味、ウイルス的なところがありましたね。不安や分断を煽るような情報を無責任に流して。
「そうですね。みんな過敏になっているから、その影響でへこまなくていいところでへこんでしまう。それを僕なりに励まして、シリアスなときはシリアスだけど常にポジティブでいようとしていました」
――だからといって、そのポジティブさを押し付けようとはしていない。サウンドの佇まいは穏やかなクール。そんななかで、ストリングスが重要な役割を担っているように思いました。
「今回はがっつり(徳澤)青弦さんと共作させてもらったんです。ロックにおけるストリングスサウンドを、新しいステージに上げるつもりで青弦さんに声をかけました。海外では、ニコ・ミューリーとかヨハン・ヨハンソンとか、クラシックや現代音楽をやっていた人たちがロックに関わるようになってジャンルの垣根がどんどんなくなってきている。ナショナルやレディオヘッドみたいに、クラシックを学んだメンバーがいるバンドは新しいサウンドを生み出しているじゃないですか。そういう動きが日本のロックシーンには見当たらず、それを自分たちがやりたいと思ったんです」
――コロナの最中に大人数のストリングスを撮るのは大変だったのでは?
「今回、無謀にもストリングスを一発録りでレコーディングしたんです。北海道に芸森スタジオっていうジョージ・マーティンがデザインした広いスタジオがあって、そこでバンドもホーンもストリングスも何曲か一発録りができた。録音した音源に合わせるのと、一緒に演奏して合わせるのとは全然違うんですよ。それは音を聴いてもわかる。やり方としては古風ですけど、血が通った音楽にするためにそうしたんです」
――核になる演奏に血が通っているから、緻密に作り込んでも温度感が伝わるんでしょうね。ストリングスをフィーチャーした曲では“Helpa”が印象的でした。どこか童謡みたいなメロディーで、不思議な雰囲気がありますね。
「自分のなかでは民族音楽を西洋に翻訳化したみたいな感覚があって、伊福部昭の音楽に近いかもしれない。ピアノなんだけど和音階で、明治時代に日本人が無理矢理、背広を着ているような感じ(笑)。ちょっと純文学の香りもするし」
――タイプライターみたいな音が聴こえてきますが、あの音は?
「タイプライターです。ドラムの工藤(明)くんのアイデアだったんですが、
――茶室的な音響空間、おもしろいですね。
「どの曲も最初に〈こういう景色〉っていうビジョンがあって、その景色のなかで音が鳴ってたり、主人公が歩いてたり、生活してたりする。そこに音を近づけていくんです」
――では、タイトル曲とも言える“HAKU”はどういうイメージで作られた曲ですか?
「この曲は最初、イントロの音が出来て、このイントロだったら、工藤くんならこんなドラムを叩きそうだな、とか、地響きを立てるようなベースを入れようとか、音遊びのように作っていきました。綺麗なタイルを集めてモザイクを作っていくような感じ。この曲と“U b u g o e”と“Eternal”が出来たときに、これで新作は大丈夫だ、と確信しました。この3曲が今年の音だと思ったんです」
――“Eternal”から“EDEN”への流れはアルバムの最深部だと思いました。アンビエントな穏やかさとロックのエモーションが溶け合ってスケールの大きな世界を生み出している。“EDEN”でついに炸裂する岡田(拓郎)くんのギターも素晴らしい。
「まさに岡田節ですよね。今回はギターソロを許すような曲があまりなかったので、〈この曲では弾きまくろう〉となったんです。岡田くんが得意技を発揮して、どんどん駆け上がっていくようなギターを弾き、そこに工藤くんが力強いドラムを叩く。一緒に演奏していて、めちゃくちゃ感動しました」