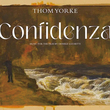ロック史に燦然と輝くレディオヘッドの傑作にして実験作『Kid A』(2000年)と『Amnesiac』(2001年)。両作のリリースから20年後の2021年、双子のアルバムが未発表曲などを加えたひとつの作品『Kid A Mnesia』となった。今回は、これを機に、初の単著『スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック』を上梓したことで注目を集めている新進気鋭の批評家、伏見瞬に本作を多角的に論じてもらった。『Kid A Mnesia』は誰がために鳴らされるのか? *Mikiki編集部

トム・ヨークにはレノン&マッカートニー〈程度の〉作詞能力しかない
レディオヘッドが巨大な存在になったのは、トーマス・エドワード・ヨークが作詞家として二流だったからだ。〈二流〉が侮蔑の言葉として響くなら、あるいはこう言い換えてもいい。レディオヘッドが商業的にも批評的にも成功したのは、トム・ヨークがジョン・レノンとポール・マッカートニー程度の作詞能力しか持たなかった故にほかならないと。
想像してほしい。“Strawberry Fields Forever”の言葉をボブ・ディランが綴ったとしたら。“Eleanor Rigby”の情景をレナード・コーエンが描いたとしたら。きっとその曲はあまりに遠くにいってしまって、だれにも気づかれずにうち捨てられていただろう。レノンのシュールレアリズムはどうにも感傷的で、マッカートニーの物語はどうにも図式的だ。
ビートルズの“The Word”を聴くたびに、ぼくは赤面する。〈その言葉を唱えれば君は自由になれる/それは「Love」〉。『Rubber Soul』でサウンドとソングライティングの実験にのりだすと同時に、ビートルズのリリックはポエジーを取り違えた。“Across The Universe”や“Fool On The Hill”より、“Please Please Me”や“She Loves You”“No Reply”のフロウの方が煌めいていることを、自分自身で気づかないまま解散した。
だからこそ、言葉の退屈さに支えられてこそ、彼らは新たな音像とコンセプトの結実に成功した。ポップな存在のまま、インド宮廷音楽や具体音楽などを取り込み、芸術作品としての〈アルバム〉を作り上げた。和音と音像の新たな組み合わせを示した。それは、ディランやコーエン、あるいはスモーキー・ロビンソンやモリッシーのような詩人には真似できない大技だった。詩的天才は、自らの声を伝えるためにむしろ保守的な形式を必要とした。ディランやザ・スミスの楽曲の伝統性に触れれば、それはすぐにあきらかになるだろう。詩的凡庸さが、ビートルズをポップの変革者に仕立て上げたのだ。
90年代中期、ギャラガー家の次男と三男はビートルズへの尊敬を臆することなく語ったが、実際にオアシスの楽曲を聴くとそこまでビートルズの匂いを感じない。レディオヘッドにこそ、ビートルズは宿っている。“Karma Police”が“Sexy Sadie”のコードとメロディーを引用していること、“My Iron Lung”のアルペジオが“Lucy In The Sky With Diamonds”のそれと似ていることだけでない。J.S.バッハとラヴィ・シャンカールとシュトックハウゼンとジャンプブルースとマーダーバラッド、その他諸々を折衷させた60年代後期のビートルズのように、レディオヘッドはピクシーズとジェフ・バックリーとDJシャドウとマイルス・デイヴィスとオリヴィエ・メシアンを混ぜ合わせる。
結果生まれたのが『OK Computer』だが、本作の有無を言わせない完成度のなかで、“Paranoid Android”や“Fitter Happier”のアイロニーは生硬く響く。〈神は子供達を愛する〉なんていう定型化したキリスト教的反語や、〈抗生物質漬けのカゴの中の豚〉なんていう笑えないメタファーでしか、社会の暗部を描けない。レディオヘッドのリリックは後期ビートルズのごとく、いつも閃きに欠ける。“Don’t Look Back In Anger”で、〈彼女の魂は滑り落ちていく〉という捻れた絶望を大勢に歌わせたノエル・ギャラガーの詩性は、トム・ヨークに望むべくもない。逆に、新たな魔術を編み出すレディオヘッドの冒険性は、オアシスに望むべくもない。