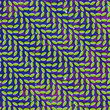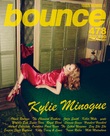いまやアメリカのインディーロックシーンを代表するバンドであるアニマル・コレクティヴのひさびさの新作『Time Skiffs』は、好評をもって迎えられている。年齢的にも精神的にも〈大人〉になった4人は、ここでバンド演奏に回帰し(録音はリモートだったそうだが)、いつになく伸びやかに、だがサイケデリアや神秘性や実験精神はそのままに、新たな音楽世界を描き出した。今回はそんなアニマル・コレクティヴの変化について、木津毅と柴崎祐二がそれぞれの視点から論じる。2人の論に共通するキーワードは〈成熟〉だ。 *Mikiki編集部

逃避的な子どもから社会を生きる大人へ――〈時の小舟〉に乗って遊ぶ喜びを再訪した意義
by 木津 毅
2000年代のアニマル・コレクティヴが放っていた輝きは、子どもたちが我を忘れて遊んでいるような邪気のなさから生まれるものだった。彼らのエクスペリメンタルポップにおける〈実験〉にはつねに遊戯性が伴っていた。そのサイケデリックな快楽性や親しみやすいメロディー、カラフルなサウンドのパレットによって描かれるイマジネイティブな世界は可愛くて、柔らかく、何より楽しいものとして鳴らされていたのだ。社会から離れた場所で自分たちの小さなユートピアを作るような態度はチャイルディッシュだ、逃避的だと揶揄されることもあったが、だからこそ自由な発想で伸び伸びとやれていたところもあるのだろう。
いっしょに遊んでいた子どもたちも、しかし、大人になってそれぞれの人生を生きなければならない。2000年代後半に隆盛したブルックリンシーンが離散するとともに、アニマル・コレクティヴの活動も次第に断片的になっていく。故郷のボルチモアで制作された『Centipede Hz』(2012年)のツアーでメンバーが疲弊したのち、エイヴィ・テアとパンダ・ベアはソロ活動によりフォーカスし、ジオロジストは育児に励み、ディーキンはバンドを休むことになる。ディーキン不参加の『Painting With』(2016年)はある意味、その時期のメンバーをどうにか繋ぎとめるようなアルバムだったと、いまから振り返ると感じられる。とりわけエイヴィ・テアとパンダ・ベアの得意な要素を並べた作品で、当時の個々の活動のフィードバックがダイレクトに表れていた。
また2016年、バンドはノースカロライナの反トランスジェンダー法案(そのひとのジェンダーアイデンティティーにかかわらず、生まれたときに割り当てられた性と同じトイレを使用しなければならないとするもの)に反対するライブアルバムをリリースし、2018年には(パンダ・ベア不参加の)オーディオビジュアル・アルバム『Tangerine Reef』で珊瑚礁破壊の反対を表明している。アニマル・コレクティヴを非政治的なバンドだと見なしていた自分は反省したものだが、ただ、彼らも年を取るとともにより社会に接近したのだと思う。無邪気だった彼らも少しずつ変わってきたのだと。
ところが久しぶりに4人が揃った『Time Skiffs』を一聴して、これはアニマル・コレクティヴがかなり生き生きと遊んでいるアルバムではないかと直感した。聞けばパンデミックで実際に会うことが難しかったために、できるだけオーガニックな音作りが目指されたという。結果、生楽器を生かしたまろやな音のタッチがフリークフォークとシンクロした初~中期を連想させるせいもあって、メンバー全員の音が『Centipede Hz』や『Painting With』よりも自然に混ざり合っているように聴こえるのである。何より、バンドがお互いの化学反応を楽しんでいる。エイヴィ・テアとパンダ・ベアの曲が繋げられた“Prester John”がその象徴で、それぞれの最近のソロ作(エイヴィ・テアの『Cows On Hourglass Pond』とパンダ・ベアの『Buoys』)より音のグラデーションの変化が顕著なアルバムに仕上がっている。アニマル・コレクティヴがまさにコレクティヴ(集合体)である意義を昇華した作品だ。
もちろん、彼らはもう逃避的な子どもではなく、社会の一員たる大人としてここにいる。けれどもタイム・スキッフ(時の小舟)に乗れば、いつだって、あのときいっしょに遊んだ喜びを訪れることができる。20年を超える時間を経たいまなお、アニマル・コレクティヴのカラフルな音は可愛くて、柔らかく、楽しい。