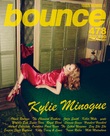個々の活躍も目覚ましい21世紀の最重要バンドが6年ぶりのオリジナル・アルバムを完成――直面する現実と豊かな創造性の間に浮かぶ時間の小舟はどこへ流れていく?
アニマル・コレクティヴの新作『Time Skiffs』は2016年発表の『Painting With』以来、実に6年ぶりのスタジオ・アルバムとなる。もっとも彼らはその間、何もせずに息を潜めていたわけではない。メンバーのパンダ・ベア(ドラムス/ヴォーカル)とエイヴィ・テア(ギター/ヴォーカル)はそれぞれ個性的なソロ作を発表してきたし、バンドとしても着実に野心的な試みを続けていた。彼らはここ数年、自分たちにレッテルを貼ろうとしてくる世間から一定の距離を保ちながら、マイペースに活動できていたのではないだろうか。
そもそもアニマル・コレクティヴほど、ある特定のイメージに基づくラベリングを退けてきたバンドもそうないだろう。2004年の『Sung Tongs』と翌年の『Feels』で摩訶不思議な音響フォークを展開し、フリー・フォークの旗手として注目を浴びるも、次作『Strawberry Jam』(2007年)ではエクスペリメンタルな色合いをグッと強め、そのラベリングをさらりとかわした。かと思えば『Merriweather Post Pavilion』(2009年)では60年代サイケ・ポップを浮遊感あふれる音響処理でアップデートしたようなとろけんばかりに甘い音世界を現出させ、前作で纏ったイメージをさらに上書きしてみせた。
自分たちのイメージと戯れながらそれを華麗に更新していく姿勢は、『Painting With』以降の活動においても一貫している。特に近年においては、映像との同期を念頭に置いた音作りへの関心が高まっているようだ。例えばシンセサイザー主体のサウンドで編まれたオーディオ・ヴィジュアル・アルバム『Tangerine Reef』(2018年)には、それが端的に表れていると言えるだろう。また昨年リリースした初の映画音楽作品『Crestone』では、電子楽器と生楽器を巧みに織り合わせ、遊び心に溢れるアンビエントを聴かせた。彼らは探究心の赴くままに、それまで主戦場としていた歌モノの世界からインストゥルメンタルの領域へと飛び込み、また新境地を拓いていったのである。

そしてこのたび、満を持して届けられたのが新作『Time Skiffs』だ。今作は、近年ずっと自分たちが張り巡らせてきた伏線を一気に回収しにかかるかのような、会心の一作に仕上がっている。冒頭を飾る“Dragon Slayer”から、これまでのスタジオ・アルバムと比していっそう精緻になった音響デザインに驚かされるが、そこには近年の映画音楽への取り組みなどを通して得た成果が確かに流れ込んでいるように感じられる。また一音一音の明瞭さとサウンド全体の浮遊感を両立させた絶妙な音作りからは、ここ数年ますます高まっているであろう彼らの音響面へのこだわりが窺える。
加えて、その音響の皮によって包まれた瑞々しいメロディーも見逃せない。“Car Keys”“Walker”“We Go Back”……どの曲にも彼ら一流のひねりが効いてはいるものの、いずれもかつてないほどまっすぐな美しさを湛えているのだ。〈ひねくれ〉の季節を過ぎて人間的に一皮剥けた彼らの現在の姿を反映している、と評したらさすがに短絡的すぎるだろうか? いずれにせよ、インストの海への沈潜を通して彼らの得たものがとびきりポップな歌モノへと完璧なまでにフィードバックされている様は、感動的である。
「音楽を聴くということは、別の時間/空間に連れて行ってもらうための手段だ」とエイヴィ・テアは語っている。わかりやすいイメージに押し込められるのを回避しながら、アニマル・コレクティヴがこつこつと作り上げた今作は、彼の言葉通り〈ここではないどこか〉へと我々を連れていってくれる方舟であるのかもしれない。
アニマル・コレクティヴの近作を紹介。
左から、2016年作『Painting With』、2018年作『Tangerine Reef』、2021年のサントラ『Crestone』(すべてDomino)
メンバーのソロ近作を紹介。
左から、パンダ・ベアの2019年作『Buoys』、エイヴィ・テアの2019年作『Cows On Hourglass Pond』(共にDomino)