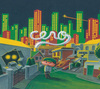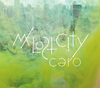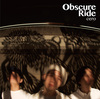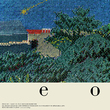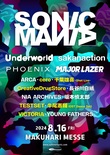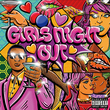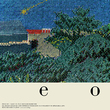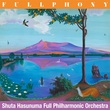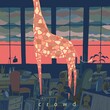目的はなくムーブがあった
──ストリングスを交えて、アメリカーナに通ずるオープニングナンバー“Epigraph”は髙城さんのソロに通じるパーソナルな世界が拡がっているように感じましたし、この曲では〈真新しいものがなくなりようやく/静けさの中ページが開く〉という一節が歌われていますよね。
髙城「『Obscure Ride』や『POLY LIFE MULTI SOUL』は何かしらの野望や願望を持って、それを表現するにはどうしたらいいかというところで自分たちが動いてきたんですけど、今回はそうじゃなかった。自分たちのムーブが先にあって、それならばこういうことが出来るよという感じで可能性が開かれていく、そういう順番で事が動いていったんですよね。だから、この曲の歌詞を書く際にアルバムを俯瞰で眺めた時、この作品は野望や願望を持たずに作ったものですよというステートメントとなる言葉が生まれたんだと思います。
ただ、目的なし、プランなしで作ったアルバムではあるんですけど、自分の作詞のクセとして、どこかしらに言葉のリンクを散りばめていって、結局、出来上がってみれば、ストーリーじみたものがぼんやり浮かび上がってくるんですよね。そういう作品であるからこそ、アルバムタイトルを付ける段階で、そのぼんやりしたストーリーを支えるタイトルを付けてしまうと、みんなの捉え方が寄ってしまって、せっかくの余白や深みが狭められてしまうかもしれない。そこでセルフタイトルでそのまま『cero』でいいんじゃないの?という意見も出たんですけど、ceroという単語を言葉遊び的にいじった方がこのアルバムで遊んだこと、具現化したことに近いものになるんじゃないかということで『e o』に落ち着いたんです」
──コンセプトやストーリーは作品の雄弁なガイド役になる一方で、作品の想定外の広がりや聴き手それそれの自由な解釈を妨げる一面もあるかと思います。今回、作ったご自身たちにとっても新鮮に感じるという発言がありましたが、どのようなアルバムになったと思いますか。
荒内「自分にとっては、ブリコラージュ的な遊びのアルバムですかね。遊びというと軽く聞こえるかもしれないですけど、汲めども尽きない深みを感じます」
髙城「どういうアルバムなんだろうと、毎回聴くたびに他人事のように思う、第三者が作ったような作品ですね。
この作品は、例えば、コロナ禍の状況と結びつけて語ったりもできると思うんですけど、そういう解釈は長い目でみれば、風化して、切り離されていくでしょうし、全然それでいいというか、時間経過に左右されない強度を持った作品になっていたらうれしいですね」
ceroの過去作。
左から、2011年作『WORLD RECORD』、2012年作『My Lost City』、2015年作『Obscure Ride』、2018年作『POLY LIFE MULTI SOUL』(すべてKAKUBARHYTHM)
『e o』に参加したアーティストの関連盤。
左から、GUIROの2019年作『A MEZZANINE(あ・めっざにね)』(eight)、CRCK/LCKSの2023年のEP『総総』(APOLLO SOUNDS)、角銅真実の2020年作『oar』(ユニバーサル)