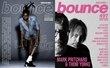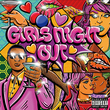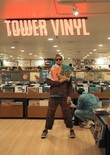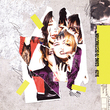シリアスな眼差しとサウンドの快楽
こういった反骨心は歌詞でも顕著だ。スターに登りつめた自身を見つめた1曲目の“Angel”では〈奴隷船に乗せられるなんてお断り〉とラップし、商業主義に走ることを拒否する。さらに“Broken”では、彼女の視点から描いた黒人コミュニティーの内実とメンタルヘルスに言及し、持ち前の秀逸な社会批評を披露してくれる。本作の歌詞はひとつひとつのフレーズが難しくなく、特定の人にしか伝わらない固有名詞も多くないシンプルな言葉選びを特徴としているが、描かれる機微や情動はとても複雑だ。その複雑さは一度聴いただけで消化しきれるものではない。それでも、グルーヴとして心地良い彼女のフロウを筆頭に、繰り返し聴きたくなるだけの軽さを演出する要素がいくつもあるおかげで、一回聴いたら満腹ということにはならない。ゆえに本作は非常に中毒性が高い。
そうした中毒性の助力となっているのがサウンドだ。随所で響きわたる甘美なコーラス・ワークはゴスペルのエッセンスが目立ち、シンコペーションを多用した肉感的なベースラインの数々にはファンクの香りが染み付いている。さらに豪快なストリングスと太いキックを刻むブレイクビーツが前面に出た“Gorilla”は、ア・トライブ・コールド・クエストあたりのジャジーなUSヒップホップを想起させる。これは恐らく、グライムから多大な影響を受けつつ、アメリカのポップ・ミュージックを愛聴してきた彼女の嗜好が強く反映された結果だと思う。本作は歌詞でシリアスな眼差しを見せつけながら、サウンドは気持ち良さという快楽性をアピールしている。このバランス感覚に筆者は、リトル・シムズの成熟と風格を見た。
『NO THANK YOU』は、言葉やサウンドなど、あらゆる面にいかなるものにも媚びないとする彼女の鮮烈な宣言が見受けられる。安易に時代の潮流と交わらず、自分の表現と想いにどこまでも忠実な姿はイギリスの音楽シーンのみならず、世界的に見ても稀有だ。UKラップ・シーンのアイコンとして注目を集めながらも、アフロスウィングを開拓したJ・ハスのように特定のジャンルという色を付けられずにここまで歩みを進められたのは、ひとえに自分の表現を追い求めてきたからだろう。
そのような表現がイギリスのハードな世情とも共振し、いまを生き抜くので精一杯の人たちにとっての光になっている様に、筆者はレベル・アーティストとしての側面を彼女に見い出してしまう。そんな戯言を言いたくなるほど、本作の批評眼は現在を鋭く射抜いている。 *近藤真弥
インフローの関連作を一部紹介。
左から、ソーの2022年作『Untitled(God)』(Forever Living Originals)、ブロークン・ベルズの2022年作『Into The Blue』(AWAL)、アデルの2021年作『30』(Columbia)
リトル・シムズの作品。
左から、2015年作『A Curious Tale Of Trials + Persons』、2016年作『Stillness In Wonderland』、2019年作『Grey Area』、2021年作『Sometimes I Might Be Introvert』(すべてAge 101)