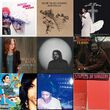驚きに満ちた編曲
78年。そんな変化を恐れないディランの初来日がどんなものになるか、まったく予想がつかなかった。大規模な世界ツアーの最初の訪問地ということで、何か新しい部分はあるに違いないとは思っていたが、12人という大編成のバンドには驚いた(メンバー紹介で、ディランは〈オーケストラ〉と呼ぶ)。そこには、ストーナー、スティーヴ・ソールズ、デイヴィッド・マンスフィールドといった〈ローリング・サンダー・レヴュー〉組もいたが、女性コーラス3人、有名セッションマンのスティーヴ・ダグラスのサックスとボビー・ホールのパーカッションはそれまでのディランのバンドにはなかった要素であり、そのサウンドはザ・バンドや〈ローリング・サンダー・レヴュー〉とはまったく異なるものだった。衣装に身を包んだバンドがソロを回すインスト版“A Hard Rain’s A-Gonna Fall”がいかにもショウの幕開けという感じで始まる構成のパフォーマンスは、新任マネジャーのもう一人のクライアントだったニール・ダイアモンドや、前年に亡くなったエルヴィス・プレスリーを意識したらしい。


その選曲は日本のプロモーターが送ったリクエストに応えたそうで、有名曲が大半だったが、曲ごとにさまざまなアレンジを施され、イントロだけでは何の曲かすぐにはわからない。この編曲とサウンドは賛否を呼んだが、当夜の客席にいた僕らは初めてディランを観られる喜びと大胆な編曲で大きく姿を変えた曲が次々と登場する驚きを受け止めるのでもう精一杯だった。確かに“Like A Rolling Stone”のような曲は本来の鋭さを失った感はあったが、スロウ・テンポに落とした“I Want You”をはじめ、編曲がメロディーの美しさを際立たせた曲も多かったしコンプリート版で初お目見えの“The Man In Me”のように、多彩なサウンドのなかでの比較的ストレートな解釈でかえって説得力を増した曲もあった。
実のところ、長いツアーの序盤だったうえに、ドラマーがビザの問題で急遽交替になった事情もあり、編曲はまだ試行錯誤中で、曲目や編曲が日々変化していった。それゆえ、ディランはライヴ盤の発表にためらいもあり、80年代には〈日本側の強い要望に負けた〉といった発言もしていた。だが、ツアーが続くうちに、サウンドがビリー・クロスのギターがもっと前に出たロック的なサウンドに向かっていったという証言もあり、結果的には、さまざまな編曲の可能性を探っていた日本公演が音盤化されたことはよかったのではないか。『The Complete Budokan 1978』のライナーで、評論家のエドナ・ガンダーセンも『Bob Dylan At Budokan』が〈その後の数十年で真価が大幅に見直され、ファンや評論家が冒険的なアレンジや挑発的なパフォーマンスを称賛するようになった〉と書く。
友人のシンガー・ソングライターで小説家のウェズリー・ステイスは、ディラン作品の表題、ジョン・ウェズリー・ハーディングを長年芸名に使っていたほどだが、ファンになったきっかけは、13歳のときに買った『Bob Dylan At Budokan』だと言っていた。日本盤だったので歌詞カードが付いていたうえに、ベスト盤のような選曲だったので、ディラン入門に最適だったそう。60~70年代に間に合わなかった世代には、『Bob Dylan At Budokan』がそんな役割を果たした人も多いに違いない。 *五十嵐 正
こちらは4CD仕様のボックスセット

この前後に発表されたボブ・ディランの作品。
左から、76年作『Desire』、78年作『Street-Legal』、78年の武道館公演の一部を収録したライヴ盤『Bob Dylan At Budokan』(すべてColumbia)