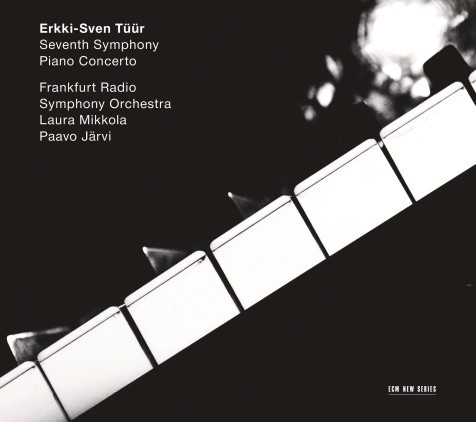これまで聴いたことのないひびき、ではない。未聴感ではない。かといって、よく知っている、慣れ親しんでいるわけではない。違和感はない、にもかかわらず、古いとはおもわないし、瞬間・瞬間のちょっとしたところに、しっかりとリアリティを感じる。わたしの心身は、妙に「いま」を、21世紀にはいって10年を過ぎた、過ぎてしまった、というリアリティを持つ。それがエリッキ=スヴェン・トゥールの音楽だ。
この作曲家の名を耳にしたのは1990年代の半ばだったのではなかったか。やはりECMからの『クリスタリサティオ – 結晶化』からだったと記憶する。旧ソ連邦の諸国から、少しずつ音楽が届き始めていた。エストニアといえば、いち早くアルヴォ・ペルトが知られていた。わずかに遅れて合唱の分野ではヴェリヨ・トルミスがいた。前者が1935年、後者1930年の生まれだから、1959年生まれのトゥールにとっては父親や叔父の世代にあたる。共通するものはたしかにある。あるのだけれど、隔たりも大きい。トゥールは、西ヨーロッパからアメリカ合衆国にかけての20世紀音楽は自分のものとしてすでに持っている。加えて、若き日に活動していたプログレ・バンドIn Speでの記憶は消えようもない。そうしたうえで、音楽をつくっていこうとする情熱と、どこか音楽のスタイルや歴史に対して抱かれている冷めた距離感とが、わたしにはけっして遠いものとはおもえなかったりする。
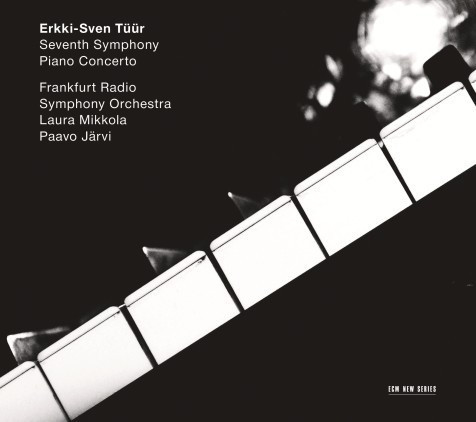
PAAVO JARVI,FRANKFURT RADIO SYMPHONY ORCHESTRA Erkki-Sven Tuur: Symphony No.7, Piano Concerto ECM(2014)
トゥール、ECMから6枚目(!)のアルバムは、2作品を収録。
仏典やガンディー、マザー・テレサといった人たちのことばをテクストとして用いている「合唱つき」の《交響曲第7番「Pietas」》(2009)。作曲家でもあるトーマス・ラルヒャーを初演時のソリストと迎えた(アルバムではフィンランド出身のラウラ・ミッコラ)《ピアノ協奏曲》(2006)。
20世紀半ばすぎまでは古い形式として冷笑されてきた「交響曲」は、いま、べつのかたち、新しい器として、作曲家に遇されている。この列島でもぽつりぽつりと生みだされているのは周知のとおりだが、さて、トゥールの作品は、どう聴かれるだろう?