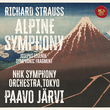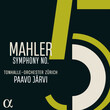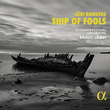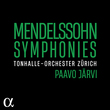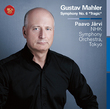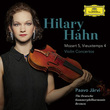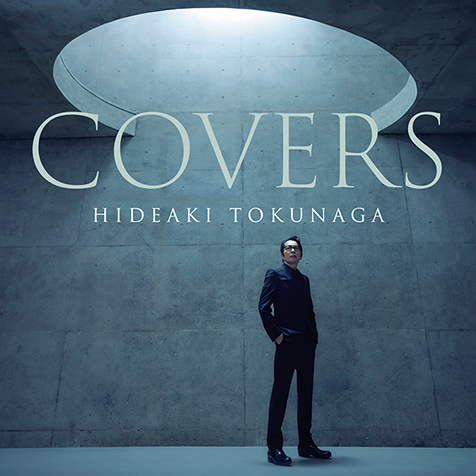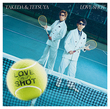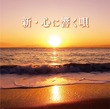年輪を重ねたことによる自らの変化も解釈に反映させながら音盤に刻む進境。彼が極めようとする頂は、さらに高い。
指揮者としてのディスコグラフィーが充実化の一途をたどる点では、文字どおり人後に落ちないパーヴォ・ヤルヴィ。首席指揮者のポストを2022年に退いてからも密接な関係を保つNHK交響楽団との最新盤はリヒャルト・シュトラウス。2023年4月定期公演のライヴ録音だが、そのジャケットに〈黒富士〉の通称を持つ北斎の版画を掲げたのは彼自身のたっての希望によるもの。日本発の“アルプス交響曲”であることを象徴的に示すための……。
「晴れ渡った空を従えた山頂。中腹に立ち込める入道雲。山麓に光る稲妻。これはシュトラウスが描いた情景そのものです(笑)。音楽と版画という異なる表現手段を用いながらも、ドイツと日本の偉大な芸術家の間に、自然と人間の関係性を扱う上での共通するスタンスまで感じられます。私にとって“アルプス交響曲”は人生のメタファーにも等しい作品です。登頂の過程、やがて襲う嵐……。これを我々が歳をとるにつれて内面に抱える苦難や危機と関連づければ、音楽の背景をなす哲学的思考も浮かび上がります。下山後の日没の情景、そして夜へ至る流れは〈告別〉そのもの。神へ捧げる祈りと感謝の点では、ベートーヴェンの“田園”と同様の精神性が認められます」
カップリングは同じシュトラウスの“「ヨゼフ伝説」交響的断章”。〈未知なる宝〉にスポットを当てる選曲も、パーヴォの好むところだ。
「編成が巨大な上に演奏が極端に難しく、実演で聴く機会に恵まれません。しかし原作のエッセンスを抽出した“交響的断章”は、リスナーに新鮮な喜びをもたらすと確信します。元々がバレエ音楽であることも手伝って、深遠な情調が息長く維持されたりはせず、演奏効果の高いチャーミングな場面が次々と入れ替わっていく。N響の演奏能力を生かす上でも適したレパートリーですね」
シュトラウスを筆頭とする後期ロマン派の音楽に対してN響が持つ〈伝統〉の力も生かせる?
「もちろん。偉大なドイツ系指揮者たちとステージを共にしてきた楽団ゆえのDNAですね。中でもシュトラウスの大家だったサヴァリッシュと積み重ねたものは大きい。仮に彼と共演した経験を持つプレイヤーの割合が減っても、合奏に脈々と受け継がれているのです。私はカーティス音楽院で勉強していた頃、サヴァリッシュのリハーサルを何度も見学しました。フィラディルフィア管弦楽団を相手にした“家庭交響曲”の稽古などは、まるで手取り足取りの授業でしたね(笑)」
昨年12月の日本ツアーでも客席を沸かせた、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン(DKB)とはハイドンの“ロンドン交響曲”が進行中。既に全12曲が収録済で、来日直前にリリースされたアルバム第2弾(2021年11~12月録音)では、第94番“驚愕”、第95番、第98番、第99番が耳にできる。その第98番ではフィナーレのみに用いられたフォルテピアノに独自のアイデアを盛り込むなど、相変わらず刺激と啓示に富む解釈を世に問うコンビだ。
「当時の演奏慣習に関する研究成果も踏まえて、アプローチを練り上げています。もしハイドンの交響曲が退屈に響くのなら、それは指揮者の持つイマジネーションが退屈なレベルだから! 彼が音楽に封じ込めた機智やジョークまで汲み取って始めて〈書かれたとおり〉の演奏が可能になる。DKBの持つ高い自発性と、ルーティンワークに陥らない合奏も大きな武器ですね」
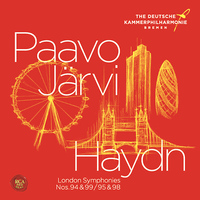
2019年から音楽監督をつとめるチューリヒ・トーンハレ管弦楽団とは、マーラーの交響曲全集という大プロジェクトがスタート。皮切りをなすのが第5番である(2024年1~2月の録音。Alpha、NYCX10516[国内盤CD])。
「過去の演奏と比べて、明らかに自分自身の変化を感じます。表現すべき事象に関して常に複数のレイヤーが共存しているようなマーラーの音楽に対して、それを掘り下げる上で必要な〈時間〉の重要性も、以前にも増して強く認識している」
変化しながら刻む進境。還暦の齢を超えてなお、パーヴォ・ヤルヴィの目指す頂はさらに高い。
パーヴォ・ヤルヴィ(Paavo Järvi)
1962年、エストニアのタリン生まれで、父は有名な指揮者ネーメ・ヤルヴィ。生地の音楽学校で打楽器と指揮を学んだ後、1980年にはアメリカに渡ってカーティス音楽院に入学し、またロスアンジェルス・フィルの指揮者コースではレナード・バーンスタインに学ぶ。現在世界で最も活躍している指揮者の一人。チューリヒ・トーンハレ管弦楽団音楽監督、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメン芸術監督、エストニア・ペルヌ音楽祭創設者・芸術監督。