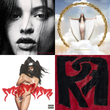ミーガン・ザ・スタリオンのニューアルバム『MEGAN』に収録されている“Mamushi (feat. Yuki Chiba)”。間違いなく2024年を象徴するヒットナンバーであり、ミーガン、ひいては客演の千葉雄喜にとっても自身のキャリアを更新する重要な1曲となったはずだ。
そんな“Mamushi”の世界的ヒットが続くなか、ドラマ界では真田広之が主演/プロデューサーを務めた「SHOGUN 将軍」が第76回エミー賞にて史上最多18部門を受賞するというビッグニュースも届いた。音楽、映像を問わず、さまざまなコンテンツを介して日本の言語や文化に大きな注目が集まっている現状を、日本人の私たちはどう受け止めるべきなのだろうか。
ここでは“Mamushi”を一つの起点に、海外アーティストらが日本語/日本文化を取り入れている背景や理由について、音楽ライターのノイ村に考察してもらった。 *Mikiki編集部
“Mamushi”など日本語/日本文化を取り入れた世界的ヒットが急増
ミーガン・ザ・スタリオンと千葉雄喜が歌う〈お金 稼ぐ 俺らはスター/お金 稼ぐ 私はスター〉という日本語のリリックを、日本から遠く離れたイギリスはロンドンのオーディエンスが大合唱している。楽曲のヒットぶりを踏まえると当然といえば当然の景色だが、やはり日本語をネイティブで話す立場としてはなかなかに感慨深いものがある。きっと、世界中のクラブやライブ会場でも同様の光景が広がっているのではないだろうか。
今年のヒップホップシーンを代表する1曲となったミーガン・ザ・スタリオン“Mamushi (feat. Yuki Chiba)”は、それほどのインパクトを与えたのである。公開されたミュージックビデオも、千葉雄喜に加えて俳優の笠松将が出演していたり、神奈川県で撮影が行われていたり、妖怪〈濡女〉や黒澤明監督の映画「夢」を彷彿とさせる演出が取り入れられていたりと、全編にわたって日本文化を参照した仕上がりとなっていて、こちらも大きな話題となっている。
思えば、最近の海外の音楽シーンを眺めていると、思わぬ方向から日本語と出会う機会が増えたようにも感じる。カミラ・カベロ“Chanel No.5”やLISA“ROCKSTAR”のようにリリックに日本語を取り入れる場合もあれば、ビリー・アイリッシュ“CHIHIRO”のように曲名やコンセプトに日本語/日本文化を反映する場合もある。
ラナ・デル・レイ“Kintsugi”にいたってはその両方の要素があり、また楽曲自体には反映させていなくとも、日本でMVを撮影したフェイド“SORRY 4 THAT MUCH”やロザリア“TUYA”、あるいはアルバム『Pink Tape』のトレイラーで大胆にアニメーションを使ったリル・ウージー・ヴァート(トレイラーのアニメ制作は日本に拠点を構えるD’ART Shtajio)など、映像表現において日本語や日本文化を取り入れていることも今では珍しくはない。
一口に〈日本っぽいものが増えている〉といっても、そのアプローチは多岐にわたる。さまざまな角度から日本文化へのリスペクトを感じることができる“Mamushi”のMVは、こうした近年の動きを象徴した作品と言ってもいいだろう。
〈日本文化を表現に取り入れることがクール〉というムード
実際のところ、日本語/日本文化に注目が集まっている現状に対して、何か大きなターニングポイントがあったのかというと、そういうわけではないように思う。むしろ、数年後に振り返ったとき、先に挙げたアーティストたちや“Mamushi”こそがターニングポイントだったと回想することになるのではないだろうか。日本語を用いた楽曲自体は、それこそ1976年のクイーン“Teo Torriatte (Let Us Cling Together)”(邦題“手をとりあって”)をはじめ現在にいたるまで膨大な数が存在する。なので、昨今の日本語/日本文化のムーブメントについては、一つ一つの事例が偶然重なったからかもしれない。
その前提の上で、〈もしこのムーブメントに何か明確に理由があるとしたら?〉と考えを巡らせると、一つ〈日本文化を表現に取り入れることがクールである〉というムードが醸成されたことが大きいのではないだろうか。さらに、日本文化を代表するアニメに対しての世間の認識、あるいはアーティスト側の表現の変化なども重要だ。
元々、ヒップホップと日本のアニメはかなり強い繋がりを持っている。先に挙げたリル・ウージー・ヴァートのほか、カニエ・ウェストやスヌープ・ドッグなどアニメ好きを公言しているラッパーは枚挙に暇がなく、その影響はリリックやサンプリング、アートワークなど、実際の作品にも色濃く反映されている。
米「NYLON」の取材に応えた、ロチェスター大学で日本語過程の准教授を務めるウィリアム・H. ブリッジス4世は、1990年代にアメリカの配給会社や放送局がアニメを放送するブームが訪れ、その後スタジオジブリの世界的な成功もあり、アメリカの文化に日本のアニメが入っていく動きを加速させたと述べている。
さらにウィリアム氏は、この時代に多感な時期を過ごした人々(主にラッパー)がアニメとともに育ち、その美学(Aesthetics)をある種の共通認識として抱くようになったとも語っている(ビリー・アイリッシュ“CHIHIRO”は「千と千尋の神隠し」にインスパイアされて生まれた楽曲であり、この発言を裏付ける例の一つと言ってもいいかもしれない)。
また、「ドラゴンボール」「美少女戦士セーラームーン」「NARUTO」といった作品を例に、物語の主人公たちが、社会的不平等や圧政などさまざまな問題に直面しながらも力や勇気を発揮し、仲間たちとともにそれらを乗り越えようとする物語が、あるいは現実とは異なる世界を描いたことによる、ある種の無国籍性が、特にヒップホップを好む人々から強い共感を呼んだのではないかとも、ウィリアム氏は指摘している。
とはいえ、特にアメリカでは〈アニメ好き≒ナード、Weeb〉と軽蔑されるケースは依然として多く、一方では白人男性を中心とした有害なファンダムによるゲートキーピングも珍しくない。ミーガン自身も今年3月に「Teen VOGUE」のインタビューで、「私がアニメが好きだと公言し始めたとき、男たちは誰も信じなかった。きっと女の子がアニメを好きになることなんてないって思われているんでしょうね。本当にバカらしい。私はずっと〈なんで私が素晴らしいコンテンツが好きだってことを信じてくれないの? 何が気に入らないの? なんでアニメは自分だけのものだと思ってるの?〉って感じてきた」と語っている。
こうしたコメントから、アメリカでは〈アニメ好き〉ということが、ある種の倒錯した特権のように扱われている時期が長く続いていたことがわかる。だからこそ、ミーガンが“Otaku Hot Girl”や“Mamushi”のような楽曲で、日本やアニメに対する愛情と、自身が強くてセクシーな女性であることを同時に語ることには大きな意味があるのだ。