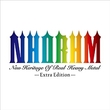『Echo』は素晴らしいアルバムだ。前作『Dot』と同じセッション(2023年7月12〜14日)で録音された楽曲をまとめた作品なのだが、映画音楽やクラシック音楽、吹奏楽といった音楽からの影響が総合的に反映され、メタルの考え方や質感を意識したという『Dot』とはまた異なる世界が描かれている。
全7曲が組曲のように連なるアルバム構成は流麗で、具象的な序盤からいつの間にか無意識の海に沈むような中盤に至り、終盤にかけて再び具象へ浮かび上がっていくような展開は、聴きやすさと底知れなさを絶妙に両立している。自由でありながら構築的でもある演奏も全曲見事で、曖昧なことを曖昧なまま明快に表現する語り口が素晴らしい(これは、独特の薫り高いフォーク/ブルース感覚についても言えることだろう)。全体として、ロバート・グラスパーやティグラン・ハマシアンなどとは異なるやり方でジャズを内部から更新する傑作になっているように思われる。
以上のような音楽性について、今回も西山瞳に興味深い話をたくさん聞くことができた。前回のインタビューとあわせてお楽しみいただければ幸いだ。

信頼するメンバーとの音色やテクスチャーによるアンサンブル
――前作のインタビューでは、「自分の好きなわりと暗めのやつばっかり集めてるので、もう1枚のほう(『Echo』)は明るめの曲が中心になると思います」と仰っていました。それなら自分は『Dot』のほうが好きな感じかと思っていましたが、実際に聴いてみたら『Echo』のほうに惹かれました。一つ一つの曲も良いですし、なにより全体の流れとまとまりが良いですね。
「ありがとうございます。いっぺんに20曲録ることは今までなかったのですが、うまくまとめられたと思います。選考漏れした曲が4曲あって、そちらは来年にでも配信リリースする予定です」
――『Dot』と『Echo』、先に全体像を意識できたのはどちらでしたか。
「『Dot』ですね。そちらを中心に1枚めを出すことを考えていたので。Excelで表を作って、並べ替えて聴いて、いろんな曲順を試しました。それで、『Dot』ができた時点で『Echo』の曲順もだいたい決まっていました。
『Dot』では、単色・モノクロみたいなところから開けていって、だんだん物語が繋がっていくイメージだったので、1曲めを“Turtledove”にすることは決めていました。それに対して『Echo』では、オープニングの手触りは全然違うものにしたいと思っていましたね」
――資料によると、『Echo』は〈組曲に聞こえるように配置した〉とのことですが、構成の面で参照されたものはありますか。
「基本的には、以前出した『Astrolabe』(2012年)の、ギターとデュオでやった組曲を膨らませたいというのが土台です」
――今回のアルバムは1年前のセッションで録音された音源で、セッション直後と今とでは感じ方が変わってくると思うんです。印象の変化や新しく見えたことはありますか。
「新作をリリースする際にフィジカルな感覚が抜け落ちてしまっているのは今までなくて、今回は他人事って感じがします(笑)。私は録音の時、いつも一冊ノートを作っていて、ミックスや曲順、OKテイクなどについてメモを書いているんですね。今回は、そのノートを見ないと思い出せない(笑)」
――なるほど(笑)。両作に共通する要素として、〈西山瞳トリオ+3〉の〈+3〉(クラリネットの鈴木孝紀、テナーサクソフォン/フルートの橋爪亮督、バイオリンのmaiko)の部分、管弦の位置付けや活かし方が特徴的だというのがあると思います。前回、録音した後はあまり音を加工しないと仰っていましたが、例えばミキシングで音量バランスを決めることなど、録音後に印象が変わる部分もあると思うんですよね。
「そこはエンジニアの松下(真也)さんに丸投げしました。優れたエンジニアなので、思うようにやってほしかったんです。パンチのある音を録る人なので、ジャズの管楽器を録るのは彼が一番だと思っているので。元の音から基本的にあまり変えてないです。
あと、『Dot』と『Echo』では違うところが一つあります。この1年の間に、松下さんが本物のプレートリバーブを買ったんですよ。『Echo』はそれが入った関係で響きが変わっています」
――『Echo』の音像は、管楽器がリードとしてガンガン出てくるジャズとは違う室内楽的な響きで、絶妙な存在感を示しています。
「そこは3人の力によるところが大きいですね。音色やテクスチャーでアンサンブルできる人でなければ無理な作品だし、3人はピッチ感もすごく良い。やればやるほど音が近づいていくのを感じました。
弦楽器の擦過音と管楽器の音って、音量感も含め本来は混ざらないものですし、バイオリンとサックスが一緒に仕事するのも、大きな編成でないとまずないんですよ。クラリネットも音が小さいから、混じりにくい。それをお互いわかりながら、音色をブレンドするように近づけていく。そういう力がある人たちです」
――現場で築き上げたまとまりを活かしたということでしょうか。
「そうですね。プレイヤーがちゃんとしてないと録れないので、〈好きにやってください〉とお願いできるほど信頼できる人とやるようにしてます。コンセプトは伝えるけど、こう演奏してくださいと指示はしないほうがワークすると思っていますね」