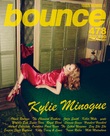時空の彼方へ飛び去ったサウンドが、またしても静寂と残響の間にこだましている……ダスト惑星を離れて早くも20年、何度となく世界を激震させてきた王者が、いままた深い深いエコーの奥から姿を現した……

夏フェスといえばケミカル・ブラザーズ、という印象のある人も多いのではないだろうか。確かにビッグなスタジアムや野外の会場において幅広いオーディエンスを煽動するダンス・ミュージックとなると、プロディジーやかつてのファットボーイ・スリムと並んでケミカル・ブラザーズがEDMムーヴメント以前の顔役だった。というか、いわゆるEDMについて別物と捉えたがる昔気質なロック・ファンも易々と踊らせる点では、いまも天下は彼らのものかもしれない。
そんな憶測を裏付けるかのように、この夏のケミカル・ブラザーズはバルセロナの〈ソナー〉や〈グラストンベリー〉、ワイト島の〈ベスティヴァル〉を巡り、その間の8月には〈サマーソニック〉への出演もスケジューリングされている。過去6回の〈フジロック〉出演を誇る彼らも、意外なことに〈サマソニ〉は初体験。エド・シモンズは同行せずトム・ローランズのみの登場となるようだが、ヴィジュアル演出を担当するアダム・スミスを伴ってのステージングには大いに期待がかかるところだ。
もちろん、そのように派手な露出が活発化しているのは、このコンビが約5年ぶりのニュー・アルバム『Born In The Echoes』を堂々完成させたからでもある。無闇なアニヴァーサリー視は禁物ながら、彼らが最初のアルバムを発表してちょうど20年。ここではその決して短くない歩みを辿ってみることにしよう。
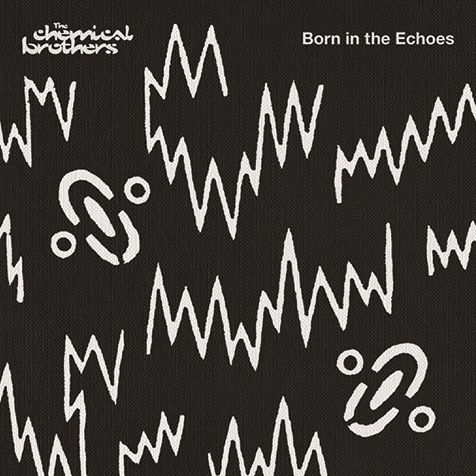
THE CHEMICAL BROTHERS Born In The Echoes Freestyle Dust/Virgin EMI/ユニバーサル(2015)
サウンド自体のポピュラー性
その20年前よりもさらに数年遡って……トム・ローランズ(70年生まれ)とエド・シモンズ(71年生まれ)がコンビを結成したのは90年代初頭。マンチェスターの大学で出会ったのはそれよりもさらに少し前になるが、互いの音楽的な趣味も手伝って親交を深めていった二人は、91年にダスト・ブラザーズなるユニットを結成している。マンチェスターでは〈ハシエンダ〉などでプレイして徐々にクラブ・ピープルの間で名を上げていくと、デッド・カン・ダンスをサンプリングした初めてのシングル“Song To The Siren”(92年)をジュニア・ボーイズ・オウンからリリース。94年夏からはロック・アーティストも数多く訪れるパーティー〈The Heavenly Sunday Social〉のレジデントDJを務めるようになり、これをきっかけにシャーラタンズたちとリンクしたことが、迫ってきたブリット・ポップの動きと彼らを自然に結び付けるイメージ作りに機能したのだった。やがて、USの本家ダスト・ブラザーズからのクレームを受けてケミカル・ブラザーズに改名した彼らはメジャー契約を取り付け、95年に『Exit Planet Dust』でアルバム・デビューを果たしている。同作のコマーシャルな成功は、ポップスやロックとダンス・ミュージックの融合――昔も今も使い古しの言い回し――とかいうこと以前に、ダンス・トラックであろうと普通にポップスとして受容されるという、時代のリスナーの変化を証明するものとなった。
だからこそ、ともすればゲスト・ヴォーカリストの存在にのみ彼らの成功の要因を見い出しがちな見立ては的外れだとも言える。日本でもお茶の間レヴェルにまで名を届けたセカンド・アルバム『Dig Your Own Hole』(97年)は、確かにノエル・ギャラガー(オアシス)がヴォーカルを取る“Setting Sun”によって一段上の成功へと至ったものだし、ビートルズ“Tommorow Never Knows”が引き合いに出された同曲のサイケデリックな音像が、多様な世代のリスナーを惹き付けたのは想像に難くない。が、同曲に続く2曲目の全英No.1ヒットとなったのが、後のニュー・スクール・ブレイクスにも通じるゴツゴツした感触のブレイクビーツ・チューン“Block Rockin' Beats”であったことも忘れてはいけないだろう。
さらにサード・アルバム『Surrender』(99年)でもっとも人気と思われるビッグ・チューン“Hey Boy Hey Girl”もゲスト不在のオールド・スクーリーなエレクトロだったことを思えば、彼らのダンス・ミュージックとしての快楽の源泉もポピュラリティーの秘訣も、いずれも同じくサウンドの部分から生じているのだということも明白だ。実際、後に彼ら自身も認めているように、既存のポップ・ヒットの鋳型に合わせるのではなく、自分たちのフォーミュラを世間に受け入れさせる形で、ケミカル・ブラザーズは大きくなってきたのである。
根本的なダンス・ミュージック
ゆえに、折々の時代の要請にどう応えるかはさまざまで、ミレニアム到来の前後からは〈ロッキン・ブレイクス〉というイメージから飛び立つように、トライバルでトランシーなプログレッシヴ・ハウスに踏み込み、あるいは原点でもあるアシッド~レイヴの雰囲気などに回帰し、根本的なダンス・トラックとしての快感を巨大なスケールと共に追求しはじめる。その極みを『Come With Us』(2002年)に見ることは容易だろう。
一方で、『Push The Button』(2005年)のようにゲストとのコラボをテーマにした作品の場合、彼らはとことんカラフルにやりきってみせる。“Galvanize”以来となるQ・ティップとの再会があるから……というわけではないが、今回のニュー・アルバム『Born In The Echoes』も馴染みのアリ・ラヴや、初顔合わせのセイント・ヴィンセント、ケイト・ル・ボン、ベック(かの『Morning Phase』の後に録った最初の曲らしい)といった演者の顔ぶれ自体をキーにした作品という意味で、これは『Come With Us』で一区切り付けた後の『Push The Button』に近いというか、珍しくノー・ゲストでストイックにフロア志向を見せた『Further』(2010年)が無事に成功したからこそのキャッチーな揺り戻しなのかもしれない。
2014年にはアイヴァー・ノヴェロ賞の〈Outstanding Song Collection〉を授かっているように、すでに何かを無理に証明する必要もなく、モチヴェーションが高まるまで創作を急ぐ必要のないポジションを手に入れている二人。だからこそ今夏のライヴ・パフォーマンスにエドは帯同していないのだろうし、このマイペースな動きこそが、またしても充実したニュー・アルバムの完成へと結び付いたことを素直に喜びたい。世界中がダンスフロアだとすれば、その覇権はやはりいまもケミカル・ブラザーズのものなのだ。