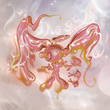転機となったビッグバンドとマリア・シュナイダーとの出会い
ジャズ作曲家となるためにNY留学で学んだもの
――大学の時は基本的にクラシックを勉強していたんですよね?
「そうです。個人レッスンはクラシックの作曲の先生に習っていて、それは真面目にやりました」
――もともとジャズをやり始めたのも、大学でビッグバンドの演奏を観たのがきっかけだったそうで。
「新入生の歓迎演奏会にたまたま通りかかって、〈なんじゃこりゃ!?〉みたいな(笑)。それまでは本当にクラシック一筋でジャズは聴くだけの人間だったけど、それでニュータイド(Newtide Jazz Orchestra:国立音楽大学の学生ビッグバンド)に入ったんです。学校はすごくつまらなくて辞めたかったんですけど、この出会いのおかげで踏みとどまりました」
――へぇー。
「そのころは〈山野ビックバンド・ジャズ・コンテスト〉に出るのがステータスでしたね。ニュータイドはカウント・ベイシーとかの曲もやってましたけど、もっと近現代というか、いま生きている作曲家の曲をやることも多くなってました。ゴードン・グッドウィンズ・ビッグ・ファット・バンドとかボブ・フローレンスのバンドとか、マリア・シュナイダーもそうだし、あとはミシェル・カミロとかハービー・ハンコックの曲のビッグバンド・ヴァージョンもやってましたね。それで、大会に出ているバンドでカッコいいのがいると思ったら、慶応義塾大学のライト・ミュージック・ソサイェティーだったんですよ。彼らはジム・マクニーリーやマイク・ホロバーの曲を演奏していて、それがこのあとの話にも繋がってくるわけです」
※山野ビックバンド・ジャズ・コンテスト
山野楽器が主催する、日本の学生ビッグバンド・ジャズオーケストラを対象とした音楽コンクール
“Skittish”はジム・マクニーリーが作曲したビッグバンドの人気曲
ライト・ミュージック・ソサイェティーは多数のプロを輩出した名門学生ビッグバンドで、
2014年作『Hope』にはマリア・シュナイダーやダーシー・ジェイムズ・アーギューらの
楽曲を含むリサイタル録音を収録している(試聴はこちら)
――そうか、そういうところにいたんですね。
「私はここでマリア・シュナイダーを知ったんです。それでライトがすごく好きで、エキストラで乗せてもらいにいったら、そのときのコンサート・マスターが帰国子女で、のちに私が留学したMSM(マンハッタン音楽院)のプリ・カレッジ(大学に入る前の高校生が、土曜日に通うコース)出身だった。その子に〈こういう音楽が好きなら、きっとヴィンス・メンドーサも好きだよ〉と薦められて、御茶ノ水のジャズに強いレコード店まで探しに行ったのに1枚も置いてなくて。仕方がないからマリア・シュナイダーを買って帰って来た記憶があります」
――マリア・シュナイダーは当時だったら『Evanescence』とかですか。
「私は未だに『Evanescence』が一番好きですけど、当時の最新作は『Concert In The Garden』(2005)かな。『Evanescence』も流行ってましたよね(『Evanescence』は94年作で、2005年に再発)。何はともあれ“Hang Gliding”(2000年作『Allégresse』収録)と“Wyrgly”と“Last Season”(共に『Evanescence』収録)ですよ。私の中で鉄板はその3曲です」
2012年の“Last Season”パフォーマンス動画(※『Evanescence』の試聴はこちら)
「JAZZ LIFE」では、挟間とマリアによる対談企画がこれまで2度実現するなど
(2013年7月号、2015年10月号)、 現在は両者の接点も増えている
――マリア・シュナイダーやヴィンス・メンドーサを好きになったのは、クラシックをやっていたことも関係あるんですかね。
「いや、なぜかよくわからないけど、とにかく好きになりました(笑)。いま考えれば絶対そうだと思うんですけどね。泣く子も黙るブラス・サウンドをバーン!と鳴らすビッグバンドの典型的な感じではなくて、クラシック的なアプローチを元に繊細で入り組んだ、一発で弾くと大して音も鳴らないような〈どうなってるんだ、これは!?〉って譜面なんですよね。当時はそういう音楽にあまり触れたことがなかったから、どれも新しく感じたし。それに、〈もしかしたら自分でも作れるかも知れない〉と思ったんですよ。日本でそういうことをやってる人が、そのころはいなかった気がして。自分が漠然と思い描いていた音楽とも一番近かった」
――大学時代は現代音楽も学んでいたらしいじゃないですか。
「私が師事していた夏田昌和さんという教授は、空間を利用した音響効果を計算して、そこからセオリーを組み立てるスペクトル音楽という作曲技法に長けてたんです。なので、理論や計画を用意してから曲を書くことを前提としてレッスンが進んでいたような気がしますね。譜面を持っていっても、〈これのコンセプトはなんだったの?〉とか〈なんでこの音は必要なの?〉とか訊かれる事が多くて、答えられないと〈書き直しなさい〉と言われるんです。でも先生の作品には、セオリーがあるのにそれを感じさせない、美しい瞬間があったりするわけですよ。そういうのっておもしろいなぁと思って。私も図形を使ったり、折り紙を折って糊でくっつけてみたりして、すごい感覚的なんだけどセオリーをなんとか作ろうと頑張ってみましたね。そのときの経験もあって、『Time River』に収録された“Fugue”は作曲前に8x8の譜表に数字を当てはめた表を作って、その表に沿ってモチーフを組み立てて行きました。いまでもセオリーで考えたりもします」
――そして、NYに留学するわけですよね。
「別にNYじゃなくてもよかったんですよ。ヴィンス・メンドーサかマリア・シュナイダーか、それかジム・マクニーリーかギル・ゴールドスタインが教えているところに行ければよかった。彼らに会ったら何か人生が変わるかもしれないと思って。大学では無調の音楽を作ったり、映画音楽みたいなコースにも入ったりしていたけど、どれもピンと来なかったというか。〈これをするために、いままで作曲を勉強してきたんだっけ?〉みたいに考えて、大学4年生くらいで夢を見失いかけてしまったんです。そういうときに山下洋輔さんや佐渡裕さんと知り合えたのはすごく大きかった。おかげで作曲家としてアーティストになるという決意を、大いに後押ししてもらえました。アメリカにはそういうアーティストが既にいるわけだし、その人達の作品はどれも好きで親近感も抱いていた。だからとりあえず、その人達が教えているであろう学校を全部受けてみたんです。それで受かったのがMSMでした」
※マンハッタン音楽院(The Manhattan School of Music)
NYはマンハッタンで1917年に創立されたクラシック/ジャズの名門音楽院。第一線の音楽家が授業を行うことで有名で、多くの才能を輩出している。ビリー・ジョエルやハービー・ハンコック、ジェイソン・モラン、クリス・ポッター、ミゲル・ゼノンも同校の出身。
――ジム・マクニーリーが教えているんでしたっけ。
「そうですね。あとマリア・シュナイダーがマスタークラス(公開レッスン授業)を受け持っているのがMSMとバークリーだと聞いていたので、ちょうどいいと思って」
――じゃあ、マリアの授業も受けました?
「入ってすぐにマスタークラスもありました。でもそのときはまだ面識も全然ないので、コンポーザーの生徒として挨拶するくらい。〈あなたの大ファンです〉と伝えておしまいでしたけど(笑)」
――ジム・マクニーリーのレッスンはどうでした?
「その頃はインスピレーション任せで曲を作ることが多くて、最初のレッスンで持っていったら〈この音はなんでここにあるの?〉と訊かれて。それでジムがスケッチブックを手にして〈曲を作る前に、こうやってスケッチをしてから書くんだよ〉とか、〈物語やコンセプト、曲のフォームとか、書き始める前に何かしら根拠があったほうが作品の中身が充実する〉とか言うんです。〈これじゃ日本で最初に受けた授業と一緒じゃんか!〉と思って(笑)。4年間やってきたことを水の泡にしたような気がして、〈何をやってるんだ〉と反省しましたね。でも、最初にそう言われて逆にやりやすかったです。いままで学んできたことと同じアプローチで出来るわけだから。そこからは常におもしろいアイディアを考えるようになって、サウンド的に面白そうだと思ったら試してみたり、ギル・エヴァンスのオーケストレーションが全然理解できなかったので真似してみたりとか、何かしら目標を作って取り組んでいきました」
【参考動画】ヴァンガード・ジャズ・オーケストラの2008年作『Monday Night Live At The Village Vanguard』収録曲“Loas Cucarachas Entran”のライヴ動画
ジム・マクニーリーは数々のジャズ・バンド/オーケストラに携わってきた作/編曲家兼ピアニストで、
この曲も作曲するなどヴァンガード・ジャズ・オーケストラ
(NYのジャズ・クラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードを拠点とするビッグバンド)への参加は特に有名
――その後の教え方はどんな感じでしたか?
「ジムは〈自分の背中を見て育ってくれ〉みたいな感じかな。BMIコンポーザーズ・ワークショップ(http://www.bmi.com/genres/entry/bmi_jazz_composers_workshop)という、私もMSM卒業後に所属していた、プロを目指す作曲家のためのワークショップがNYにあるんですけど。そこでも昨シーズンまでジム・マクニーリーとマイク・ホロバーがミュージック・ディレクターとして一緒に教えていたんですよ。マイクは〈このオーケストレーションはどうかと思う、僕はこっちの方が良いと思う〉とか結構細かくアドバイスしてくれるんですけど、ジムは持って行くと〈いいね! じゃあ続き書いてきて〉で終わっちゃうから、自分のわからないことは予め質問を用意するようにしてました。そうすると、自分の作品をiPhoneで聴かせてくれながら〈僕はこういうふうにしたから、君もそうしてみたほうがいいかも〉とか具体的に答えてくれて」
――曲を日々作っている人の過程を見て学ぶみたいな。
「そうそう、ザ・現役なので。HRビッグバンドでもすごい量の新作を書いているから、それを授業でも聴かせてもらったりとか。あとは譜面を見せたりして、〈こういうふうに出来るよう頑張りなさい〉的な教え方でしたね」
――〈フレッド・ハーシュの教え方がとにかく厳しい〉みたいな話はよく聞くので、そう考えると珍しいですね。
「心構えというか人間性も含めて、プロになるとはどういうことかを見て盗めたので、いい環境だったと思います。それに、ジャズ作曲家の実情も知ることができましたし。ジムですらNYでは作曲家としての仕事をしていなくて、自分の名義でライヴもやっていない。アメリカでは教える仕事がほとんどで、音楽家としての活動はヨーロッパが拠点なんですよ。そういうふうに、尊敬している人達の後ろ姿をリアルタイムで追うことが出来たのは大きかったです」
――NYの状況って厳しいんですね。
「『Time River』に参加してくれたエンジニアのブライアン(・モンゴメリー)も、〈こんなご時世に、この2~3年でこれだけ多くのビッグバンド・アルバムが出ているの不思議でしょうがない。みんなどこからそんな金が湧いてくるんだ?〉みたいに言ってましたね。作曲家は自分のブランドを作曲で示すしかないけど、そういう仕事がNYにあるわけじゃないから、自分を発信するためには結局バンドを持つしか方法がないわけですよ。じゃあ自分でやるか!って考える人がいま増えてるんだと思う」
――でも、ビッグバンドのシーンって最近とにかく面白いですよね。新しい作曲家が面白い作品を次々と出している。
「そうなんです! そういったなかで私はジャズ・チェンバーで個性を出していきたいと思っていて、〈オーケストラとの架け橋といえば挟間美帆〉みたいに言われるようになっていきたい。ブランドがはっきりしているのが重要だし、そういう人が増えているのが面白いんですよね。プログレッシヴな作風だったら絶対ネイサン・パーカー・スミスだし、ダーシー・ジェームス・アーギューは幾何学的な音楽性で、ギジェルモ・クラインのようにアルゼンチンからもユニークな才能が生まれている」
ラージ・アンサンブルとプログレッシヴ・ロックを掛け合わせた、パワフルな音楽性を展開
2013年作『Brooklyn Babylon』
エイフェックス・ツインやステレオラブからの影響を汲むミニマルなサウンドを
18ピースのオーケストラで表現してみせる鬼才、リリース元のニュー・アムステルダムは、
「JTNC3」でも特集が組まれた〈インディー・クラシック〉を語るうえでも重要なレーベル
★新作『Time River』について掘り下げた後編はこちら
〈挾間美帆 m_unit ニュー・アルバム
『タイム・リヴァー』 発売記念ライヴ〉
日時/会場:2015年10月15日(木) BLUE NOTE TOKYO
開場/開演:
1stショウ17:30開場/19:00開演
2ndショウ20:45開場/21:30開演
ミュージック・チャージ: 6,800円
http://www.bluenote.co.jp/jp/artists/miho-hazama/