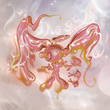新時代のジャズ・ガイド〈Jazz The New Chapter(以下JTNC)〉で旋風を巻き起こした気鋭の音楽評論家・柳樂光隆が、人種/国籍/ジャンルなどの垣根を越境し、新たな現在進行形の音楽をクリエイトしようとしているミュージシャンに迫るインタヴュー連載「〈越境〉するプレイヤーたち」。登場するのは、柳樂氏が日本人を中心に独自にセレクト/取材する〈いまもっとも気になる音楽家〉たち。第3回は、NYで活躍する新進気鋭のジャズ作曲家、挾間美帆が登場。この後編では、ジャズ・コンポジションの現状について話をさらに伺いながら、注目すべき新作『Time River』の内容や制作エピソードを深く掘り下げている。(Mikiki編集部)
★前編はこちら
★〈挾間美帆 m_unit ニュー・アルバム 『タイム・リヴァー』 発売記念ライヴ〉
10月15日(木)開催、詳細はこちら
★連載【〈越境〉するプレイヤー達】の記事一覧はこちら
★〈Jazz The New Chapter 3〉紹介記事はこちら
挾間美帆が〈ジャズ作曲家〉を名乗る理由
ジャズ・コンポジションの現在と将来
――最初のアルバム『Journey to Journey』(2013)を作るとき、メンバー集めはどのように進めたんですか?
「管楽器やリズム隊は大学の時に一緒にやってもらった事がある人とか、そこから紹介してもらった人たちですね。ジュリアードとMSM(マンハッタン音楽院)の出身者が多い。弦楽器だけはわからなかったから、ジム・マクニーリーに相談したらマーク・フェルドマンを紹介してくれたんですよ。それで、マークがセカンド・ヴァイオリンとヴィオラの人を紹介してくれて。チェロは以前からずっと一緒にやりたいと思っていた同級生の女の子がいたんです」
レディー・ガガのカヴァー、m_unitによるライヴ動画はこちら
――メンバーとして参加している人の多くは、いわゆるジャズ・ミュージシャンですよね。彼らとは、どんな感じで知り合ったんですか?
「リズム隊のベースとのサム・アニングは(MSMの)同級生で、ドラマーのジェイク・ゴールドバスは一つ下の学年かな。サムは私の学年で唯一フル・スカラーシップ(学費を全額支給)だったオーストラリア人で。どれだけ巧いんだろうと思ったら本当に巧くてビックリして。これはタダゴトではないと思いました(笑)」
――『Journey to Journey』を作ろうと思ったのはどういう経緯で?
「〈ジャズ・ピアニストとしてデビューしませんか?〉みたいなお話も、遠い昔にあったんですけどね(笑)。ジャズ・コンポーザーというより、何はともあれ作曲家になりたかった。ピアニストという肩書きからは半ば逃げるような形だったかもしれないですけど、2年間ジャズ作曲修行で雲隠れすることによって、みんな作曲家として見てくれるだろうと考えたんです。日本では誰も私のことをよく知らない状態になっていると思ったし、発表したい音楽も溜まっていたので、どこかでアーティストとしてデビューできる可能性がないか探っていたときに、ちょうど(日本の)ユニバーサル・ミュージックが拾ってくださって」
――なるほど。
「最初は〈自主でも作る〉と言い張ってましたね。とりあえずCDを作りたかった。どこかレーベルからリリースできたほうがもちろんいいけど、もう逃げ道がないし、とりあえずアーティストとしてデビューするしかなかった。結局サニーサイドにも全部作り終わったあとに売り込みに行ったんです」
※『Journey to Journey』と『Time River』は、日本ではユニバーサル・ミュージック・ジャパン内のジャズ・レーベルであるヴァ―ヴ、USではジョン・ホーレンベックやアーロン・ゴールドバーグも今年新作を発表したサニーサイドよりリリースされている。
サム・アニングやジェイク・ゴールドバス、サム・ハリス、ミーガン・バーク(チェロ)、
庵原良司(サックス)など『Journey to Journey』や『Time River』に参加した奏者が集っている
――挟間さんは〈ジャズ作曲家〉という肩書きにもこだわりがありますよね。でも音楽性でいえば、ストリングスがいっぱい入っていたり、ジャズっぽくない要素も多いじゃないですか。それでも敢えて〈ジャズ作曲家〉と名乗り続けているのはどうしてですか?
「たしかにジャンル分け出来ないんですよね。でもだからといって、CD屋さんに〈挟間美帆ってジャンルのコーナーを作ってください〉なんてお願いするのも無理だし」
――僕も〈ジャズ評論家〉を名乗っていると、〈音楽ライターとか音楽評論家じゃなくて、ジャズ評論家なんですね〉ってよく言われます。
「私もです。〈(頭に)ジャズ要らないよね?〉って〉」
――でしょ?
「でも正直なところ、〈ジャズ作曲家〉って名乗ると、いまはすごい楽なんですよ。ただの〈作曲家〉だとどういう曲を作るかわかりづらいじゃないですか。ジャズ作曲家だと、〈なんでジャズなのに作曲家なの?〉って結構ツッコまれるんです(笑)。世の中の人にとって、ジャズといえば即興でマイルス・デイヴィスとかチャーリー・パーカーみたいなものだと思っているから、〈作曲する必要ないじゃん〉みたいなイメージですよね。でも、〈マイルスやパーカーが使っていた和音やリズムも使って作曲するんです〉と伝えると、私がやっていることが想定しやすくなる。おかげで、クラシックの人が“Sing, Sing, Sing”(ジャズ・スタンダード)をカッコよくしたいとか、チャーリー・パーカーの文化も織り交ぜた作品を作りたいとか、私が作りたいものに最初から寄ったオーダーが届くので、〈クラシックの調性があって、同時にジャズっぽい〉というのがいい名刺代わりになってます。それに、〈ジャズ作曲家〉って響きも珍しいし」
――たしかに。
「でも、自分のブランドでCDに収録している音楽が、ジャズの要素をもつリズム隊を使っているというのと、楽曲でもインプロヴィゼーションのセクションが大きな役割を占めているわけで。それはさすがにクラシックやロックの人には無理で、ジャズの人じゃないと出来ない。だから自分の音楽をジャンル分けするとなったらジャズしかないと思う。もちろん、バックグラウンドでは本当にいろんな物がミックスされていて。それはマリア・シュナイダーにも同じことが言えるわけで、彼女の音楽をカウント・ベイシーと同じ括りにするのはちょっと酷かなと思いますし。マリアがマリア・シュナイダーというブランドの〈作曲家〉といわれるように、私もゆくゆくは〈作曲家〉と名乗るだけで自分のブランドを築けたら嬉しいですね」
――僕も挟間さんについて、ジャズ・ミュージシャンにしかできないんだけどカテゴリー分けしづらい不思議な音楽をやっているイメージが以前からあったんです。〈JTNC〉にも〈ジャズ・ミュージシャンにしか演奏できないものは全部ジャズと呼ぼう〉というのがコンセプトにあって。だから、挟間さんがいま話していることは……。
「ピッタリですね(笑)。即興って要するに自由で何でもアリだから、譜面で書かれているなかに即興が用意されたものでも、逆に100パーセント完全な即興であってもジャズになりうるわけですよ。そういう意味では、すごく多様化できるジャンルだと思います」
――ジャズという言葉の意味が100年の歴史を経て、すごく広がってきてますよね。
「マリア・シュナイダーの音楽が新しいジャズ・コンポジションの形なのであれば、かなり惜しいところまできていると思うんですよ。クラシックの人も演奏するくらいまでにもうすぐなるんじゃないかな。マリアは実際に(クラシック音楽の殿堂である)カーネギー・ホールで数年前に彼女の作品を初演しているし、2013年の『Winter Morning Walks』はチェンバー・オーケストラのアルバムで完全に書き譜(アドリブではなく譜面に従って演奏すること)だった曲も1曲入っていたし、内容もクラシックに寄ったものでしたよね。もともと私はクラシック音楽のオーケストラが好きで、ベルリン・フィルとかN響を聴いて育ってきているので、(レナード・)バーンスタインと(ジョージ・)ガーシュウィンで終わりじゃなくて、マリア・シュナイダーやジム・マクニーリーみたいな人の作品も演奏されるようになってほしいし、されるべきだと思う。ジョン・アダムスやフィリップ・グラス、スティーヴ・ライヒはあんなに演奏されるのに、ジム・マクニーリーが演奏されないのが不思議でしょうがなくて。絶対にウケると思うんだけどな。だから、そういう可能性が私にとってはモチベーションになっているんです。いつ日本のオーケストラに〈私の曲もやりませんか?〉って売り込もうかと(笑)」
――マリアがジャズとクラシックの両方でグラミー賞を獲ったり、そういう動きも形になってきている気がします。
「私にとってはすごく励みになりますね。やっぱりマリアはロールモデルというか憧れの存在なので。いろんなことの架け橋になっているところに憧れるんですよ。この前はデヴィッド・ボウイと曲を作って、完全にロックだったじゃないですか。でも完全にマリアの音がしていて〈なんだこれ!?〉って爆笑しましたけど(笑)。どこでやってもあのサウンドになってるし、通用しているし、愛されている。あんなふうになりたいし、可能性があるのであれば挑戦するべきだと思いますね」
収録曲“Sue (Or In A Season Of Crime)”のMV
ドラムスはマーク・ジュリアナ、サックス・ソロを吹くのはダニー・マッキャスリン
ソプラノ歌手ドーン・アップショウと共演した本作で、
第56回グラミー賞のクラシック音楽部門で作曲賞、ヴォーカル賞、録音賞を受賞した(試聴はこちら)
――そういう〈作曲〉が必要とされる状況になっているムードもありますよね。
「この前クリス・ポッターがジム・マクニーリーと一緒にストラヴィンスキーの“春の祭典”をデディケートする組曲をHRビッグバンドでやってましたね。すごく難しそうだったけど、そういうことをすることが出来る可能性があるというわけだから、たしかにそうなのかもしれない。私としては〈増えろ! 増えろ!〉って思いますけど(笑)」
――ダーシー・ジェームズ・アーギューの周辺で、ヴィジェイ・アイヤーや(バッド・プラスの)イーサン・アイヴァーソンの曲をチェンバー・アンサンブルで取り上げた音源とかも最近出てますし。
「ジャズ・ミュージシャンが作曲家としても認められ始めているのかもしれないですね。今までは32小節あったら、それを延々10分アドリブする事に意義があった作品が多かったかもしれないけど、ヴィジェイもダーシーも32小節では到底終わらない曲ばっかりですし」
――ジャズという音楽が変化するとともに、ジャズ・ミュージシャンの書く曲の質も変わったのかもしれないですね。
「複雑さが増しちゃったのかもしれない。ジャズがフリー・ジャズまでいって一通り全部やり尽くした後に、発展させようと思ったらいろんな(ジャンルの)音楽の破片を取っていくことをせざるをえないですしね。ウィントン(・マルサリス)みたいに新古典主義に戻る者もいれば、ロバート・グラスパーとかエスペランサ(・スポルディング)みたいにR&Bとかヒップホップに寄っていく動きもある。私はクラシック音楽との共存を探りたいし、ダーシーとかマリアもそういう方にいるんじゃないかな」
NYの先鋭的な弦楽四重奏団が、ヴィジェイ・アイヤーやイーサン・アイヴァーソン、ビル・フリゼール、