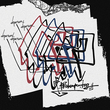京都を拠点に活動する男女4人組、Homecomingsがセカンド・アルバム『SALE OF BROKE DREAMS』をリリース。音と言葉の両面で、バンドが2014年の前作『Somehow, Somewhere』を経てネクスト・ステージに達したことを告げる作品だ。
まず、破格にヴァリエーションを増した楽曲に目を見張る。USエモへの愛情が表れたギター・ロックや、90年代のマンチェスター・サウンドを彷彿とさせるナンバー、そして初の試みとして鍵盤を採り入れ、まるで小沢健二“ローラースケート・パーク”の如き柔らかな多幸感が広がるミッドテンポ・チューン――彩り豊かな収録曲のなかでも、昨年リリースのシングル“HURTS”を発展させた、リズムのループを基調にグルーヴを紡いでいく数曲が印象深い。新作には、メンバーのプレイヤーとしての成長と、バンド自体のレヴェルアップが刻み込まれている。
そして、歌詞にも注目だ。前作は、1人の主人公が夜に抱くメランコリアを私小説的に描いた作品だったが、『SALE OF BROKEN DREAMS』では、表題が意味する〈いくつもの壊れた夢の叩き売り〉を通奏低音に、1つの街でさまざまな登場人物に起きたストーリーを綴っている。言葉自体の美しさも胸を衝くものがあり、まるで珠玉の短編集のように味わい深い。
サウンドの多彩さとストーリーテリングの豊かさという両面での成長がシンクロし、バンドとして理想的な発展を遂げたアルバムについて、ギターの福富優樹に訊いた。
“HURTS”の制作は、バンドとしてすごく大事な瞬間にいるという感覚があった
――新作『SALE OF BROKEN DREAMS』は、前作『Somehow, Somewhere』を引き継ぎつつも、異なるコンセプトで作られたアルバムだと感じました。いま振り返って、前作はバンドのどんな側面を表した作品だったと思いますか?
「いわゆるギター・ポップという括りから離れようとした作品でしたね。それまではアノラックやジャングリーなサウンドのイメージが強かったと思うんですけど、それは自分たちの本質じゃなかった。だから前作は〈脱ギター・ポップ〉というか、自分たちが本当に好きなことをやったアルバムじゃないかな」
――そうした自分たちの狙いが世の中から理解された手応えもあったのでしょうか?
「それは前作のあとにリリースしたシングル“HURTS”くらいからのような気がします。“でも『Somehow, Somewhere』を出したときはレヴューなんかでもギター・ポップと書かれることが多かったですね。あと、なぜか〈マーチング・バンド〉と書かれたり(笑)。まあファースト・アルバムだし、そういう要素がないわけじゃないし、しゃあないかとも思ったんですけど」
――“HURTS”はバンドとして、どんなトライアルを課した曲でしたか?
「とりあえずシングル曲というものを作ろうと思ったんです。バンドとしてシングルのためにシングルっぽい曲を作るというのは、それまでやってきたことがなくて、すごく気合いが入っていた。それまでの集大成かつ次のアルバムに繋がるようなやつにしたいなと。すでに“HURTS”の制作時には、新作のタイトルになった〈SALE OF BROKEN DREAMS〉というコンセプトはあったから、歌詞もそのテーマに沿って書こうと思いました。で、曲は〈これぞシングル〉なビッグなもので。フォーマット※の“The First Single”とか、あの年代のシングルっぽい曲を作りたかったんです」
※2008年に解散したUSのギター・ロック・バンド。ヴォーカリストのネイト・ルイスは現在ファンで活動中
――フォーマット! そうだったんですね。言われてみればすごく納得できる。
「ただ、自分個人としては、この時期すごく悩んでいたというか。嫌なことがいっぱい起きていた時期でもあり」
――そういう歌詞にはなってますよね。サビでも〈毎日毎日とは言わないけれど 嫌な事が次から次へとやってきて〉と歌われていて。
「当初はもっと暗くて、遺書みたいな歌詞やったんですよ。もうバンドも辞めるかもしれんから、これは書いておこうくらいの気持ちで(笑)。サビ自体はいまと同じなんですけど、その前後はもっと重たい歌詞やったんです。流石にこれはヤバイなとなり、じゃあフィクションにしてみようと思った。なので、作詞家として初めて、人から聞いた話や他者のストーリーを書いてみたんです。次のアルバムのことも考えつつ、自分自身の〈死にたい〉みたいな気持ちも入っているし、フィクションを書こうという新しい挑戦もある。いろんなアイデアが詰まった曲ですね」
――〈SALE OF BROKEN DREAMS〉という言葉がテーマになったたのは、このフレーズからどんなイメージを喚起されたからですか?
「すごく映像的やなと思ったんです。短い一文やけど、視覚的に想像が膨らむというか。しかも“HURTS”の頃の自分にもすごく寄り添う感じもあって。ズーンと落ち込んでいる自分の気持ちをなにかに昇華できるタイトルだと思った」
――BROKEN DREAMを歌った“HURTS”の手応えが、新作での〈SALE OF BROKEN DREAMS〉というコンセプトを推し進めたのでしょうか?
「“HURTS”は曲も歌詞もミュージック・ビデオもすべてを含めてうまくいったんです。まあセールスに関してはもっと売れる……軽く8万枚くらいいくと思ったんですけど(笑)。でも評価はすごく良くて、この曲でバンドの認知度が拡がった印象もあり、じゃあこういう方向で行けば良いんやなとは思えた。 “HURTS”は、レコーディング中から4人全員が〈これは凄い曲やな〉という雰囲気を共有できていたんですよ。それまではそういうことはなくて、『Somehow, Somewhere』のときなんて最後まで完成して、やっと安心できたという感じやったし。でも、この曲はもうレコーディング中に〈ヤバイ、これは良い曲や〉みたいなムードで、バンドとしてすごく大事な瞬間にいるという感覚があった」
――“HURTS”のリリースから今回のアルバムまでは約1年空きましたよね。“HURTS”の手応えを感じつつ、アルバムの制作にはゆっくり取り組んだのでしょうか?
「アルバムのリリースを春にしたいというのは、僕とヴォーカルの(畳野)彩加さんのなかではなんとなくありました。前作が冬にこだわって制作したアルバムだったし、次は春の作品というのがしっくりきて、じゃあリリースもその時期かなと。実際去年の秋頃まではライヴが忙しくて、曲はほとんど作れていなかったんです。ただ、もうタイトルは決まっていたし、自分のなかでイメージをどんどん固めていった感じでしたね。ギターは持たず、楽曲のアイデアと歌詞のストーリーをずっと考えていた」

ストーリーテラーでありたい気持ちが強い
――前作『Somehow, Somewhere』は、私小説的な作品だったと思うんですが、今回のアルバムでは短編集的な趣向になっています。〈SALE OF BROKEN DREAMS〉というテーマを敷いたうえで、アンソロジー的な作品にしようというコンセプト自体には、なにか着想元があったのでしょうか?
「柴田元幸さんの編んだ短編集『Don’t Worry Boys 現代アメリカ少年小説集』という本を読んだ影響は大きいですね。それから、そのアンソロジーに作品が収録されていたスチュアート・ダイベックの短編集〈シカゴ育ち〉を読んだら、そっちもすごく良くて、〈あ、こういう感じに出来たら良いな〉と思った。『Somehow, Somewhere』は映画のイメージだったんですけど、今回は短編小説集というフォーマットに惹かれたんです。あるテーマの下にバラバラのストーリーが集まっているのが、すごくアルバムっぽいなと思った」
――短編集として〈Don’t Worry Boys〉や〈シカゴ育ち〉のどんな点に惹かれたのでしょうか?
「語り手の視点ですね。過去を思い出しているような視点が作品のなかで一貫しているのがすごく良いと思ったし、自分はそういう感じで作ったことがなかった。前作は、自分の当時の寂しさをそのまま出した感じなんですけど、“HURTS”からは一歩引いて見たほうがおもしろいんじゃないかなというのもあり、そこで過去を振り返る目線にすれば対象ともちょっと離れるわけじゃないですか。それを、ある街が舞台のフィクションでやるのはどうだろうかと」
――以前から福富さんはミュージシャンであるのと同等にストーリーテラーでありたいという意識が強い印象なんですよ。
「うん。その通りです」
――1つの街を舞台に、そこで暮らすさまざまな人のストーリーを語った表現として、なにか音楽作品で思いつくものはありますか?
「うーん、シャムキャッツの『TAKE CARE』と……なにかありますかね?」
――スフィアン・スティーヴンスの『Michigan』『Illinois』が思い浮かびましたけど、それらは実際の地域の歴史や風土といった要素も盛り込んで作った作品なので、今作と完全には一致しないですよね。
「あー、でもスフィアンのそれらは大好きなアルバムですね。そもそも僕はコンセプトがある作品が好きですし、作り手としてもコンセプトありきのタイプだと思います。いま言ってくれたように、音楽だけじゃなくトータルとしてストーリーテラーでありたい気持ちが強い。バンドの作品を映画みたいにもしたいし、小説みたいにもしたいんです。良い曲が何曲か収録されているアルバムというより、ジャケットとかすべてを含めて意味を込めた作品を作りたい。そもそも、なにか物を作るということが好きなんですよ。小学校4年生のときに星新一の〈ショートショート〉を読んで、自分もワープロでショートショートを書いていたし。めちゃ妄想をしちゃうタイプで、いまだに『ONE PIECE』とかに自分が入り込んでいたらどんな立ち位置でなにをするだろうかと考えたりもする。そういう自分の性質がバンドの作品にも出ているとは思います」
――さっきコンセプト的に近しい作品で『TAKE CARE』を挙げられていましたけど、そのうえで今作と『TAKE CARE』のいちばんの違いはなんだと思いますか?
「うーん、寂しさみたいなほうに僕らはどうしても向いちゃうところですかね。ポツーンとした感じに絶対なってしまうなと」
――確かに『TAKE CARE』は、人と人との関係性にフォーカスした作品のような気がします。その一方で、今作の主人公たちはみんな一様に孤独で。
「あー、そうですね」
――奇しくもと言うか、今作のアートワークは『TAKE CARE』と同じく漫画家のサヌキナオヤさんが描かれていますね。
「シャムキャッツとの作品が素晴らしかったのはもちろんですけど、そもそもサヌキさんとは好きな作品が通じていたり、感覚が近いんです。なので、やり取りは早かったですね。前のアルバムのジャケットが看板一枚だったので、今回は歌詞のテーマ的にもそこから拡げて街全体で、というイメージを伝えました」
――福富さんとサヌキさんが共通して好きなアーティストや作品と言えば?
「お互いにエイドリアン・トミネやダニエル・クロウズ、クリス・ウェアとか、日本だとPresspopが邦訳を刊行しているようなオルタナティヴ・コミックスが好きなのは間違いないでしょうね。実際にそういったアーティストの作品がイメージにもあった。なんとも言えない線の太さや、全体に漂う寂しさ――そこは僕らの音楽性ともリンクしていると思います。その寂しさは、彼らのストーリー漫画はもちろんそうなんですけど、一枚絵でもすごく出ていて、サヌキさんの作品にも近しいムードを感じる。長いセリフで感情を説明するのではなくて、絵とちょっとした言葉でメランコリックな感じを出すところとか」
メンバーそれぞれの持つ音楽性がようやく出てきた
――今作は、1曲ごとに異なる人物のストーリーを描くという歌詞面での挑戦と、前作以上に曲調が多彩というサウンド面での進化がすごくマッチしていると思ったんですが、バンドの成長自体が今作のストーリーテリングを導いた面はありますか?
「これまでは好きな曲を聴いて、こういうのをやりたいとイメージしてもできないことが多かったけど、それをやれるようになってきたことは大きいです。それは4人全体のスキルの向上もあるし、ギター・ポップというイメージを取り払ったというのもあるし、この1年間ライヴでPAをしてくれている荻野(真也)さんがレコーディング・エンジニアもしてくれて、制作スタッフ全体でのチーム感もあるから、いろんなことを試せるというのもあった。曲調的にももっといろんなことをしたかったし、そういうのが合わさった結果やと思います」
――福富さんが描いているアイデアをバンドとして具現化しやすくなったということですか?
「それもあるし、もしかしたら僕がやりたいアイデア自体が4人の共通項に近付いたのかもしれない。例えばデス・キャブ・フォー・キューティやペイヴメント。やろうとしているバンドの方向性が意外にメンバーみんなに備わっているものだった」
――アンサンブルでも音色でも多彩になった作品だと思ったんですけど、今日の話を聞くと、本人たちとして新しい挑戦というよりルーツ回帰に近かったんですかね?
「ルーツに戻ったというよりは、本当に好きなことを際限なくやろうとしたんです。キーボードや鉄琴を入れたり、サウンド面でやりたいことにブレーキをかけずにやった。“DON’T WORRY BOYS”や“BUTTERSAND”やったら、なるちゃん(石田成美、ドラムス)が最近はヒップホップが好きでデ・ラ・ソウルとかを聴いているからそういうビートの感じを採り入れたり。ほなちゃん(福田穂那美、ベース)が曲を作ってきたのも初めてのことですし」
――へー! 彼女の曲はどれですか?
「“CENTRAL PARK AUDIO TOUR”はほなちゃんが持ってきた曲なんですよ。バンド内でベン・クウェラーやトバイアス・ジェッソJrの話で盛り上がったあとに、彼らの曲をイメージして彼女が作ったんです。今作は、ようやくメンバーそれぞれの音楽的な嗜好が出てきたアルバムでもある」
――それは大きな変化ですよね。だって前のアルバムのときは、リズム隊の2人はどんな作品になるのか全体像が見えないままレコーディングしていたそうじゃないですか。
「今回は録音中からそれぞれ思い入れのある感じでしたね」
――となると、レコーディング自体は前のアルバムと比べると比較的スムースだったんですか?
「前はメンバーごとにバラバラで録っていたんですけど、今回は常に4人全員がスタジオに揃っている状態でレコーディングしたんですよ。だから、なんとなくの全体像は全員が見えている状態ではあったと思います」
ギタリストである自分に視線が向かった
――福富さんのギター・プレイもすごく幅が拡がった印象です。こんな音色でこんなフレーズを弾くのかと驚いた箇所が多くて。
「ギターに関しては、これまで本当に適当だったんですけど、アルバムを作るちょい前からアンプを買ったり、機材への興味がめちゃくちゃ出てきたんです。ハードオフにめっちゃ行くようになったし、いまや機材厨ですよ(笑)。『Somehow, Somewhere』までは、表現者として歌詞を書いたりバンドをどうするかを考えたりするのに手いっぱいで、ギタリストの視点はほとんどなかった。彩加さんと一緒に曲を作るというフォーマットを固めるのにも必死やったんですよ。でも、それはもうできたから、次はギタリストである自分に視線が向かったんでしょうね。自分が思い描いているバンドの表現に、歌詞でも曲でもなくギタリストとして参加しているという状態がようやく楽しくなったんです。前作では、自分のギターが力不足だったなと感じた面もあったし、それはもう完全にギタリストとしての僕の責任じゃないですか。そこをめっちゃ考えた気がしますね。自分がこのバンドの曲や歌詞にまったく関わってないとしたら、どうしようみたいな(笑)。でも、ギターにハマったことで、弾くのがめっちゃ好きになりました」
――それは非常に大きな変化ですね! あと福富さんや畳野さんはかねてからスピッツへの愛情を公言していますが、演奏面で成長したことで、これまででもっともスピッツを彷彿とさせる作品になっているとも思ったんです。特にビートのループ感やギターのサイケな音色に『惑星のかけら』までの初期スピッツを感じました。
「それはいちばん嬉しいですね。しかも、僕は『惑星のかけら』がいちばん好きなアルバムですし」
――特に“BUTTERSAND”は、“日なたの窓に憧れて”を思い出しました。
「あら! でもそこは意識してなくて、この曲はいわゆるいまのアメリカン・ポップス的な、コード進行がずっと同じでという構成をやりたかったんです。言われてみて、そういえば!と思ったくらい。確かにギターは(三輪)テツヤ感がある気がします(笑)。“PERFECT SOUNDS FOREVER”のギターもそうですし」
――“PERFECT SOUNDS FOREVER”の主旋律のヴォーカルとは違うメロディーを奏でているプレイにもテツヤ感がありますよね。あとは“BLINDFOLD RIDE”の急にノイジーになるところとかも。
「うんうん。それはやっぱりルーツですから、出ちゃったんでしょうね」
世界と関わっているが故に生まれる孤独を描こうとした
――それにしても、バンドとして理想的な成長を遂げたアルバムですね。
「そうなんですよ。正直、自分では良すぎるんじゃないかと思うところもあって(笑)」
――ハハハ(笑)。そのうえで歌詞について、もう少し深く訊いていきたいんですけど、私小説的な語りから、キャラクターを設けたストーリーテリングへと枠組みを変えたことは、書き方自体にも変化を及ぼしたのでしょうか?
「ちょっと変な作り方をしていて、歌詞だけ最初に全部書いちゃったんですよ。だから、曲よりもなによりも先に歌詞だけがあった。今回はここがヴァース、ここがコーラスとかは気にせずに書いてみようと思ったんです。どこがサビになるかは、もう彩加さんに任しちゃおうと、曲になることを意識せずに歌詞を書いた。だから、歌詞というより〈詩〉を書いたという気持ちが強くて」
――複数の登場人物のフィクショナルな物語を綴っていくという行為自体はエキサイティングでした?
「めっちゃおもしろかったです。本当に制限なく書けたし、一曲一曲ちゃんと物語を描けたから愛着も強いですね。曲ごとに1人子供を生んだようなイメージで、すごく愛おしさを感じる」
――じゃあ、そうした子供たちを並べる順番にもこだわった?
「冒頭は朝で、最後は夕日が射して終わるという流れは当初から考えていたし、最後が“LIGHTS”からBASEBALL SUNSET”というのは決まっていました。また、1つの街を想像して作るうえで、なにが中心にあるかなと考えると、なんとなくのサブ・テーマだった野球――いくつかの曲でもメジャー・リーグやリトル・リーグが出てくるんですけど、それに沿って最後もまとめたら良いんじゃないかなと思って、最終曲の舞台を野球場にしたんです。“BASEBALL SUNSET”では、日曜日のデー・ゲームが終わり帰っていく人たちと、少年野球の子供を迎えにいくお母さんが描かれていて、そこには地下鉄が舞台の“LIGHTS”もリンクしてる。黄昏のなか、みんなが帰路に着く野球場の下を地下鉄が通っていて、というイメージがあった」
――今回は、野球場や地下鉄の駅、大きな公園など、パブリック・スペースを描いていることが多いように思いました。そうした空間に関心が向かったのはどうしてでしょう?
「前の『Somehow, Somewhere』には、そうしたロケーションは1つも出てきませんでしたよね。前作の、夜に1人で散歩しているというシチュエーション――それは京都で言うと岩倉みたいなひっそりとしった街が舞台だとしたら、今回はもう少し南に降りてきて、御所があったり、京都駅があったり、そういった場所のイメージなんです。前作にあった夜に1人でいる寂しさに対して、今作は、人がいっぱいて、物もいっぱいあるなかでの寂しさを描きたかった。世界と関わっているがう故に生まれる孤独みたいなものを描こうとしたんだと思います」
――“BASEBALL SUNSET”や“CENTRAL PARK AUDIO TOUR”の歌詞を見ていくと、主人公は人が大勢いる場所で、その光景のなかのさまざまな営みを見つめていて、幸福感もあるんだけど、それと同時に寂しさも感じているんだろうなと想像できる。そういう他の感情とも混ざった複雑な寂しさみたいなものが、今回は多く描かれているように思ったんですよ。
「寂しさにしても、前やったら青とか黒とか一色やったのが、今回はいろんな色があると思う。カラフルにしたかったというのもあるんですけど。そうしたいろいろな色を言い表せるのが〈SALE OF BROKEN DREAMS〉というタイトルでした」
〈死の匂い〉みたいなものをどう扱うかは意識していた
――あと『SALE OF BROKEN DREAMS』では、実際に人がいる描写以外に、そこに誰かがいたという匂いや記憶を描いている局面も多いと思うんですよ。
「そうですね」
――歌詞にいくつか出てくる〈亡霊〉という言葉がそれを象徴しているようにも思ったんですよね。
「わ! それは、よくわかりましたね。そのことは本当に誰にも言ってないんですけど、僕と彩加さんの間ではなんとなく共有していました。裏テーマじゃないですけど、それは前のアルバムでやりかけて、やれなかったことだったんです。前作では〈GHOST WORLD〉という言葉を自分なりに解釈しようとしていたけど、今作では、描かれている世界の裏に違う世界があり、幽霊的なものがいるというのをはっきり意識していました。そこをちょっとずつ隠している作品なんですよ。いや、よく気付きましたね。びっくりしました」
――気付けて良かったです(笑)。
「“ANOTHER NEW YEAR”では、誰のものかわからないマフラーが公園の遊具に巻きつけてあり、“LIGHTS”では地下鉄の車窓に過去に起きた出来事が一瞬だけ映し出される。そして、“BASEBALL SUNSET”の最後では夜のグラウンドに幽霊みたいなものがいる。それがいったいなんなのかは説明できないんですけど、今回はそれを作品に残したいなと思い、こっそりやっていたんです」
――各曲の主人公に関しても、この人はもしかして幽霊なんじゃないかと思う瞬間があって。
「えー!!! それわかります? そう決めて書いたわけじゃないんですけどね。でも、映画の『シックス・センス』じゃないですけど、〈実はもう自分は死んでいるのかもな〉とかみたいな寂しさがあるじゃないですか」
――前作が“GHOST WORLD”で終わり、そのあとのストーリーとしてこういった見立ての作品になるのはすごく理解しやすい。ダニエル・クロウズの「ゴースト・ワールド」の最後でも、イーニドは〈向こう〉に行ったという解釈もできるじゃないですか。
「それは“HURTS”のときからすごく考えていたことですね。死の匂いみたいなものをどう扱うかは意識していました」
――脚本家/映画監督の三宅隆太さんという方がいるんですけど、その人が心霊の定義は生きているか死んでいるかではなく、心の時間が止まった人のことをそう呼ぶんだと言っていたんです。このアルバムを聴いて、その発言を思い出したんですよ。
「へー、なんか嬉しいというかゾッとしたな(笑)。わかっちゃうもんなんやと思った。僕自身はインタヴューでそのことを言うつもりもなくて、それを自分で楽しんでる感じやったんですよ。幽霊たち=〈SALE OF BROKEN DREAMS〉という裏テーマみたいな感じで」
――ただ、止まった時間を慈しむだけでなくて、それらが進みそうな瞬間も描いているように感じたんですよね。“LIGHTS”の〈THE MOMENT〉と歌われる箇所とか。だから、SALE OF BROKEN DREAMSという言葉が救いにもなっているような気がする。
「そうですね。でも、いま言われて驚いたな。アートワークでも、ジャケットの床屋にだけ人がいる感じとか、この世のものじゃない的なニュアンスはあるんですよ。でもサヌキさんにもちゃんと言ってなくて、誰かが気付いたらおもしろいなというくらいだったんです」
――なるほど。じゃあ最後の質問なんですけど、Homecomingsのプロフィールの〈女の子3人+男の子1人〉という表記は、いつ時が進むんですか?
「ギャハハ(笑)! それはやっぱ永遠にイノセントな感じで。〈ライ麦畑〉の主人公みたいな」
――なるほど。でも、ホールデン・コールフィールドも心霊なのかもなと思えますからね。
「確かにね。そういう感じもするじゃないですか。〈この人は、もう死んでてNYを彷徨っているのかな〉みたいな。そういうニュアンスは、みんなわかるものなんですかね? 僕だけ頭がおかしいのかなと思っていたんですよ(笑)。小学校のときに観た『シックス・センス』の衝撃が消えないからか、他の作品に接するうえでも、実はそうやったりして、と考えちゃうところがある。『ゴースト・ワールド』を最初に読んだときも、僕は『シックス・センス』的な話やと思った。このアルバムは、それを自分なりにやってみた作品なんです」
『SALE OF BROKEN DREAMS』 RELEASE ONE-MAN TOUR “DON'T WORRY BOYS”
6月25日(土)名古屋TOKUZO
6月26日(日)大阪・梅田Shangri-La
7月1日(金)東京・渋谷WWW
Homecomings〈CENTRAL PARK AUDIO TOUR〉
7月16日(土)静岡・静岡Freakyshow
共演:KONCOS/Seuss/herpiano
7月17日(日)宮城・仙台LIVE HOUSE enn 3rd
共演:角舘健悟(Yogee New Waves)/CAR10
7月18日(月・祝)福島・郡山PEAK ACTION
共演:角舘健悟(Yogee New Waves)/CAR10
9月18日(日)島根・松江NU
共演:後日発表
DJ:TFC
9月19日(月・祝)広島・福山Hot Blues Cafe
共演:Kensuke Yamamoto(full band)/Jigga
9月23日(金)福岡・福岡UTERO
共演:シャムキャッツ
9月24日(土)愛媛・松山Bar Caezar
共演:シャムキャッツ/オノマトペ
DJ:ROCK TRIBE Dj's(Nori/Kondo/Hajime)
9月25日(日)岡山・岡山YEBISU YA PRO
共演:シャムキャッツ
10月10日(月・祝)石川・金沢vanvan V4
共演:後日発表
■フェス出演情報
7月23日(土)FUJI ROCK FESTIVAL 2016
8月27日(土)RUSH BALL 2016
9月3日(土)BAYCAMP 2016