
デビュー40周年を迎えた2016年に期間限定で復活し、ライヴ・ツアー〈Moonriders Outro Clubbing Tour〉を敢行してファンたちを大いに喜ばせたムーンライダーズ。そんな彼らのアニヴァーサリー・イヤーを盛り上げるのに一役買ったのが同年にリリースされたトリビュート・アルバム『BRIGHT YOUNG MOONLIT KNIGHTS』だ。
ムーンライダーズの音楽にリスペクトを捧げる次世代ミュージシャンを中心に、縁のあるアーティストからアイドルまで、ブライトな面々が集結したこのアルバム。その発売記念ライヴが5月5日(金・祝)に東京・新代田FEVERにて行われる。当日はアルバムに参加したアーティストから11組が出演。多彩にしてユニークな顔ぶれが揃う貴重な機会となるだろう。今回はその出演メンバーの中から4組に集まってもらい、ムーンライダーズの魅力を語る座談会を敢行した。メンバーは、METAFIVEやpupaのほか、鈴木慶一と高橋幸宏のユニット=BEATNIKSのサポートも務めるゴンドウトモヒコ、5人組シティー・ポップ楽団、1983の新間功人、牧歌的なカントリー・ポップを鳴らすポニーのヒサミツ、そして杏奈&優奈の姉妹と幼なじみの涼夏からなるアイドル・ユニット、ANNA☆Sという面々だ。
今回の対談場所に選ばれたのは、都内某所にあるゴンドウのプライヴェート・スタジオ。うららかな日曜の午後、それぞれのムーンライダーズ愛をざっくばらんに語り合ってもらった。
★曽我部恵一とスカート・澤部渡がムーンライダーズを語った記事はこちら
とにかく〈ヘン〉なバンド
――今日お集まりになられている皆さん、うまく年代がバラけてますよね。ゴンドウさんが60年代生まれ、新間さんとポニーさんが80年代生まれ、そしてANNA☆Sの3人が90年代生まれという。ライダーズとの付き合いが長いということでまずはゴンドウさんからバンドへの想いをお訊きできますか。
ゴンドウトモヒコ「昨日もとあるレコーディングをしていた流れで(鈴木)慶一さんと呑んでいたんですけどね。僕が最初にライダーズを聴いたのは中学生の頃でした。3つ上の兄貴がいて、YMOとかコアな日本の音楽をいろいろと聴いていたんです。で、僕は兄貴に対抗するようにビートルズとか洋楽を聴くようになっていたんだけど、彼がいないときにこっそり隠れてLPを聴いて、すげえカッコいいなぁと思って」

――どういうところにほかのバンドとは違うカッコよさを感じたんですか?
ゴンドウ「僕はテレビで流れているような歌謡曲も好きだったんですが、その延長線上にはないちょっと変わった音楽、という認識ですね。その頃はまだロックが主流の時代ではなかったですから。僕は『ANIMAL INDEX』(85年)がリアルタイムなんですよ。あの頃のライダーズはシンセやコンピューターとかを使いだして、曲もミクスチャーな感じだった。かしぶち(哲郎)さん作詞・作曲の“Frou Frou”がポップでカッコ良くて、とにかく好きでしたね」
――同業者の視点から、こういう曲は作れないよなぁってところがあれば教えていただきたいんですが。
ゴンドウ「いや、そういう曲ばっかですよね(笑)。でも彼らが本気でキャッチーな曲を書いたときの強さって凄いものがありますから。あと80年代はCM音楽もよく作っていて、なかでも化粧品のCMに使われていた“GYM”(84年のシングル)がすごく耳に残って。ああいう職人技を見せつけられるとスゲえなって思いますよね」
――なるほど。新間さんのライダーズとの出会いは?
新間功人(1983)「僕らの世代だとMOTHER※とかゲーム音楽が入口になっている人が多いと思うんですが、自分もそのクチです。ミュージシャンとして彼らを初めて認識するのは、大学のサークルではちみつぱいの“土手の向こうに”(77年作『センチメンタル通り』収録)をコピーすることになったときですね。歌詞も演奏も大学生の自分にすごくしっくりきて、ほかに何をやってるんだろう?と興味がわいて、手に取ったのが『AMATEUR ACADEMY』(84年)でした。確かSTUDIO VOICEのアートワーク特集で取り上げられてて、その中でもジャケが異様にカッコ良かったんで。それで中身を聴いたら、はちみつぱいとはあまりに違い過ぎて、何だコレ?って。ただ、聴き込んでいくうちに、歌詞の良さとエレクトロ・ファンクなサウンドにどんどんのめり込んでいきました」
※鈴木慶一と田中宏和が音楽を手掛け、糸井重里がゲーム・デザインを担当したRPGゲーム
――やがて中毒性のある音楽だとわかったと。
新間「完全に中毒でしたね。あと大学生の頃ってテンションの浮き沈みが激しいじゃないですか。そういった沈んでいるときにかなりフィットするんですよ、ライダーズの音楽って(笑)」
――続いてポニーさんはいかがですか?
ポニーのヒサミツ「新間さんとは世代がかなり近いので、入り方は結構似ていると思います。はっぴいえんどなどと同じ系譜にあるバンドとしてまずはちみつぱいを聴き、次に『火の玉ボーイ』(76年、鈴木慶一とムーンライダース名義)へと進んで。そのあたりを聴いた分には、わりとアメリカ的なサウンドをやられている方々だなあって印象でしたが、その流れでムーンライダーズのファースト(77年作『MOON RIDERS』)を聴いたらイメージがガラリと変わってしまい、そこで〈あ、ヘンなバンドだったんだ〉って気付くわけです。そのあとも次々にアルバムを聴き進んでいったのですが、だいたいどのアルバムも〈ヘン〉だったので、そのイメージはますます強くなって。メンバー6人それぞれが曲を書かれるわけですが、どの曲が誰の主導で作られているのかを意識して聴くようになったことで、どんどんその魅力にハマっていきましたね」
――はちみつぱいとムーンライダーズを比較して、どっちが上でどっちが下とか考えることがたまにあったりしませんか?
ポニー「ハハハ(笑)。別物だという印象が強いというか、それぞれおもしろさのタイプがまったく違う気がしているので。自分自身の音楽性に影響を与えているのは間違いなくはちみつぱいのほうなんですけど、それとは別次元のところでムーンライダーズを楽しんでいるところがありますね」
――ちなみにゴンドウさんがはちみつぱいを聴いたのっていつ頃ですか?
ゴンドウ「かなり後になりますけど、はちみつぱいそのものを意識することはあまりなかったかな。“塀の上で”(77年作『センチメンタル通り』収録)もムーンライダーズの曲だと思っていたぐらいだから。ライダーズの曲と同時にラジオで流れていたりしたし、両者が一致するのはだいぶ後だった気がする」
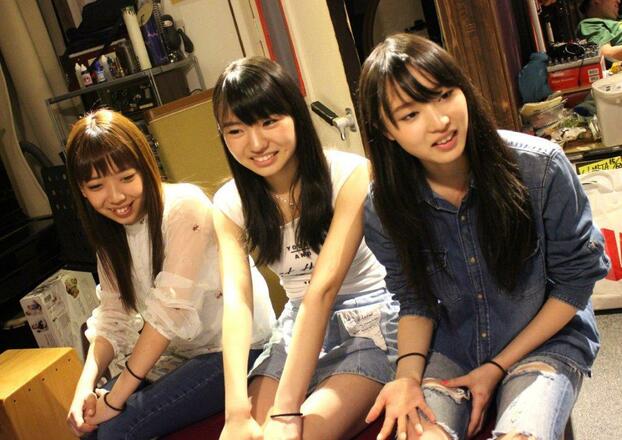
〈気障〉という美学
――さてANNA☆Sの3人は、うどん兄弟以前にムーンライダーズ、あるいは鈴木慶一さんのことを知っていました?
杏奈(ANNA☆S)「はじめ事務所の社長から〈すっごい有名な人なんだよ!〉って聞かされたとき、私たちは〈……誰?〉って感じで」
優奈(ANNA☆S)「でもタワレコに行ったときにポスターが貼ってあったりして、徐々にすごい人なんだなって認識するようになりました」
杏奈「慶一さんにはうどん兄弟の“ママが歌うアイドルの歌”(2014年作『ラストアルバム vol.1』収録)を書いていただいたんですが、そのミュージック・ビデオにも出演していただいたんです」
優奈「最後にメンバーでうどんを食べるシーンがあるんですけど、それを運んでくる店員さん役で」
新間「そんな使い方していいんですか(笑)」
優奈「フフフ(笑)。そんな思い出があります」
――実際に会われた慶一さんはどんな方でした?
優奈「もうめっちゃ優しい人でした」
杏奈「ダンディーというか男前というか」
――おぉ、それは素晴らしい。ではライダーズの音楽を聴かれた印象はどうでしたか?
杏奈「以前、慶一さんのControversial Spark主催のライヴにうどん兄弟で出させていただいたときなどをきっかけに聴かせてもらったんですけど、めっちゃカッコ良くて。特に声がもうすごくカッコ良かったです」
――独特な声ですもんね。でも3人から見たら慶一さんってお父さんというよりは……。
優奈「お父さんより上で、おじいちゃんより下、って言えばいいですかね(笑)」
ポニー「お父さんの年の離れた兄ぐらいだよね(笑)」
――そんなANNA☆Sの3人に、ライダーズの音楽を愛する3人がその魅力を伝えてくださると大変ありがたいのですが。
新間「さっきポニーくんも言っていたように、作者の傾向を読むのが楽しいですよね。でも歌詞だけだとどれが誰だと判別するのが難しかったりする。これって慶一さんっぽいなと思ったら、(鈴木)博文さんやかしぶちさんの歌詞だったりして。そういうバンドの統一されている部分と統一されていない部分を読み取っていくのがおもしろいんですよね」
――ちなみに統一されている部分って何だと思います?
新間「気障(キザ)という美学ですかね。いまの時代、気障ってもはや失われてしまった美徳だと思うんですけど、ムーンライダーズにはどの作品にも通底してあるように思います。で、逆に統一されていないと思えるのは、レゲエ趣味であったり、クラシック寄りなところとか」

ポニー「キャラクターの色は6人それぞれはっきりとしていて、かしぶちさんの曲はロマン溢れる作風だったり、岡田(徹)さんはポップな曲からヘンな曲まで何でも作れたり、そういう個性はいろんな部分でも活きているんだけど、6人が集まるとムーンライダーズになっちゃうところが魅力だと思います。それぞれ歌も歌えるし、マルチに演奏もできてしまう。そういう人を集めて出来たんじゃなく、自然と集まったのがそういう6人だった、ということがすごいですね。例えば『ANIMAL INDEX』なんかそれぞれが曲を持ち寄って演奏して、という完全分業になっているんですけど、むしろよりムーンライダーズらしさが際立ったアルバムなんじゃないか、と思わせるところがあって」
ゴンドウ「それを何10年も続けるって、日本ではほかにいないですもんね」
新間「〈解散し損ねた〉って言ってましたけどね(笑)」
ポニー「いまはまた活動休止状態に入っちゃいましたけど、僕らが好きな70~80年代のバンドでいまなおあそこまで現役で続けているのってムーンライダーズぐらいしか思い浮かばない。彼らが生で活動しているのを見られるってものすごくありがたいことだなって思うんです」

――ムーンライダーズの作品を振り返ってみると、その時々の最先端を懸命に追いかける姿が浮かんで見えてきたりしますよね。その様子が何やら義務感に駆られるかのように感じられるところもあったりして。
新間「〈新しい機材が登場したらまずそれを使わなきゃって思う〉と慶一さんが以前インタヴューで話していたんです。僕らの世代だと新しい機材が出たといっても、既成のものを少し改良した程度のものだったりするんだけど、彼らはサンプラーやシーケンサーが誕生したときに出くわしているわけですから。ライダーズの音楽を聴いていると、そういった新しい機械と夢中になって取り組んでいる、という熱量を感じることが多い。それが影響して、なかには閉鎖的になってしまっている作品もあったりするんだけど、僕はそこが結構好きな部分だったりもする」
――無我夢中にのめり込んでいるような感じ。
新間「そうですそうです」
――BEATNIKSのライヴに参加した2001年からゴンドウさんは慶一さんとお付き合いがあるわけですが、レコーディングはどういうふうに行われているんですか?
ゴンドウ「まっさらな状態でスタジオにやってきて、何かアイデアが浮かんだらギターだったり鍵盤だったりで音を作り上げていくんです。鼻歌で歌っているようなものをどんどんコンピューターに入れていくんですが、どういう形になるのかまったく見当がつかない。まだ何もできていない状態なのに、いきなり〈これは間奏のソロね〉とか言われたりするし(笑)。いろんなピースをパズルのように並べながら形にしていくんだけど、最終的に歌詞が乗ったときにあたかもはじめから世界観が用意されていたかのように仕上がってしまうのが不思議なんですよね。頭の中がいったいどうなっているのか、いつまで経ってもわからない」
ポニー「間奏から作り始めるって斬新ですね(笑)」
――出会って17年、まだまだ謎が多いと。
ゴンドウ「多いですね。とにかく何が出てくるかわからない。あと常に世界中の音楽を聴いているから詳しいですよね。そしてその時々興味のあるものがアイデアとして瞬間的に出てくるんですね、新しいものから古いものから。とにかく次に何をやるのかわからないところが大変で、そこに(高橋)幸宏さんがいるともう……。でもそれにうまく対応できればあっという間に曲ができてしまう。作業が早いんです。似てますよね、(BEATNIKSの)2人は。喋っている冗談とかも」
――やっぱりそうなんですね。
ゴンドウ「人柄がね。慶一さんがいたからやっぱりバンドもまとまるわけで、幸宏さんもYMOではほかの2人の間で融和材的な役割になっていたわけだし。そんな2人が喧嘩するわけがないでしょ?」





































