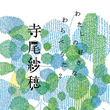シンガーソングライター・寺尾紗穂の新しいアルバムは『たよりないもののために』と名付けられている。英題は〈For the Innocent〉。〈たよりないもの〉の訳語に、無垢・純真・無実などを意味する〈Innocent〉=イノセントという言葉を選んだところに寺尾の表現に対するスタンスがあると思った。
〈楕円〉という言葉を用いてさまざまな〈かたち〉が混じり合い存在する世界への讃歌を捧げた2015年作『楕円の夢』の発表後、日本各地の〈わらべうた〉を歌った2016年作『わたしの好きなわらべうた』を経て、オリジナル・アルバムとしては2年ぶりにリリースされた本作。楕円よりももっと形のはっきりとしない、しかしそこに確かに存在する〈たよりないもの〉への眼差しと握りしめた希望が約47分10曲という形で記録されている。
夢半ばで死んでいった人々、過ぎ去ってしまった思い出、汚れた水、天使、イノセント――寺尾が〈たよりないもののために〉歌う唄は、優しいわけじゃない。ただただ、現実をありのままに見つめようと努める真摯な生の軌跡なのだ。
マヒトゥ・ザ・ピーポーの作品の奥深さに触れて、音楽を作らなきゃと思った
――『たよりないもののために』は〈For the Innocent〉という英題が付けられていますが、〈たよりないもの〉を〈Innocent〉という単語に訳しているのは何故でしょうか?
「本当のところ、〈Innocent〉という言葉でも言い尽くせてない感じがあるんです。最初は〈たよりない〉を直訳しようとしたんですけど〈ひ弱な〉みたいなイメージの単語が出てきてしまって、これは全然違うなと思って。ロンドンに住んでいた友人に聞いたら、この言葉を考えてくれたんです。でも言いたいことを全部はカヴァーできてないなぁって思ってます。平和な日常とかそういう何気ないものも、実は〈たよりないもの〉ですよね。考え出すと、いろんなものがその言葉の中に入るから」
――1曲目に“幼い二人”という楽曲がありますし、表題曲の“たよりないもののために”には〈信じることで/この夜に/ようやく朝が訪れるなら/信じる力は/どこに落ちてる/みんなが飲んで/しゃっくりしてた/かあさまの腹の水に/にぎりしめてた/へその緒の彼方に〉という歌詞があります。なので〈たよりないもの〉=〈Innocent〉というのはてっきり子どもたちのことを指してらっしゃるのかな、と短絡的な結びつけをしていました。
「“幼い二人”の〈幼い〉って実は私自身のことを言ってるんです。子どもじゃなくて。それから(“たよりないもののために”の)〈へその緒の〉はもちろん子供ととってもらっていいのですけど、命ある誰もが、という意味で使っているので、子供を強調しているわけではないんです。別のメディアの方も母性的な角度からアルバムを読み解こうとしてたんだけど、実はあんまり関係がない(笑)。その“たよりないもののために”の歌詞も確かにそうなんだけど、私が母親じゃなかったら出てこなかったかというと、それはちょっと……わからないですね(笑)」
――そもそも、この“たよりないもののために”は、どのようなきっかけで出来た楽曲なのでしょうか? マヒトゥ・ザ・ピーポーがエレクトリック・ギターと歌で参加していますね。
「きっかけはいろいろあるんですけど、1つは植本一子さんという親しくしている写真家の義理の弟さんが自殺したんですね。それ以前にも、周りにいる若い人たちで絵を描く人や音楽をやっている人が自殺したって話はちらほら聞いていて。何かを求めて進んでいたはずなのに、いつのまにか死を選んでいなくなってしまう人たちのことを考えたんです。その人たちが死んで自分が残ったということは、これ以上そういう人たちが出ないような社会にちょっとずつでもしていかなきゃいけない。少ないかもしれないけれど、私たち一人一人にその責任は必ずあるなって思って。そんなことを考えていた時にマヒトゥ・ザ・ピーポーとの2マン・ライヴがあって。彼の作品の奥深さ――痛みの中から這い上がろうとするような美しさに触れて、私も音楽を作らなきゃと思ったんです。それで歌詞をバーっと一気に書き上げました」
――寺尾さんは、ご自身の音楽が苦しんでいる人々のためのセーフティー・ネットのような存在になりうると考えていますか?
「そういうふうな気持ちで聴いてくれている人たちは少なからずいるかもしれない。でも、私の場合は音楽で救えればいいけれども、もうちょっと社会のシステム的なところで変えられる部分があるならば、少しでも行動しなければいけないなと思っています。自分が運動の先頭には立てないかもしれないけれど、誰かが興した動きはいつもチェックしていたいし、広めたいなって」