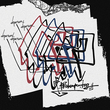才媛、モリー・ランキンが率いるカナダ・トロント発のドリーム・ポップ・バンド、オールウェイズが今秋にリリースしたセカンド・アルバム『Antisocialites』。80年代のスミスやキュアー、NMEのコンピレーション『C86』周辺のアノラック系バンドたちの時代を黄金期に、90年代以降はベル・アンド・セバスチャンを頂点とする、DIY精神とメロディアスなサウンドを備えたインディー・ポップ、いうなればギター・ポップの系譜における、10年代屈指の名盤と評価されるであろう作品だ。
このオールウェイズの魅力について、今回は80年代の黎明期からシーンを追いかけ、自身の音楽活動を通じて90年代後半のスウェディッシュ・ポップ・ブームの火付け役になるなど、日本におけるギター・ポップ・カルチャーの啓蒙に大きな役割を果たしてきたカジヒデキ。そして、その系譜に准える国内若手バンドとしては、今もっとも注目されるHomecomingsのヴォーカル&ギターを務める畳野彩加という両名を迎えて、フランクな音楽座談会を催した。後半には2017年にリリースされたギター・ポップ系アーティストの最新作について語ってもらい、世界的に活況を呈しているジャンルの一端を覗き見ていただける内容になっている。

オールウェイズはインディー・ポップの様式美から抜きん出た
畳野彩加(Homecomings)「この間、ヴァニラ画廊で開催していたダニエル・ジョンストン展※に行きましたよ」
※2017年10月9日~同月の22日までに開催されていた〈ダニエル・ジョンストン展 「HI,HOW ARE YOU?」〉
カジヒデキ「あ、やっていましたよね。 ダニエル・ジョンストンの展覧会なんて、なかなか観られるものじゃない」
畳野「めっちゃ良かったです、本当に。実物を観たらちょっと感動しちゃって」
――PCのモニターごしに観るのとは違いますよね。
畳野「ペンの質感がちょっとずつ違ったりして。細いペンで描いたりとか、太めのペンで描いたりとか。あと当時売っていたテープがきれいに展示されていて、11本セットで25万とかしたんですよ」
カジ「25万!! すごいね。やっぱりそれぐらいするんだ?」
畳野「当時は白かった紙がもう黄色くなっちゃっていて、それとか観て、ウワーって」

――素敵なイントロダクションをありがとうございます。今日カジさんと畳野さんにお伺いしたいお話は、まさに今のようなお話の延長です。最近インディー・ポップ、特にいわゆるギター・ポップと評されそうなサウンドの新譜が、またおもしろくなってきているなと感じているんですけど、とはいえ何かわかりやすいムーヴメントがあるわけでもないので、なかなかまとめて紹介される機会もなく……。というわけで、カジヒデキさんとHomecomingsの畳野さんをお迎えして、最近の海外ギター・ポップ事情を放談していただこうかなと。
畳野「いや、今日はホントお勉強させていただきます(笑)」
――ハハハ(笑)。では、まずきっかけの1枚として、このラインとしては今年屈指の傑作と名高い、オールウェイズの新作アルバム『Antisocialites』から取り上げます。2人ともこのアルバムは聴かれていますよね。
畳野「はい、聴きました。アナログも買いました!」
カジ「自分もそうです」

――オールウェイズのプロフィールを振り返っておきますと、カナダはトロント出身の5人組バンドで、2013年に自主制作でリリースしたアルバムが評判に。その後、UKはトランスグレッシヴ、USはポリヴァイナルと契約して、ワールドワイド・リリースされたのが前作『Alvvays』です。本作はそこから約3年ぶりのセカンド・アルバムですが、まずは簡単な感想からお伺いできればなと。カジさんはどうでした?
カジ「1曲目”In Undertow”のビデオが先行でYouTubeに上がったときから、アルバムがすごくステップアップしていそうだなっていう予感がありました。前作も好きだったけれど、ちょっと違う次元に行ったなって。実際、アルバム全体を聴いてみると、『C86』とかあの頃のテイストの曲が多くなったという感じで、その弾け方みたいなものでひとつ抜けちゃったっていう感想です」
――畳野さんはどうですか?
畳野「私も前作をすごく聴いていたし、好きなバンドです。女の子が歌っているギター・ポップのバンドって最近たくさん出てきていると思うんですけど、やっぱりオールウェイズは楽曲の良さが飛び抜けて違うなというのに、今作で気付かされました。カジさんも言っていたとおり、冒頭の“In Undertow”から、これまでの要素も含めつつ何か進化したなっていうのは感じられて。4、5曲目ぐらいには前作に入っていたようなテンションの、ちょっとインディー・ポップ色の強い曲が入ってきたり、後半はちょっと静かになっていったりする流れとか、アルバムを通してまとまりがあるなというのも感じました」
――お2人がいちばん好きな曲をあげるとすれば?
畳野「私は2曲目の“Dreams Tonite”がいちばん好きです。テンションが好きというか、ちょっとバンドすぎない感じというか、最近はゆっくりな曲が好きなので」
――ちょっとアンニュイな感じ。
畳野「そうですね。かつ、ちゃんとサビっていうか歌えるメロディーがあって、こういうのがすごくいいなと思いました」
カジ「この曲の〈タラーラララーララーララ〉っていうメロディーが、たとえばエジソン・ライトハウスの“Love Grows”とか、70年代のイギリスっぽさがありますよね。ブー・ラドリーズの“Find The Answer Within”にも似ているし、昔のポップスを楽しく掘っているからこそ生まれてくる曲」
――バックボーンを想像させてくれて、まさにポップ・マニアの心をくすぐる箇所ですよね。
カジ「元ネタというほど露骨ではなく、オールウェイズらしく表現されていて、思わずニヤッとさせられてしまう感じというか」
――では、カジさんはいかがですか?
カジ「ちょっとプリミティヴズみたいな“Lollipop(Ode To Jim)”とすごくタルーラ・ゴッシュみたいな”Your Type”という2曲。今回のアルバムは、そういう80〜90年代ぐらいの頃のインディー・ポップのムーヴメントにあったテイストを意識的に打ち出した感じがすごくするんです。前作はそのあたりが、もうちょっといい意味で不明瞭というか、わりと同じようなトーンの曲が多かったような気がするけれど」
――彼女たちは、ベル・アンド・セバスチャンやカメラ・オブスキュラとか、90年代のグラスゴーのバンドが好きだと公言しているんですが、たしかに今作はそれらよりももうちょっと前の時代、カジさんのおっしゃっている80年代のインディー・ポップ――『C86』とかの頃のアノラックみたいな雰囲気の曲も入っていますよね。
カジ「うん、入ってる。それもマニアックに陥りすぎないというか、ただそういうのを真似してやりましたって感じじゃないのがいいなと」
――トゥイー・ポップっていわれるようなものって、ちょっとオタクっぽくなりすぎるきらいがあるというか、様式美を追求するあまりに、こじんまり纏まっちゃうことが多いですもんね。
カジ「そうだね。インディー・ポップみたいなのってどうしても小さくまとまりがちになるから、サークルのなかではすごく受けがよくても、どうしても外側の人たちはあまり興味が持てないっていうか。でも、やっぱりこういう作品が作られるとすごく広がる」
畳野「そうですね。本当に広がったなと思います」
カジ「ヴォーカルのモリーのインタヴューをちょっと読んだんですが、彼女は結構、古いポップ・ミュージックも掘っていて、それがすごく楽しいと言っている内容だったんです。このアルバムでは、そういう70年代とか60年代のポップスが好きな人の感じも、メロディーとかにすごく出てきている」
畳野「〈すごいキャッチー〉って言ったらあれですけど、今作は入ってくるメロディーが多いように感じました。1曲のなかでもそうだし、アルバムを通してもそうだし、耳に残るものがすごく多いなと思って」
――前作って、いわゆるインディー・ポップ・バンドのファーストとしては完璧だったなと思っているんですよ。メロディーがポップすぎない感じとか、抜けきらない感じも含めて、あれはあれで良かったと思うんですけど、そこからの本作で、一気に開けた感じは抗いがたいですよね。
カジ「ね。こういうインディー・ポップとかギター・ポップのバンドって、基本的にやっぱり様式美っていうか、ある程度、同じような感じっていう前提があるじゃないですか。でも、やっぱりいいバンドは確実にそこから抜きん出ているっていうか。ただのインディー・バンドじゃないという感じは、すごく出たなと思う」
畳野「そうですよね。風景がちょっと変わった感じもしました。前作はビーチや青い空とか、本当にいわゆるインディー・ポップのイメージっていう感じだったけど、今回はそこから広がって、夜の風景とかも見えてくるし、情景がすごく広がったなって」
――あと、おもしろいところでは、ティーンエイジ・ファンクラブのノーマン・ブレイクがグロッケンシュピールとヴォーカルで参加しているんです。自分もぜんぜん知らなかったんですけど、彼はグラスゴーからカナダに移住したらしくて。
畳野「そうなんですね、知らなかった。嬉しい繋がりというか、どっちも大好きなので※、理解できるし、すごくうらやましい」
※Homecomingsは2013年のノーマン・ブレイク京都公演でサポート・アクトを務めた
――そういう意味ではグラスゴーのインディー・ポップの系譜にも准える作品かと。ティーンエイジ・ファンクラブも、前身にあたるボーイ・ヘアドレッサーズというインディー・ポップ・バンドから始まって、90年代にはオルタナティヴ・ロックやブリットポップのシーンでも評価されるバンドとして音楽性を拡げていきましたよね。
カジ「ティーンエイジ・ファンクラブはすごいよね。僕は彼らのデビュー当時、普通に聴いていたんだけど、まさか彼らがあのボーイ・ヘアドレッサーズだとは思わなかったぐらい、パンチ力があったっていうか。音楽的には両方とも大好きだけど、ティーンエイジ・ファンクラブはアメリカのグランジの人たちからもリスペクトされて一世を風靡したよね」
――オールウェイズも、今作に関しては、もうちょっとオルタナティヴ寄りの音楽を聴いているリスナーにも、好意的にリアクションされている気がします。例えば、キャプチャード・トラックスあたりを好きなリスナーからも、並列に聴かれていそうですよね。
カジ「そうだね。本当にそれはあるよね」