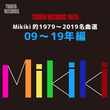〈ジオラマラジオはラボだ〉。インタヴュー冒頭、中心人物のlen(ヴォーカル)が語った言葉が印象的だ。正式メンバーはlenと、さかきばらみな(ヴォーカル、キーボード)の2人で、そこにスティーブン・ビチャルバーグ(ベース、ミュージック・ビデオも手掛ける)とPhil Kenta(ギター)というサポート・メンバーはいるものの、メンバー構成は流動的。バンドというよりかは音楽集団に近いのかもしれない。
ライヴ活動、そしてMVでの新曲発表を続けてきた彼らが最初に自主制作でリリースしたのは、カセットテープ+ZINE『ZOMBIE CASSETTE』(2018年作)。甘酸っぱいメロディーに、どこかで聴いたことがあるような郷愁感や親近感と、どこにもない新世代感が同居したポップ・サウンドが話題を呼び、早耳リスナーの間で話題となった。今年に入ってからは東京・渋谷WWWで、さとうもか、中村佳穂BANDといういまをときめく2者との対バンも経験。そんな彼らがついに初となる公式作品『img』をリリースする。len、さかきばらみなに話を訊いた。

ジオラマラジオは〈ラボ〉
――lenくんは最近〈ren〉から〈len〉に表記が変わりましたね。
len「アールの人がいっぱいいて、やめようかなって。名前がどんどん変わっていくのもいいかなって」
――ジオラマラジオは作詞作曲、その他全般をlenくんが務めていて、さかきばらさんの担当は……?
さかきばら「えっと……」
len「マスコットキャラクター!」
さかきばら「マスコットキャラクターです(笑)。あ、衣裳を手掛けています」
――(笑)。『ZOMBIE CASSETTE』にはZINEも付いてきて、lenくんの書く文章もおもしろいし、一緒に載っているさかきばらさんのセピアっぽい写真もすごい良くって。写真、お上手ですね。
さかきばら「ぼやーっとした写真で。あれ、私が使ってたフィルムカメラのレンズが傷付いてて、全部ああいう写真になっちゃっただけなんですけど(笑)」
len「それをボツにしないで使うっていう。自分たちのなかから、例えば音楽だけじゃなく文章でも写真でも、出たものをすぐに真空パックするみたいなことは、自分たちの活動に繋がることですね」
――ジオラマラジオって、そういう写真も文章も、ビチャさん(スティーブン・ビチャルバーグ)の撮るMVの雰囲気も全部リンクしていて、世界観が出来上がってると思います。
len「うれしいですね。映像とか映画の話は、音楽の話よりもずっとたくさんしてるんですよ。いろんな話をして、そのなかから彼らもアウトプットしていく。ビチャルバーグくんも人一倍ジオラマに対する熱い思いがあるので」
――ジオラマラジオは、そんな2人のメンバーと、2人のサポート・メンバーからなるユニットと考えていいですか?
len「サポートとか本メンバーとかも実はどっちでもよくて、バンド・メンバーは流動的でいいと思っています。いまは毎回ライヴにいるサポート・メンバー2人のことをコア・プレイヤーって呼んでるんですけど、実は誰がいてもいい。ライヴでもメンバーを固定していないし、今作でもドラマーにいろんな人を呼びました。ドラムスが叩けない場所ではリズムマシーンを使った編成にすることもできるし。そういうほうがおもしろいし、あんまりメンバーを固めたくないというのがあります。まあ一応2人組で、2人組なのに、いろんな人が関わっているラボみたいなものですね」
――今作では3人のドラマーに、ストリングスのアレンジに猪爪東風(ayU tokiO)さんが参加されています。彼らもラボのメンバーの一員ということですか。
len「ちょっとおこがましいですけど、参加していただくっていうことはそうですね。メインになる人は僕ら2人で、作品によってメンバーが変わるっていうのは、例えばダーティ・プロジェクターズに近いかもしれないですね。それぐらいのラフさが僕らのやりやすい形です」
――最近だとコレクティヴ(集団)っていう言葉もありますね。
len「コレクティヴですね。同じ思考を持った人が集まる集団。それか、いちばん近いのはヒップホップで言うところの〈クルー〉かもしれないです。それを意識してるわけじゃないですけど、ヒップホップは好きな音楽のジャンルでもあるし」
――バンドを紹介する側からすると、〈どこどこ出身の何人組〉とかあったほうが書きやすいんですけど、もしかしたらそういう形容詞を付けようとすること自体が古い考え方なのかもしれないですね。
len「もちろんそういう形容をするのもいいんですけど、僕らは出身地で先入観を持たれたくないんですよね。例えば、同じ音楽をやってたとしても、〈東京出身4ピース・バンド〉と〈大阪出身4ピース・バンド〉では持つイメージが変わるじゃないですか。先入観で変わっちゃうのってもったいないし、もっとフラットに聴いてもらいたい。何の先入観もなく聴いて、いいなって思ってもらえるのが理想です」
――たしかにそうですね。それと、首謀者のlenくんはライヴではヴォーカルに専念してるから、どういうふうに楽曲を制作しているのかも気になります。
len「昔はギターで曲を作ってたんですけど、好きなコード進行でしか曲が作れなくなっちゃうから、つまんなくってやめて。いまは基本的に〈イメージ〉から曲を作るんです。例えば今作にも入ってる“Zombies!”だったら、まず〈ゾンビの曲を作ろう〉と。で、〈どういう雰囲気にしようかな?〉って頭のなかで組み立てると、自然とメロディーとか歌詞が浮かんできて、それを(スマホの)ボイスメモに吹き込んで。そうやって全体像を掴んでからパソコンで作ります」
――それをコードに落とし込むんですか?
len「コードとかもよくわからないんで、一音ずつ打ち込んでますよ」
――すごい、天才かもしれない。
len「いやいやいや(笑)」

きっかけはドラマーの脱退と津野米咲らとの出会い
――昨年の『ZOMBIE CASSETTE』まではリリースがなかったけれど、こうやってリリースをしていこうと決まったのは何かきっかけがあるんですか?
len「マネージメントとか、信用できる人との出会いもあったし、赤い公園の津野米咲さんに〈やりたいことはわかるけど、CDは出した方がいいよ〉って言われたのも大きいですね。実は今回のリリースに関してはどんどん当初の意図からズレていて、最初は、以前在籍していたドラマーがバンドを辞めることが決まっていて、彼の卒業制作のつもりでCDを出すっていう話だったんです。〈春には出そうか〉って話していたのが長引いちゃって。それで今年の頭に渋谷WWWで〈NEWWW〉っていうイヴェントに中村佳穂さんたちと一緒に呼んでもらって、そこで〈初夏にアルバム出します〉って言ったんですけど。結局10月に、アルバムじゃなくてEPが出るっていう(笑)」
さかきばら「めちゃくちゃ長引いたね」
――ドラマーの卒業も関係なくなっちゃって。じゃあきっかけはドラマーの脱退が半分、津野さんたちとの出会いが半分?
len「そうですね。しかも今回はリリース日(10月2日)が津野さんの誕生日でもあって。これも半分偶然、半分愛(笑)。僕らの姉さんが導いてくれた感じもありますね。あんまり言わないようにしてますけど」
――(笑)。今回は何にそんなに時間がかかったんですか?
len「全部納得いくまでやったら必然的に時間がかかっちゃったって感じで、自分たち的に沼にハマってた感覚はなかったんですけど、周りからは〈ヤバいんじゃない?〉って思われてたみたいですね」
さかきばら「スタッフは〈大丈夫ですか?〉ってね」
len「レコーディング大好き人間なんで、永遠にレコーディングが続けばいいって思ってるんです。〈終わったら出せばいっか〉って。それにスタッフにも恵まれていて、〈いいものが出来るまでは出さなくていい〉って腹を括ってくれたんですよね」
――さかきばらさんはどうでした?
len「みなちゃんは今回のレコーディング、2日くらいしか来なくて。ヴォーカル録りの時と、ドラムス録りの時くらい」
さかきばら「いやいや(笑)。レコーディングの終わり際にたこ焼きを持って行って、自分で食べて。そんなに時間かからないだろうなと思って。エンジニアさんが綺麗好きな人だったから、スタジオのお菓子を綺麗に並べてました」
――(笑)。じゃあ、その長い制作期間は何をもって完成とするんですか?
len「作業の終わりは見えてたんですけど、先にリリパの予定が決まっちゃったので、終わりを決めて。そこから逆算して」
さかきばら「すごい急いだね」
――もちろん音は満足いくものに仕上がったんですよね。
len「もちろん。もうやりつくしすぎました」

マネージメントだけが付いている僕らの規模のいちばんの利点
――今作の周りからの反応はいかがですか?
len「津野さんは“orange”がいちばん好きって言ってたかなあ。でも“orange”の人気がありすぎて、みんなが好きなのは分かるけど、自分の手癖で特に何も考えずに作った曲だから〈この曲でいいんですか?〉みたいな感じはあります。この曲はみんながいいって言うから、そんなに言うなら録ろうかなって録ったんですよね。もちろん今作は6曲とも全部同じくらい好きだし、どの曲を世に出しても恥ずかしくないんですけど」
――“orange”はずっとライヴでやってたので音源化が待ち遠しかったです。このイントロのギターの音は?
len「あれはウチにあるセミアコをiPhoneで録ったのをそのまま使ってますね。いまの体制のいいところとして、めちゃめちゃ高いマイクも使えるし、iPhoneでもいい。そういう何でも選べる自由さっていうのがありますね。(今作には未収録でMVのみ公開されている)“さよならレディ・スターダスト”なんて一部はMacの内臓マイクで録ってます。ハマっちゃえば何でもいい」
――制約がなく自由に作れる。
len「はい。それがマネージメントだけ付いている僕らの規模のいちばんの利点だと思います。チャンス・ザ・ラッパーとかもそうやって出てきたわけだし。僕らも協力してくれる仲間がドラクエのように次第に増えていって、心強いし、ありがたい限りです」
――“MAPLE”はそれこそダーティ・プロジェクターズに近い変態さとか、USインディーっぽさが出てますね。
さかきばら「“MAPLE”が好きっていう人はいちばん少ないかも(笑)」
len「でも“MAPLE”でやりたいことの方向性がバシっと決まった感じはあったよね。あそこからどんどん発展していったね」
――個人的にいちばん好きなのは1曲目の“step”です。
len「やった!」
――決して、ぽいわけではないんだけど、例えば小沢健二の“天使たちのシーン”を初めて聴いた時のような感動がありました。日常の何気ない景色がキラキラして見えるような。
len「“step”にはいまの僕のすべてを詰め込みました。今回出来た音源をいろんな友達に聴かせてるんですけど、同じ世代の友人たちから〈“step”ヤバいね〉って反響がすごくあって。これまで僕らって、お兄さんお姉さんみたいな人からよく信頼はされていて、それって以前はもっとインディーっぽかったし、例えばペイヴメントっぽかったり、90'sのオルタナ好きに響くような音楽だったりするからだと思うんですけど。でも今回は同世代にも響くっていうことを意図して作ったので、そういう友人から反響をもらえたのは自信に繋がりました。納期の前日夜から朝までミックスして、エンジニアさんから〈最高傑作です!〉って来た最終テイクが実際に最高傑作だったんで、この曲だけで現時点の〈最高〉は作れたと思っています。
――本当そう思います。
len「“orange”みたいな曲はサビがドーンとあるから分かりやすいけど、“step”はサビがどこだか分からないし、それがもしかしたらいわゆるオザケンっぽさに繋がってるかもしれない。構成はJ-Popらしくないんだけど、メロディーはすごく歌謡曲で。それはやりたかったことでもありますね」
――“Zombies!”は『ZOMBIE CASSETTE』にも収録されていますけど、改めて録り直しました?
len「歌も楽器も全部録り直しました。ドラムスはMONO NO AWARE、Jurassic Boysの(柳澤)豊さん。豊さんは男気に溢れた良い人で、すごく好きになりました」
――ドラマーは各曲で3人が起用されてますけど、それぞれの曲に選んだ理由は?
len「いろんなドラマーと試してみたいし、曲によって適性があるし。豊さんと堀正輝さん、いまライヴでサポートしてくれてる奥村大爆発くんの3人はそれぞれ違う良さがあって、選曲もバッチリはまって良かったです」
――“honey / なんて傲慢な…!”は歌詞にもMVにも〈旗〉が出てきますよね。
len「大人になることって楽しいこと、素晴らしいことだと思うんです。年を重ねて初めて分かることもある。だけど、いつまでも記憶に残る思い出たちも大切で。それまで人生で経てきたいくつもの名場面に旗を立てていきたいと思って、そのイメージを曲にしたんです」
――なるほど。だからMVにも旗が出てくるんですね。
len「MVで実際に旗を立てるのはビチャルバーグくんから出たアイデアで。実はあの場所はビチャルバーグくんの地元で、彼の家から10分くらいの場所なんです。だから裏テーマとして、幼少期への追憶みたいなものもあります。思い出の場所に旗を立てるっていう精神が大事だなって思うんですよね」
さかきばら「(ビチャルバーグくんの)お兄ちゃんに運転してもらってね。みんな運転できないし、できてもペーパードライバーだから」
――あのMV、すごくいい映像ですよね。
len「MVのタイポグラフィーはアルバムのデザインをしてくれた、てっちゃん(沖山哲弥〈Mount Stew〉)がやってくれて」
――じゃあアルバムのアートワークについてもお聞きしましょうか。紙ジャケだし、歌詞カードも本当にカード型で、かなりこだわった作りですね。
len「歌詞カードは、表面が写真、裏面が歌詞で、全部歌詞にちなんだ写真が印刷されてるんです(写真はオフィシャルサイトにも掲載)。“step”は出会いと別れの曲なので、花言葉が関係のあるスイートピーを。“MAPLE”は秋から冬にかけて足踏みをする季節なので、その季節感を」
さかきばら「よく見るとメープルなんだよね」
len「え、本当だ!! “honey / なんて傲慢な…!”は分かりやすくミツバチ。“orange”は砂浜で踊る男女の足跡」
さかきばら「それをヤドカリが見てて」
len「“telephone card”は受話器。“Zombies!”はPCのキーボードなんですけど、なんでコマンドキーと〈Z〉なのかは、ぜひ考えてもらいたいですね。デザイナーからこのアイデアを聞いた時は鳥肌が立ちました」
――ジャケットの煙突から煙が出ているのは?

len「『img』というのは〈イメージ〉って読むんですけど、どんな表現においても、表現のおおもとってイメージだと思うんです。でも頭のなかのイメージってもやがかかっていてクリアじゃない。それをクリアにするのが表現なのかなって思うんですよね。今作ではそのおおもとの部分にフォーカスしていて、デザイナーさんと話し合って、アートワークが全部ぼやけている案が上がってきて。だから、もやもやしたものの象徴として煙突から出る煙が選ばれたし、ジャケットの〈img〉という言葉だけがぼやけているんです」
さかきばら「曲ごとに色のテーマで分かれているので、裏ジャケではその色の煙が出ていて」
len「てっちゃんとの初回のデザイン打ち合わせの時、曲作りの根本から知りたいって言ってくれたので、楽曲解説を書いて説明して、それはオフィシャルサイトにも載ってます。それを元にこういうアートワークも作ってくれて」
――画像だけで見るより手に取ったほうが感動しますね。
len「めちゃめちゃ愛おしい盤に思えてくる。出来上がったときは本当に感動しました。僕は〈神は細部に宿る〉って思ってるんですけど、さっきも言ったようにこういう細かいところまで自分たちでできるのが、僕らの規模でできることの最大の利点だと思うので。アートワークには遊び心もあるので、ぜひ細かいところまで見てほしいですね」

ポップスの普遍性と、そこに対するアンチテーゼ
――さっき“MAPLE”の時に話に出てきた、ジオラマラジオのやりたい方向性っていうのは、あらかじめ目標が用意されていたんですか? それとも作ってる最中に見えてくるんですか?
len「基本的に制作チームには根底に、〈インディーから革命を起こす〉じゃないけど、ポップスに取って代わるものを自分たちが作るっていう〈既存のポップスに対するアンチテーゼ〉みたいな反骨精神は持っていますね。そこからその時その時で、聴いた音楽とか観た映画から影響を受けて、どういうコンテンツを作っていくか考えながら、できる最高のことをやっていく。でもそこで〈こういう曲作ったらウケるだろ〉みたいな打算的なことは考えていないです。それが無いのが良さでもあり、足を引っ張るところでもあるんですけど。でもこういうふうにやっていきたいし、変えたくないところです」
――そういうのって、さかきばらさんにも言葉で共有するんですか?
さかきばら「いや、全然」
len「根本的にみなちゃんはわかってなくてもいいと思ってます。わかってない人がメンバーにいるってのは大事なことかもしれないし。もちろん反骨精神はみんな持ってるんですけど、コンテンツの方向性とか、どう微調整していくとかは、言葉で伝えるなり、音で感じてもらうなりで、徐々にメンバーに伝えていく感じですね」
さかきばら「私、ボケボケであんまり何も考えてなくって(笑)」
――さかきばらさんは服を作りたいんですよね(笑)※。でも〈ポップスへのアンチテーゼ〉が根底にあるのに、影響を受けたのはSMAP※っていう、言わば〈どポップ〉なのがジオラマラジオのおもしろいところですよね。(※どちらも過去のインタヴューでの発言より)
len「いい質問をしてくれてありがとうございます。僕らは〈TokyoNouvelleVague.(トーキョーヌーヴェルヴァーグ)〉というテーマを掲げていて、ジオラマラジオ自体をひとつの実験の場にしたいんです。ビデオも自分たちで作るし、ゆくゆくはみなちゃんが服作りたいっていうならアパレルもやってみるかもしれないし。その根底にある〈TokyoNouvelleVague.〉っていうのは、僕らがすごく好きな、1950年代のフランス映画の潮流の〈ヌーヴェルヴァーグ〉が元になっていて。
大衆映画って一時期、大がかりなセットを組んでお芝居をするのが基本になってきて、テンプレが出来上がってしまったんですね。どポップになりすぎて、形骸化して腐敗してきちゃう。そこでゴダールとかトリュフォーといったフランスの映画オタクの若者たちが集団で、それらへのアンチテーゼとして手持ちの8ミリカメラだけで映画を作り出すんです。街角でゲリラ撮影とかをして。それもめちゃくちゃセンスが良くて、超おもしろくて。僕らがポップスでやりたいことって、その流れと似ているなって思って〈TokyoNouvelleVague.〉っていうのを提唱しているんです。映画の質感を真似たいとかではなく、もっと精神的に、日本のポップスが大好きで、聴いて育ってきたからこそ、最近のJ-Popはおもしろくないと思っている部分もあって、そこに対するアンチテーゼをインディーからやりたいと思っていて。だからポップスから影響は受けているけど、やりたいことはポップスに疑問符を投げかけたい。こういうアプローチの仕方もあるんだよというのを出したいんです」
――なるほど。もうひとつ気になっているのが、ジオラマラジオの楽曲には独特のにおいがあると思っていて。あのにおいがどうやって作られてるのかがずっと気になっているんです。例えば子供の頃に読んだ、なぜ家にあるのかわからない洋書とか、一瞬だけ観た洋画のワンシーンとか、ああいうにおい。
さかきばら「うれしいです」
len「ジオラマ感みたいなもの。やっぱり僕の優しさとか、人間性かな(笑)」
――この発言には(笑)を足しておきますね(笑)。優しさですか。
len「優しい人間なんで(笑)。でも、もしかしたらデモ曲はもっと灰汁が強くて、それを薄めたのが完成形かもしれないです。ただ、大衆音楽って、どこの国でも歌われてることって結局は一緒だと思っていて。愛とか恋とか、人が死んだとか、大体同じことが歌われていて、それは人間のコアの部分だし、ポップスの普遍性でもあると思うんです。だって大衆音楽っていうのは、いろんな人が大切に噛みしめながら人生と共に歩んでいく音楽なので。特別意識しながら作っているわけじゃないけど、そこは重要なポイントだとは思っています。そういうところで、懐かしさとかを感じるのかもしれないですね。
だから僕も、においっていう表現はよくわかります。琴線と涙腺に触れる部分があるというか。それはさっき言われた小沢健二さんの曲もそうだし、ハイスタ(Hi-STANDARD)を聴いて涙ぐんじゃったり」
――それはすごいよくわかります。
len「なので、今回の“step”っていう曲は特にそれを意識しました。最近〈エモい〉って言葉をみんなよく言うけど、〈それって本当にエモい?〉って思うことが多くて。僕らの思う〈本当のエモってこういうことじゃない?〉っていう部分を入れてます。それは方法論とかではなくて、人に対する感情とか、想いとか、歌詞もメロも全部。それが結局、琴線に触れる部分になるんじゃないかなって思います。
それと今回は、〈感動する音楽って現場にも感動がないといけない〉と思っていて、インディーの現場にはまだそれがあるんですよね。みんなで〈ヤバイもん作っちゃったね〉みたいな感覚になる。まあ、それは本人たちの過信かもしれないけど、一緒に関わったチーム全体がそう思えることが大事だと思っています」
――本当に良い環境で作れたみたいですね。お2人は、ゆくゆくはどうなりたいですか?
len「ゆくゆくは……解散したいですね(笑)。早めに」
――(笑)。さかきばらさんもうなずいてるけど、それはいいんですか?
さかきばら「ずっと言ってることだし」
len「解散して、ピザ職人になるためにイタリアで修行したいですね(笑)」
さかきばら「わかる」
――わかるんだ(笑)。
さかきばら「別のことやりたいよね」
――まあ、最近DIYで音楽をやってる若い人たちには、いまは音楽を作ってるけど他のことをやってもいいっていう人が結構いますからね。
len「そうですね。ジオラマラジオとしてやりたいことをやったら、解散したいです。ずっと同じメンバーで一生やり続けたいっていうタイプの人がいるのもわかるけど、ジオラマラジオはそういうタイプじゃない。打ち上げ花火みたいな集団で、どういうふうに上がるかも分からないし、そもそも打ち上がるかどうかも火を着けてみないと分からないし。もう火を着けてしまったから後は知らないよっていう」
――地上で爆発するかもしれない。
len「かもしれないし、メンバーが誰か捕まるかもしれないし(笑)」
さかきばら「捕まるなら誰かなあ(笑)」
LIVE INFORMATION
ジオラマラジオ 1st ep. "img" release live
2019年10月19日(土)東京・新代田FEVER
開場/開演:18:30/19:00
出演:ジオラマラジオ/SaToA/uri gagarn
前売り/当日:2,000円/2,500円(いずれもドリンク代別)
http://www.fever-popo.com/schedule/2019/10/19/