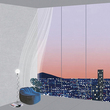世界をトリコにする、クセになるサウンドを密封したライヴ・アルバム
サイケデリックなギターともっさりしたベースの旋律線をブレイクビーツ風のドラムが下支えするアンサンブルのくりだすエキゾチックでゆるやかなグルーヴを、私たちはきっとはひと昔前なら「イナタい」といって憚らなかった。テキサスからやってきた男女混合の三人組クルアンビンは2000年代なかごろの結成から数えて十年になんなんとする下積み時代に現在のスタイルを確立し、2015年の『The Universe Smiles Upon You』でデビューしたころは好事家の耳目を惹いたにすぎなかったが、映像化の時代にあって、ベースのローラ・リーはじめ、なにかと映えるルックスも相俟ってじわじわと存在感を高め、18年の2作目『Con Todo El Mundo』を経て、今年3月の来日では追加公演まで出る盛況ぶりだった。

その理由はなんといっても彼らのクセになる音楽性に由来する。1960~70年のタイのロックやポップスのレアグルーヴ的捉え直しを意味する「タイ・ファンク」を音楽的影響源と公言するクルアンビンの楽曲には五音音階のモチーフが多出し、ゆったりとった音と音のあいだの隙間をマーク・スピアーのギターが滲み出していく。とはいえ編成はオーソドックスなインストバンドであり、見てくれ以外に奇をてらったところはみあたらない、と思いきや、よくよく耳を傾けるとベースのフレーズはタイの2弦楽器「ピン」っぽかったりするしギターは「ケン(タイのリード楽器)」のような背景音を奏でていたりするのが油断ならず、それらをまったりと、しかし周到に聴かせていくのはDJカルチャー以降の感性といっていい。それを裏書きするように、シカゴのリンカーン・ホールでの演奏を収めた本作の、ライヴでは好例となったメドレーではドクター・ドレからJディラまで、往事のヒップホップをとりあげ、サンプラーのビットレイトを模した空気感で、過去の秘宝が2010年代に生まれかわっていることを物語るのである。