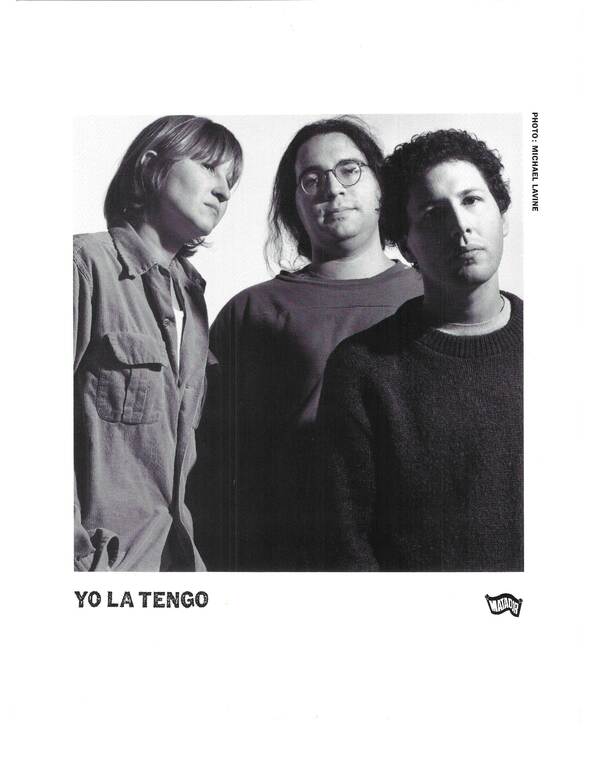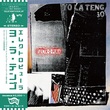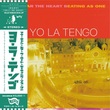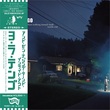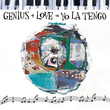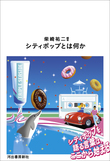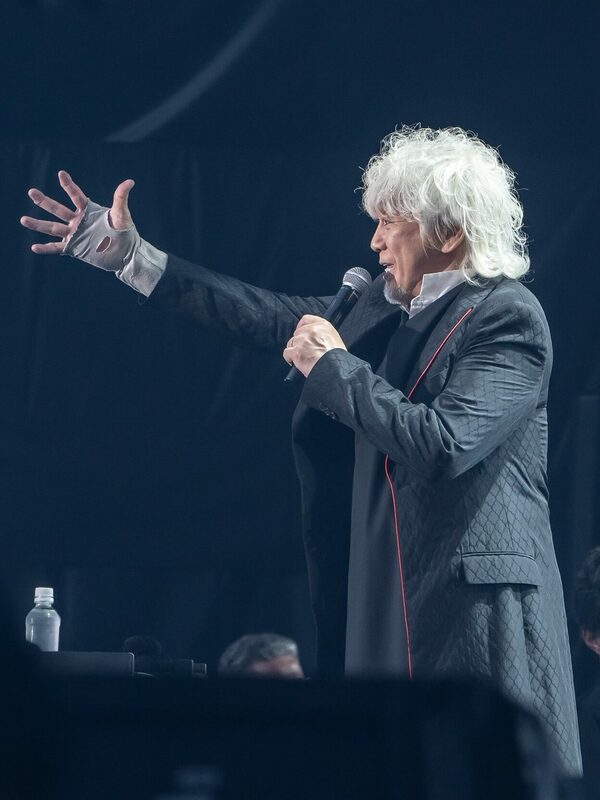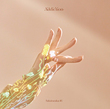福田教雄(Sweet Dreams Press)の3枚

『Fakebook』(1990年)
『And Then Nothing Turned Itself Inside-Out』(2000年)
『Stuff Like That There』(2015年)
ヨ・ラ・テンゴが新しく発表する作品に接するたび年々強く思うようになったのは、いかに自分が音楽から離れてしまったかということだ。それはなんら悪いことではないが、なぜだか罪悪感や焦燥感を感じさせられることでもある。音楽よりも人生に起こるあれこれを優先せざるを得ないときは誰にでもあって、でも、3人がつくる音楽は自分が落ち着くまでそっとしておいてくれる。いつも歩調を合わせていくわけにはいかないが、ときどき追いつくようにして、でも、一緒に進んでいるという感覚を持てる音楽家やバンドがいるということは人生においてとても幸せなことだと思う。そんな風に今はヨ・ラ・テンゴのことを感じています。どうもありがとう。
イアン・F・マーティン(Call And Response Records)の3枚

『I Can Hear The Heart Beating As One』(1997年)
『Painful』(1993年)
『I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass』(2006年)
ヨ・ラ・テンゴはたくさんの表情を持っている。ヨ・ラ・テンゴはメロウであり、獰猛でもあり、なだめるような音楽を奏でたかと思えば調子っぱずれで、だけど聴きやすく、挑戦的で、実験的で、ポップだ――これらのうち1つか2つの要素は、ときにアルバム一作のなかに同時に存在しており、またあるときには聴き手をそのすべてへと一気に引きずり込む。でも、私にとってヨ・ラ・テンゴは、音楽の可能性をぐっと押し広げられる感覚と結びついたバンドだ。
同世代の多くがそうだったように、私はアルバム『I Can Hear The Heart Beating As One』を通じてヨ・ラ・テンゴの世界へと足を踏み入れた。1997年――ブリットポップの商業的かつ野心的でソフトなナショナリズムが衰退していった時期――に発表された『I Can Hear The Heart...』は、私にとって奇妙で、興味をそそられるものだった。そして、すべてを完全に理解するのが難しい作品だとも思った。そのかわり、その後、私はあのアルバムに何度も立ち返ることになる。なにか新しいものを発見するたび、音楽への理解を少しずつ広げていくたび、あのアルバムは、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドやクラウトロック、ポスト・パンクやビーチ・ボーイズ、そしてそれ以上のなにかが、いかに他の音楽と繋がっているのか、その関連づけを手助けしてくれた。
私はその後、1993年のアルバム『Painful』を発見する。『Painful』は、新たな音楽的語彙への感覚をちがったやり方で開拓してくれた。それ以前もヨ・ラ・テンゴはいいバンドではあったが、『Painful』は彼らが新たな音の世界へと急激に雪崩れ込んでいったことを感じさせるのだ。アルバムは穏やかに始まるものの、徐々に大胆さを見せていく――ヨ・ラ・テンゴは、いつのまにかあなたをすっかり魔法で包み込んでしまっている。そして、自分はいまマスターピースの内側に入り込んでいる、と気づかされるポイントがある(私にとってそれは、スペースメン3風の“I Was The Fool Beside You For Too Long”の中間あたりだった)。そう気づくと、本作はより一層スリリングになる。なぜなら、あなたはいま新たな創造の領域を初めて探検していることを、バンドと共有しているのだから。
ヨ・ラ・テンゴが私の心を揺さぶるもうひとつの方法、それは、ステージでのパフォーマンスだ。そして、彼らのライブを観る体験は、2006年のアルバム『I Am Not Afraid Of You And I Will Beat Your Ass』と常に結びついている。オープニング・ソング“Pass The Hatchet, I’m Goodkind”は、シンプルかつキャッチー、ベースラインはありがちなロックのそれだが、11分間にわたって容赦なく、まるでロボットのように打ち付ける曲だ。楽曲が進んでいくにつれて、ギターはめちゃくちゃに暴れ回る。彼らの〈わかりやすさ〉と混沌とがステージ上で戦うさまは、驚くべきものだと言っていい。レコードはライブでの体験を再現することはできない。しかし、『I Am Not Afraid Of You...』は素晴らしい成果を上げている。ヨ・ラ・テンゴが表現するさまざまな表情のコントラストを強烈に対比させることで、ライブの興奮に近い感覚をもたらしてくれるのだ。
訳:天野龍太郎
松永良平(リズム&ペンシル)の3枚

『Fakebook』(1990年)
『I Can Hear The Heart Beating As One』(1997年)
『Fade』(2013年)
初めて聴いたアルバムは1987年の『New Wave Hot Dogs』で、上京後まもなく。たぶん18歳くらい。池袋にあったオンステージヤマノで買った。彼らに対して知識があったわけではないし、特に強く推されていた記憶もない。バンド名とジャケットにぼくの好きなタイプの謎感があったし、ちょうどアメリカのポスト・パンクやインディー・バンドにもっと興味を持ち始めていた時期でもあった。そのころ、フィーリーズのファーストやビーチ・ボーイズの『Surf’s Up』あたりも一緒に買ったはず(オンステージヤマノさんには本当にお世話になりました)。
『New Wave Hot Dogs』の頃の彼らはまだずっとひ弱で、アルバム自体も傑作だとは思わなかったけど、少ない生活費のなかで買った一枚だから何度も聴いた。一度しか聴かないレコードもたくさんあったから、あれを何度も聴いたのは、当時の生活になじむものがあったんだろうな。しかし、そんな生活のなかにも他の名作レコードがどんどん流れ込んできて、お金に困ったときにあのアルバムは売り払い、ヨ・ラ・テンゴのことも忘れた。忘れてしまったために、彼らの初来日(1989年)を知らずに見過ごした。チャンスはあったのに!
しばらく忘れていたヨ・ラ・テンゴのことを思い出したのは、高円寺の喫茶店で働きだしてからのこと。店員が好きなレコードやCDをかけられる店で、バイトの先輩があるときかけたのがフォーキーなカヴァー・アルバム『Fakebook』だった。あの居心地のよい日陰みたいな感覚は、当時ぼくが夢中になっていたジョナサン・リッチマンやキンクスの『Village Green Preservation Society』や『Muswell Hillbillies』にも通じるものだった(『Fakebook』で彼らはキンクスの“Oklahoma, U.S.A.”をカヴァーしていた)。
さらにアルバムを聴き進めていくと、もう一曲すごくいい曲を彼らはカヴァーしていた。聴き覚えが確かにあるはずなのに誰の曲なのかすぐに思い出せない。
その曲は“Did I Tell You”。あれ? これって『New Wave Hot Dogs』で好きだった曲じゃないか。ヨ・ラ・テンゴの曲だとまったく思いもせずに聴いたその曲で、ぼくの記憶は彼らの現在に連結された。
ライターになってからは取材も何度かしているし、その後に見たいくつものライブにまつわる思い出もいっぱいある。だけど、あのときの驚きはやっぱり忘れられないし、本気の好きはそこから始まった。いまも彼らに対しては、自分が自分であることにまつわる意外性の尊さを教えてもらってる。
きみって、きみだったのか! みたいなね。