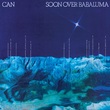戦後ドイツの焦土から生まれたバンド
また、シュミットへのインタビューや著述家・明石政紀の論考「焦土からの再生〜クラウトロックを育んだ戦後ドイツの風景」で興味深かったのは、カンの音楽にもやはりナチス・ドイツが影を落としていることだった。
開放的で、どこまでも自由で、いたずらっぽい諧謔精神に満ちたカンの音楽の背景には、暗く重い、拭い去れない過去がある。「私たちはみな、破壊されて廃墟になった街で育った。しかも、自分たちの親世代がファシズムを信奉して文化を破壊したわけで。そこからは自分の中に否定しようのない不吉さやダークサイドのようなものが芽生えてくる」とシュミットは言う。
つまるところ、カンとは戦後ドイツの焦土から立ち上がったバンドなのだ。彼らが時折見せるダークで恐ろしげな表情はそういったところからきているのか、と合点がいった。
だから、「カン大全」はカンをドイツのバンドとして歴史的、文化的に位置づけ、彼らのドイツ的(あるいは非ドイツ的)な相貌とはどんなものなのかを描くことに重きが置かれているように思う。カンについては、ムーニーやダモ鈴木にまつわる突飛なエピソード、あるいは上に書いたポスト・パンク・バンドへの影響ばかりが語られがちだ。しかし、同書はそんな伝説のバンドの実相をとても冷静に、深い位相で取り戻そうとしている(同じドイツのバンドとして、徹底的にコンセプチュアルなクラフトワークと比較してみると、より見えてくるものがあるだろう)。
カンの音楽に宿る未来の予感
石野卓球、Corneliusこと小山田圭吾、そして坂本慎太郎が今回のリイシューにコメントを寄せていることからわかるように、カンは日本の音楽家たちから愛されているバンドである。OGRE YOU ASSHOLEの近作などを聴けば、いまもこの国でカンが強い影響力を持っていることが伝わってくるだろう。
カンは近年の音楽シーンにおいても重要なバンドである。2000年代以降のインディー・ロックが立ち返ったのは、(ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとともに)カンに代表される、いわゆる〈クラウトロック〉のサウンドだった。たとえば、アニマル・コレクティヴのあのオプティミスティックな音楽は、きっと『Future Days』の残響のなかで育まれているはず。インディー・ロック・バンドの大御所であるスプーンはバンド名をカンの曲名から取っている、というエピソードもある。また、ブラック・ミディ(black midi)とダモ鈴木との共演が示すとおり、現在盛り上がりを見せるロンドンのロック・シーンも、確実にカンの影響下にある。
カンが残した作品群は、半世紀近い過去のものだ。そして、それらをいま改めて聴いてみればわかるとおり、その音楽は〈ロックではないなにか〉を常に内包していた。だからこそカンの音楽には、まだ見ぬ未来の日々の予感、その可能性が、未分化な状態のままで詰まっている。
彼らが奏でた、どろどろした、ぐにゃぐにゃした不定形のサウンドの底知れなさには、何度触れても驚かされる。これから先の〈Future Days〉を生きる未来の人々も、きっとカンの音楽に驚きつづけることだろう。
※このコラムは2020年12月10日発行の「intoxicate vol.149」に掲載された記事の拡大版です