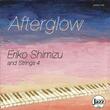清水絵理子の音楽は誰の音楽にも似ていない。クラシック界のホープとして注目されるも、19歳からジャズの世界に飛び込み、ライブハウスという現場で自らのジャズを構築し始める。これまでに山口真文や竹内直、峰厚介らさまざまなアーティストのバンドでレギュラーピアニストを務め、自身でも『SORA』(2010年)、『Afterglow』(2013年)、『Double axes』(2018年、加藤真一との共作)という3枚のアルバムを発表してきた。独自の世界観を提示してきた彼女が、2022年1月26日(水)に Days of Delightから最新作『Aspire』を発表する。彼女の音楽性がどのように培われ、いかにしてこのアルバムに結実したのかに迫った。
クラシック漬けの生活に耐えきれず爆発してしまった
――清水さんは幼少の頃からクラシック音楽のピアノを弾いていらして、その後、ジャズを演奏するようになったと伺っています。どのような経緯でジャズを演奏するようになったのですか?
「私の場合、クラシック音楽から徐々にジャズに移行していったわけではないんです。音楽そのものとピアノから完全に離れてしまった時期があって、そんなリセット状態の中で、突然ジャズの世界に出会った、っていう感じです」
――といいますと?
「祖母が私の家の向かいでピアノとエレクトーンの先生をやっていたので、小さい頃から遊び道具のようピアノを弾いていました。5歳からは外の音楽教室に通うようにもなりましたし。小学校に上がってからは、全国から数人を選抜した特殊なクラスに入って、海外に演奏旅行に出掛ける機会に恵まれたり、マキシム・ショスタコーヴィチの指揮で新日本フィルハーモニー交響楽団と一緒に自作の協奏曲を演奏したり、普通では経験できない世界を見ることができたのですが、それと引き換えに、生活のすべてが音楽になってしまって。
音楽活動を優先させるために、それまで通っていた学校から転校したり、食事と睡眠以外はすべてピアノという生活。楽しかったはずの音楽がどんどん苦痛になってしまったんです。そんな生活に耐えきれず爆発してしまったのが16~17歳の頃。〈もう、いや! ぜんぶ辞めてやるっ!〉と、ちゃぶ台をひっくり返したわけですね(笑)」
――16~17歳というと最も多感な頃ですよね。
「そうですね。時が過ぎたので、今ではこうして笑ってお話しできますけれど、当時は本当に壮絶でした。周りの人たち全員が敵のように思えて、ピアノの近くに寄ることすらできない状態。心が音楽からすっかり離れてしまいました」

強烈な〈ジャズの匂い〉を味わったのが転機
――その後は、どのように過ごされていたのですか?
「2年くらい何もせず、アルバイトを転々としながら過ごしていました。そうしたら、そんな私を見かねた母が、〈ピアノが弾けるんだから、ピアノを弾くアルバイトでも探してみたら?〉と声を掛けてくれて。探してみたら、その当時、向島にあった〈インフィニティ〉というジャズバーの〈ピアノ奏者募集〉という広告を見つけたんです。当時の私は、〈ジャズバーってどんなところ? ジャズって何?〉という状態でしたが、ピアノが弾けるからまあ大丈夫だろうと(笑)」
――そこでジャズと出会われた。
「そうです。それまでの私はクラシック一辺倒。ジャズが何であるかもまったく知らない状態でした。仕事は、お店の手伝いをしながら、ジャズ〈風〉に演奏するというもの。アドリブなんてものにはほど遠かったけれど、それでもその仕事を通してだんだんとジャズを知るようになったんです。有線放送から流れてくるジャズを聴きながら、お客さんたちから、〈これは◯◯というピアニストが弾いているんだよ〉とか、〈このアルバムを聴いてごらん〉と教えていただき、たとえばウィントン・ケリーみたいな大好きなピアニストを知ることもできました。
そうやって少しずつジャズのことを知っていったんですが、そうした知識以上に大きかったのは、ジャズの生演奏が毎日繰り広げられていたこと。そのお店は、よくプロのミュージシャンも遊びに来ていたし、お客さんにはジャズ研究会OBも多くて、そういう人たちが集まると夜な夜なセッションになるわけですけど、彼らの演奏が私のピアノとはぜんぜん違うんです。それまで味わったことのない強烈な〈ジャズの匂い〉がして。まさに、目から鱗が落ちる思いでした。その時に気づいたんです、私は〈ピアノは弾けるけれど、ジャズは弾けない〉と。そんな中で、気がついたら完全にジャズにハマっていました」
――そこからジャズピアニスト清水絵理子がスタートした?
「その〈インフィニティ〉からはじまり、他の店でも演奏している時、〈御茶ノ水NARU〉の先代マスターである成田勝男さんに出会い、ある時、〈ウチでも弾いてみるか?〉と声を掛けてくださったんです。毎週1回のペースで出演させてくださり、そこで大勢のプロミュージシャンと定期的に演奏したり、プロのセッションに参加したりするようになりました。それが私のジャズミュージシャンとしてのスタートでしょうね」