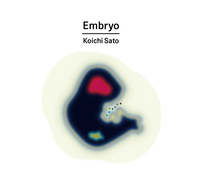ジャズは動き、今多彩な顔を見せていることを示す2枚組をリリース
鋭敏な純ジャズ・ピアノ演奏(ex.本田珠也ICTUSトリオ)から、涼風を伴うサウンドスケープを描く作品(ex.前作『Melancholy of a Journey』)まで。ピアニストである佐藤浩一の表現は幅広くも研ぎ澄まされ、新しい美意識に富む。そんな彼の3作目となる『Embryo』は、2枚組の作品だ。自分の中にあるメロディを素直に拾うDisc1〈Water〉はソロでレコーディングされ、Disc2〈Breath〉は弦楽器も用いるアンサンブル盤という内訳を取り、半数はそれぞれに同じ曲を紐解いている。
「ソロのほうは、ちょっと変わった調律(ヴァロッティ音律という古典調律を応用した調律)を用いているんです。それと曲調が相まっての不思議なサウンドだな、まるで赤ちゃんがお腹の中から聴いているみたいだなという話が出まして、それで『Embryo』(胎児という意味を持つ)と付けました」。ソロ・ピアノの録音で古典調律を用いた事について、「すごい新しい感覚でした。今までにない発想を得ました」と、彼は振り返る。
一方のDisc2は、佐藤が過去作で求めてきた情景的でもある路線の延長にある。「そうですね。ただ、弦楽カルテットが入っており、それは今まで自分の音楽に入れたことはないので、それについては初めてとなります」
両Discはともにゆったりと流れ、聴く者を誘う。だが、古典調律を介したソロ・ピアノにしても曲ごとに興味深い編成を取るアンサンブルにしても、それらは旧来のジャズのあり方へ疑問や、尽きぬ音楽探求が下敷きとなっていることに気づかされる。
「出来上がった時、泣きそうと思いました。自分が思い描いていたものがちゃんと形になったからです。ジャズとかクラシックとかいった垣根を超えて音楽を聴く人たちに聴いてもらえればうれしいです」
『Embryo』を聴いていて納得させられるのは、ジャズの意味がどんどん広がっているという事実である。ジャズたる衝動や、発展の〈窓〉の持ち方はいかようにでも。ジャズは本当に動いており、今いろんな顔を見せるようになったという感慨も本作は引き出すだろう。
「海外の動きに追従していないものだとも思います。アメリカやヨーロッパの音楽を真似しても二番煎じになってしまう。自分を肯定するという意味で、自分にしかできない音楽が作れたんじゃないかと思います」
『Embryo』は外に向けての、今の日本人のもう一つのジャズという提案になっている。そして、それこそは本作を送り出す福盛進也の〈nagalu〉レーベルの掲げる指針の一つでもあるのは言うまでもない。