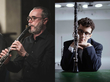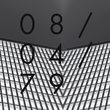数学的的な発想で書かれた美しい曲
――では、肝心の選曲についてお伺いさせてください。アルヴォ・ペルト、アンディ・アキホ、ジョン・アダムス、ジョン・ササス、エリオット・コール、ルドヴィコ・エイナウディ、そして言わずと知れたスティーヴ・ライヒといった作曲家の作品が選ばれています。どのような構想でプログラムを組まれたのでしょうか?
三村「このジャンルは新しい曲もどんどん作曲されていますが、今回は第1回目ということで原点のような作品を紹介したいという思いがありました。
ペルトやジョン・アダムスは、現在のムーブメントの火種になっている作曲家ですね。アキホとエリオット・コールに関しては、バング・オン・ア・キャン※からの流れから選びました。彼らは、ニコ・ミューリーなどとも関係が深いですし、私もNYで仕事をさせていただいたことがあるんです。ササスはニュージーランドの作曲家で、彼も90年代からこのジャンルの起点になるような作品をずっと書いています。最近はエレクトロニクスを使った音楽も作っていますね」

――この選曲について、林さんはいかがですか?
林「僕は奈々恵さんほど詳しくありませんが、もちろんアルヴォ・ペルトなどには親しんでいました。作品を初めて聴いたときに、〈なんて美しいんだ〉と感動した作曲家ですね。たとえば、彼の“鏡の中の鏡(Spiegel Im Spiegel)”は僕も演奏したことがありますが、長三和音をこんなに美しく響かせられるんだと一音一音へのこだわりを感じてジーンときて、鳥肌が立ちました。
プログラムには聴いたことがなかった曲もありますが、自分が知らない間に取り入れていた技法が使われているものもあるんです。なので、どれも僕のなかにすっと入ってくる音楽で、演奏もすごく自然にできそうだなと思っています。たとえば、大学生の頃にフィリップ・グラスの譜面からヒントを得て、ピアノの同じ音域を右手と左手で周期を変えて演奏する、ポリリズム的なアプローチの演奏をしたことがあったんですよね」
三村「今回演奏するアキホの“カラクレナイ”が、まさにそういう曲なんです。〈31〉という素数にこだわったポリメトリカル(多拍子)な構造になっていて、右手と左手で別々の拍子のフレーズを弾きながら、最小公倍数で1サイクルする仕組みになっています。
“カラクレナイ”や“21”については、私の20周年公演のプログラムノートに詳しい解説を書いたことがあります」
林「なるほど。数学的な発想は、僕もよく作曲に作っています」
三村「ええ。林さんの曲に近いんですよね。なので、ぴったりだと思います」
林「クラシックや現代音楽の第一人者の方々と一緒にステージに上がるのは緊張しますが、普段自分がやっているアプローチでできそうな気がして、緊張が解けました(笑)」
――お話を伺っていると、林さんこそが適任だと感じます。
三村「林さんしかいないですね。ロマン派などのクラシックを主体にされていて、機能和声やホモフォニックな音楽が専門の方ですと、こういう数学的・幾何学的なアプローチやポリフォニック・ポリリズムの音楽は演奏しづらいかもしれません。なので、林さんの存在は本当に心強いです」

〈唐紅〉を奏でるアキホ、現代人に必要な美しい癒しの響きを取り戻したペルト
――いまお話に出たアキホの“カラクレナイ”という曲は、日本人としてはタイトルが気になりますね。どういう作品なのでしょうか?
三村「アキホは、アメリカ生まれの日系二世の作曲家です。(アレクサンドル・)スクリャービンのように共感覚の持ち主で、ある音を聴くと色が同時に見える方なんです。
この“カラクレナイ”に関しては、〈唐紅〉という色が見えるそうなんですね。唐紅って日本人にもあまりなじみのない色で、私も知らなかったんですけれど、ダークな濃い赤色のことです。林さんも、〈あいうえお〉の曲を作る〈五十音シリーズ〉を作曲されているじゃないですか。同じように、アキホは色ごとに作曲をしているんです。
アキホはバング・オン・ア・キャンに参加していて、デヴィッド・ラングなどから影響を受けて、プリンストン大学の博士課程で学びました。エリオット・コールもそうです。まさに、現在のアメリカのトップオブトップの作曲家ですね」

――ペルトに関してはいかがですか? ペルトも今回のプログラムで重要な作曲家なのではと感じています。
三村「ええ。ペルトはやっぱり外せません。セカンド・ヴィーニーズ・スクール(新ウィーン楽派)の作曲家たちが十二音技法によってそれまでの調整音楽を壊して無調に挑んだ流れのあと、音楽の歴史的には調性に回帰する動きがありました。ラディカルな実験的カオスからまた秩序に戻るだけではなく、失われていた美学を進化させた形で取り戻してくれたのが、ペルトだと思っています。
20世紀後半のヨーロッパは、特にブーレーズなどが君臨していたので、調性音楽が軽んじられていた向きもありました。そんななかで調性音楽に自信を持たせてくれたのが、ペルトの登場だったと思うんです。彼の音楽には、現代の人々に必要とされている美しい癒しの響きがあると思います」
――現代音楽における調性音楽の魅力とは、どんなものでしょうか?
三村「たとえば、十二音技法の譜面は、音程や各セグメントをアナライズすると、本当におもしろいんです。でも、アナライズしているときが、一番おもしろいのかもしれません(笑)」
――(笑)。
三村「譜面なしで聴くと、〈なんなんだろう、これは?〉となってしまうんですね。でも、調性音楽は、シンプルに聴いて楽しむことができる音楽です」