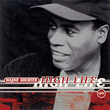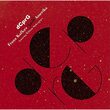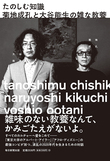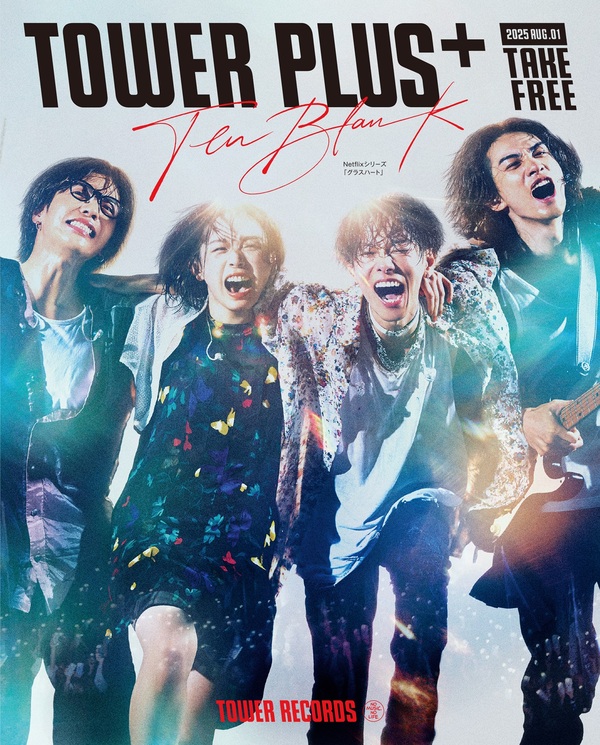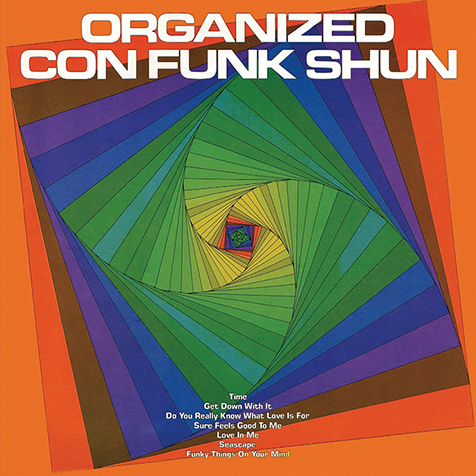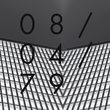菊地「あなたは我々が知るかぎり、アート・ブレイキー、マイルス・デイヴィス、ジョー・ザヴィヌル、そしてウェイン・ショーターという、偉大なバンドリーダーを4人ご存知だと思いますが、バンドを維持し、音楽をクリエイトし、それをリスナーに届けるという活動の上で、この4人のバンドリーダーには、それぞれどういった特徴があるでしょうか?」
ウェイン「4人とも共通して、何が見過ごされ、無視され、片隅に追いやられていたかへの意識を持っていた。つまりアートのいろいろな側面において、社会学的なことも心理的なことも含め、人間がおかれた状況、体験といった人間の現状に満足していなかった。しかもその全盛期にだ。例を挙げよう。ジョー・ザヴィヌルは13歳の時、オーストリアで映画を見て以来〈レナ・ホーンみたいな女をみつけるんだ!〉と心に決めて、アメリカに来たんだよ。私にしたって〈ニュージャージーから抜け出さなくては!〉という思いだった。〈ニューヨークに行くぞ!〉とね。満足しないってことさ。私の学生時代の友人の多くは、そういった〈どこどこへ行きたい!〉という欲求を持っていないみたいなんだ。みんな市の役人になったり、ワシントンで職員になった者もいる……でもワシントンDCはニュージャージーの延長にすぎないよ。というか、DCはアメリカ中の都市をひとつにしたような街だから、そこにいる人間は誰一人として、地元を離れていないんだよ、心は。neighborhood mentalityというのかな、みんな〈おらがふるさと〉的意識をそのまま持ちこんできている。ある種、隔離されている街なんだ。ハンフリー・ボガートは憧れだった。ハンフリー・ボガートみたいに言いたいことをはっきり言える勇気が欲しいと。マイルスもファンだったんだ。こう言われたことがあるよ。〈聞いたか、あいつの今の台詞を? ああいう風に吹いてくれ!〉」
菊地「ところで、サックスは最近どのくらい吹いていますか?」
ウェイン「まったく吹いてないな、家では。フロリダのコンドミニアムの27階に住んでいるんでね。法律では朝の10時から夜10時まで練習してもいいことになっているが、眼下ではプールで人が泳いでいるし、海があるし……そんな中でサックスを練習してる奴なんて誰もいないよ。聴こえるのはキューバから聴こえてくるコンガの音色だけだ。毎日、パーティしているよ、あそこじゃ! でもメンタルな練習はしているよ。同時に二つの違うことをするという練習だ」
菊地「これを最後の質問とさせてください。私はこの国の多くの国民と同じく、祖霊崇拝による仏教と神道の混合体の、漫然とした信者であり、熱心な特定宗教は持ちません。なので、話が理解できるかどうかわからないのですが、仏教があなたの音楽にもたらしたものがあるとしたら、それは何でしょうか?」
ウェイン「仏教は、アメリカでの教育カリキュラムの中では触れられることのない、多くのことを教えてくれた。小学校の歴史の授業に始まり、高校、大学に至るまで――今でこそ各大学で、アフリカに関する研究はさかんだが――東洋に関する研究はほとんどされていない。でも私は日本、中国、インド、東南アジアの歴史を知れば知るほど、いろいろなことかが見えてきた。たとえば、演繹(えんえき=deductionは一般的、普遥的な命題から個別的な判断を引き出す推理。帰納=inductionはその逆で、個別な事象から普還的な命題を引き出す推理法)的考え方と帰納的考え方もその一つだ。チャーリー・チャン(チャイニーズ・アメリカンの探偵)の映画を知っているか? 彼には息子がいて、チャーリー・チャンが殺人を犯した犯人を見事に探し出すと、息子がたずねるんだ。〈どうやってわかったんだい、父さん?〉するとチャーリーが言うんだ。〈簡単な演繹法だよ。〉そうやっていつもストーリーが終わる、という具合だった。アメリカ人である僕らは〈ああ、そうか〉としか思わなかった。ところが仏教の集まりなどに参加するようになり、演繹的考え、帰納的考え、という話をしていた。まだ8歳の少年だった頃、私は106 South Streetに住んでいた。その当時の私にとってはそれが世界のすべてだった。いまだにその考えのまま、生きている大人は世の中に大勢いる。だからこそ、戦争も起きるんだ。私にとって、仏教は別に宗教とか哲学ということではない。だって考えてみれば、人生そのものが宗教のようなものだ。人が人であること自体が、いわば宗教なのだからね。いろんなことを自分に問いかけさせてくれるんだ。鏡を見て、私は私自身にたずねる。〈お前の本当の名前はなんていうんだ?〉〈ホモサピエンス〉でもない、〈男性〉でもない、〈ウェイン〉でもない。本当の名前は何だ? 俺のミッションは何だ?! NYUである授業を受けたことがある。最後の期末テストで私にAをくれた教授が、ある時、私のところへやってきて、こう言ったんだ。〈おまえ、哲学を専攻したらどうだ?〉とね。自分の中に、その教授の言葉がずっと残っていたのかもしれないね。今、私がとても心待ちにしていること! それは『ダヴィンチ・コード』の公開だ! 日本でも公開されたか? もうひとつ。よく人から哲学や仏教を信仰していることが、音楽と関係しているか?とたずねられるが、それはこういうことだ。私の人生、生活におけるあらゆること。たとえば、妻と買い物に行くことも含めて。すべては進んでいる。動き、成長し、始まる。何かが見えるようになる、考えても見なかったことが解るようになる。それらがすべて一つになって動くと、何も起こっていないみたいに思えるんだ。自分は同じ人間として、同じ場所に立っているみたいに。だから一つだけが飛び出してしまってはよくない。音楽だけが自分を越えて先に行ってしまっても、人間としての善良な性質が成長しても、音楽が成長してないようでは困るし、繊細さを忘れてしまってはならないし……すべてがひとつとなって動く時、まるで動いていないかのような錯覚に陥る。飛行機が進んでいないみたいに感じるのと一緒で。そういうときに僕はわかるんだ。golden meanに自分は乗っていると。永遠に向かって、golden meanの旅に出ていると。生きている理由は永遠の冒険をするためだと思うよ。〈永遠〉ということが解れば、銀行強盗をする人間も殺人を犯す人間もいなくなるよ。一度しかない、永遠に続く人生においてね」
菊地「ありがとうございました」
取材協力:ユニバーサルミュージック
2005年7月25日 ヒルトン東京にて
ウェイン・ショーター(Wayne Shorter)
1933年8月25日生まれ、米・ニュージャージー州ニューアーク出身のサックス奏者/作曲家。ニューヨーク大学卒業後、59年にアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズに参加し、初リーダー作を発表。60年代はブルーノートから作品を発表しながら、マイルス・デイヴィスの右腕として活躍。70年にウェザー・リポートを結成し、フュージョンブームを牽引。80歳以降も来日公演を開催するなど、圧倒的な人気を博す2023年3月2日にロサンゼルスの病院で死去。89歳没。
菊地成孔(Naruyoshi Kikuchi)
音楽家/文筆家/音楽講師 ジャズメンとして活動/思想の軸足をジャズミュージックに置きながらも、ジャンル横断的な音楽/著述活動を旺盛に展開し、ラジオ/テレビ番組でのナビゲーター、選曲家、批評家、ファッションブランドとのコラボレーター、映画/テレビの音楽監督、プロデューサー、パーティーオーガナイザー等々としても評価が高い。5月26日(金)公開、「岸辺露伴ルーヴルへ行く」の音楽を自らの生徒と共に立ち上げた「新音楽制作工房」と共に担当。