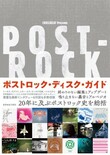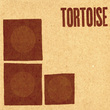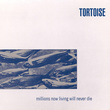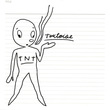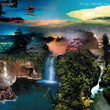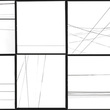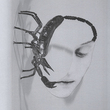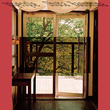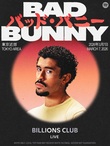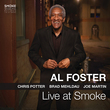既存のフォーマットを嫌い、ニュー・タイプのインストを鳴らそうと立ち上がったシカゴの革命家が世間に受け入れられるまで、そう多くの時間は必要なかった。静と動、過去と未来、陰と陽、調和と軋轢、繊細さと大胆さ、直線と曲線、喜びと悲しみ――相反するマテリアルをミックスし、〈ロックのその先〉を見せてくれたトータス。アルバム・デビューから20年強が過ぎてもなお、5人の実験精神は萎えることを知らない。音楽の新たな可能性を模索する旅はまだ始まったばかりだ……

Wikipediaによると〈ポスト・ロック〉という用語の起源は、94年にUKの音楽評論家であるサイモン・レイノルズが書いた、バーク・サイコシス『Hex』のレヴューにあるらしい。レイノルズはポスト・ロックを〈リフやコードよりも音色や響きに重きを置き、人間の演奏とデジタル機器のサウンドとの境界にある音楽〉と定義した。同じ年、グランジのアイコン、カート・コバーンが死去。90年代のミュージック・シーンを席巻したUSオルタナ・ムーヴメントの流れは変化の時を迎える。そんな年にひっそりとリリースされたのが、トータスのファースト・アルバム『Tortoise』だった。
シカゴから起こった新しい波
振り返ると、90sオルタナ・ブームの爆発を準備したのは、80年代を通じてハードコア・パンクのコミュニティーが築き上げた、ローカルなインディー・シーンのネットワークだった。地方のバンドが繋がり、情報を交換し、ムーヴメントを生み出していったのだ。トータスはそういった環境から生まれたグループであり、メンバーのほとんどがハードコア・パンクの洗礼を受けている。そもそもの始まりは、シカゴで活動していたイレヴンス・ドリーム・デイのダグラス・マッカム(ベース)が、新バンドを組もうと画策し、周辺のミュージシャンに声をかけたこと。彼の頭のなかにあったのは新しいタイプのインスト・ユニットで、メンバーにエンジニアがいることだった。
こうして90年にトータスは結成される。最初期の顔ぶれは流動的であり、『Tortoise』リリース時のラインナップは、マッカム、ジョン・ヘーンドン(ドラムス)、ジョン・マッケンタイア(ドラムス/シンセ)、ダン・ビットニー(ドラムス)、バンディK・ブラウン(ギター)といった面々。そのうち、ブラウンとマッケンタイアはケンタッキーのルイヴィルを拠点とするバストロの一員だった。距離が近いことからルイヴィルとシカゴのインディー・バンドは盛んに交流していたようだ。ドラマーが3人いるというトータスの変わった編成は、〈普通のロックをやるつもりはない〉という意志の表れ。全曲インストでギターとベースがメロディーらしきものを奏で、さまざまな打楽器がサウンドを肉付けする。なかでもヴィブラフォンの響きが新鮮で、彼らはリフやメロディーを立たせるのではなく、5人のプレイヤーが織り成すサウンドスケープを塊で聴かせていくバンドとしてスタートを切る。
そんなトータスが注目を集めるきっかけになったのは、『Tortoise』のリミックス・アルバム『Rhythms, Resolutions & Clusters』(95年)。当時、インディーのロック・バンドがリミックス盤を出すことはまだ珍しかった時代だ。ここにはマッケンタイアのほか、トータスやシー・アンド・ケイクを支えたエンジニアのケイシー・ライス、ブラウンも名を連ねるガスター・デル・ソルで頭角を現していたジム・オルーク、そしてスティーヴ・アルビニが参加。シカゴ~ルイヴィル・シーンのキーパーソンを投入し、地元愛をアピールしてみせた。そして、セカンド・アルバム『Millions Now Living Will Never Die』(96年)でバンドは界隈の最前線に浮上する。
同作はマッケンタイアが立ち上げたソーマ・スタジオで録音。プロデュースやミキシングを担当したのはもちろんマッケンタイア本人で、電子音楽や現代音楽を大学で学び、機材にも精通していた彼の音響センスは、このアルバム以降、サウンドの鍵となっていった。また、前作の後に脱退したブラウンに変わって、ここから元スリントでマルチ・プレイヤーのデヴィッド・パホがメンバー入り。20分間にも及ぶ冒頭曲に象徴される通り、クラウトロックやジャズ、テクノ、ダブなど多彩なフレイヴァーを混ぜながら、ポスト・プロダクションで楽曲全体を加工するというスタイルが出来上がる。こうした実験的なアプローチこそ、オルタナ・ロックの重要な要素であり、世間で〈オルタナ〉のイメージが消費され、カート・コバーンが殉教者のように倒れた後、トータスはしっかりとその精神を受け継ぎ、発展させていったのだ。それから2年後、3作目『TNT』(98年)で彼らは早くもひとつの頂点へ達することに。