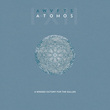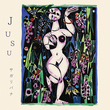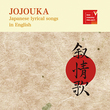自分が聴きたい音楽をだんだん作れるようになってきた
ところで、本人に言われるまで気が付かなかったのだが、僕は10数年前にも林正樹と交差していたのだった。2001年に僕のレーベルであるMemorylabが『Sea Of Memory』というコンピレーション・アルバムをリリースした。林はそこに収録されたSŪというバンドのピアニストだったのだ。バンド・リーダーだったドラマーの佐藤大輔と親しくしていた僕は、エンジニアとして曲のミックスまで手掛けていたのだが、インタヴューの席で林に言われるまで、それも完全に忘失していた。そのSŪの“7C”という曲を改めて聴き返してみると、この頃から林とその仲間たちは世界のどこにもないリズムを志向していたようにも感じられる。
「健太郎さんにお世話になったSŪというバンド(の名前)は、数字の〈数〉から来ていて、変拍子なんだけど踊れる音楽を生演奏で作ろうというコンセプトで始めたバンドだったんです。そのバンドといまの活動がどう関連しているか……僕もいろいろと通ってきたので、急にはここに辿り着かないんですけけれど、でも共通している部分はあるのかもしれないですね。僕は他では先輩ミュージシャンとやる活動が多かったんですが、SŪは数少ない同世代のメンバーでやっているバンドでした」
――林さんがいまソロでやっている音楽も、他のところで一ミュージシャンとして参加している音楽とは切れているところがあるんでしょうか? いろんな交流が反映されているというよりは。
「そうですね、こういう音楽をあまり他の人とはやっていないので。いまもいろんなアーティストと日々、一緒に音楽をやらせてもらっていますが、そこからどういうふうに影響を受けているのかは自分でもわからないんですよ。ただ、自分が思うことをそのままやっていいという自信がここ数年出てきました。最近の話で言うと、11月5日からの渡辺貞夫さんのツアーに参加したんですけども、貞夫さんと一緒に音楽をやれるとは夢にも思っていませんでしたから。83歳になったいまでも、常に前へ進んでいる本当に素晴らしい方です。去年の2月に初めて共演した時、〈好きなように弾いてくれ〉と言ってもらって、素直な僕は遠慮せず自分がやりたいアプローチで演奏したところ(笑)、おもしろい演奏をする奴だなぁと思ってもらえたみたいで。それが近年、自信を付けた大きな出来事でもあったんです」
――なるほど、今回の『Lull』にも自信という形でそれが反映されている。
「たぶん……反映されていると思います(笑)。一見、大人しい感じの曲が集まっているかもしれないですけれど、自信を持って演奏できないと、こういう音楽ってただ流れていっちゃうと思うんです。自分のはそういう音楽じゃない、聴くたびに新しいことに気付いてもらえるような、そんな音楽になったかなと思っています」
――アンビエント的に流れていくものでもないし、ロマン主義的にメロディーでグッと来るものでもない。ジャズ的にたくさん弾くピアノでもないし、すごく言葉に困るんですけれど、この音楽がいま、林さんが自分でも聴きたいものなんですか?
「自分が聴きたい音楽をだんだんと作れるようになってきた気がします。振り返ると、かつては自分がやっている音楽なのに、本当に自分が聴きたい音楽と一致してなかった。家で自分が聴きたい音楽じゃないことを、なんでやっているんだろうと。自分のプロジェクトに関しては、自分がやりたい、自分の聴きたいものをやろうという考えにやっと変わってきました。数年前に始めた〈間を奏でる〉というバンドは特にそれを象徴している感じです」
――家で自分が聴きたい音楽って、他人の作品で言うとどんなものになりますか?
「ECM全般はすごく好きですね。夜に音楽を聴くこが多いからなのか。一番好きなのはスウェーデンのピアニスト、ボボ・ステンソン。あとはジョン・テイラーもとても好きです。残念ながら昨年亡くなってしまいましたが、2012年にトリオで日本に来たんですよ。吉祥寺STAR PINE'S CAFEとSARAVAH東京でライヴをやっていて、両方ともノーPAでした。その生音の絶妙なバランスに感激したんです。ピアニストでいうと、その2人が好きですね」
「あと、日本ではずっとフェビアン・レザ・パネさんが好きで。数か月前に大塚のライヴハウスで2台ピアノで共演させてもらったんですけど、やっぱりすごい世界観を持っている人だなと。パネさんも基本ピアニッシモで音楽を考えていると思うんですけど、そのなかに入れ込んでくる強力な説得力が半端じゃないです。日本で活動している人のなかでは、ずっと惹かれ続けている人ですね」
――ピアニスト以外では?
「アルヴォ・ペルトの音楽が好きですね。こんなシンプルなことをやって、こんな深い感動を与えてくれる音楽があったんだ、みたいな。ドミソの響きがこんなに美しいんだっていうのは、ペルトを聴いて感じましたね」
――ピアノ以外の楽器から演奏のインスピレーションを受けることはありますか?
「楽器全般が好きで、最近は特にドラムですね。自分でも趣味でドラムをやっているんですけど、YouTubeで検索するのもドラムの人ばっかり(笑)。たぶんピアノをパーンと(ロング・トーンで)弾く時も、自分のなかではリズムを感じながら弾いていると思うんです。あらゆる要素を実際に音で出したいわけではなくて、それこそさっきの南米のピアニストに繋がるかもしれないですけど、演奏する人が自分のなかでいろんなリズムを感じていると、ピアノの長い音にも何か生命が吹き込まれるという気がするんですよ」
――さっき、フェビアン・レザ・パネさんの話で〈ピアニッシモで考える〉と言ってましたけれど、それが林さんにとっても重要?
「そうですね。初めてのピアノに出会うとまずは、どう弾けばピアニッシモが出せるかということはすごく考えますね。それが自分のなかで馴染むと、その日のタッチが決まる。そこはかなり意識しています。ピアニッシモでもただ小さい音というのではなくて、情緒豊かで温かい音というか。それで音楽を奏でるのはすごく難しいんですけど、何気なくポーンとメゾフォルテで弾いちゃって、それが標準音量になってしまうと、残されたダイナミックレンジがすごく狭くなってしまうんです。そこはバンド・アンサンブルになっても、なるべく……。バンドのなかでピアニッシモでやってたら埋もれちゃうだけかもしれないですけど、周りが大きいから自分もがんばるんじゃなくて、周りが大きくても、どうすればピアノの音を浮き上がらせることができるか。それを理想としているんです。強く弾いても聴こえないから、PAでピアノの音を上げて、みたいなのではなくて」
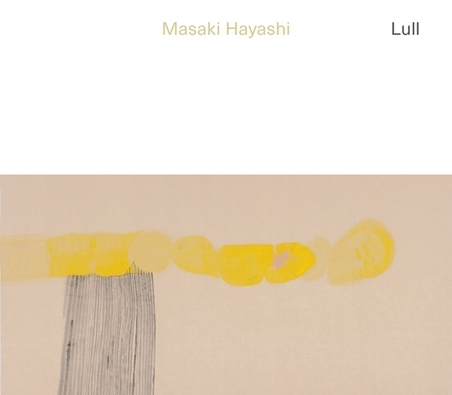
(c)WAKABAYASHI STUDIO
音楽がありきたりに機能して盛り上がってしまうことを、林は丁寧に避け続けていく。そのうえで、ピアニッシモでも豊かな表情を聴かせ、ロング・トーンでも内在するリズムを聴かせる。『Lull』はそんな瞬間を重ねていくアルバムと言っていいかもしれない。
アルバム・タイトルの『Lull』は〈凪〉という意味を持つ。あるいは、鎮める、落ち着かせる、という意味であり、そこからララバイ(Lullaby)の最初の4文字にもなっているという。これもまさしく、〈ピアニッシモで考える〉林正樹のヴィジョンと合致した言葉なのだろう。ピアニッシモこそは強い意志を必要とする。凪いだ時間のなかで林正樹はそんな表現に挑み続けている。