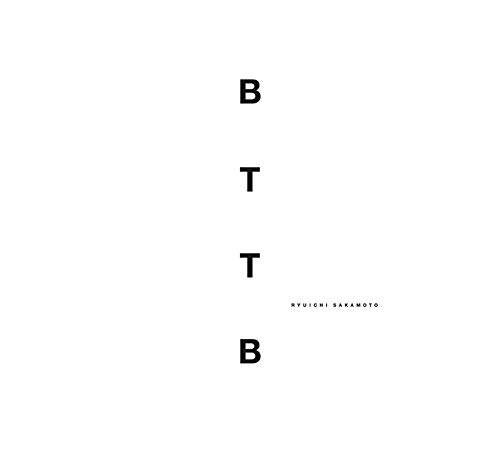BTTB for What?
記憶のなかの音はいつも新しい。1998年と2018年がどれほど近く、あるいは隔たっていようとも。
そもそも、『BTTB』の音楽家の構えは、意識的に無意識に接近を試みるよりも、無意識を余白いっぱいに溢れさせて、そのなかで自意識を溺れない程度に遊泳させる、というのに近いように思える。戦略はある時点や局面における有効性を選ぶが、それが近視的ではなく遠望を宿すのは、やはり坂本龍一がここで方法論というよりも心情的なレヴェルで、西洋音楽の歴史、とくに近代以降やバロック以前を散策するようにみつめていたからだろう。
すべてを減衰に委ねることで、音楽の時間は前へと進むが、その記憶は微細な移ろいのうちに留まる。『BTTB』の響きの連なりが、それぞれを重ね合わせて波紋のように広がっていくのは、そうして神秘的な印象を憧憬するように音楽とその記憶、同時に音楽家自身の記憶を原点にみているからだろう。そのまなざしには、ピアノを弾くことへの愛情と同じくらい、憧憬の色彩の滲みがあり、装飾を控えた意匠を好み、素直に歌い出される歌がある。
「Back To The Basic」の記号のもと、回帰すべき「B」にはBach、Brahms、またRavelやSatieに親しい造形もあれば、打楽器的なプリペアド・ピアノの反響、口琴や水音を音響処理したものや、アンビエントな残響の広がりもあって、簡潔な音像のうちにも、近作『async』までを派生させる展望がすでに響いている。旋律作家とピアノ奏者としての彼の美質も、率直かつ優美に明かされる。原点をみつめる坂本龍一の視座からして、原初的に流動性を孕み、したがってその作品もピアノ演奏もソリッドというよりはずっとリキッドな性質が濃い。
初めてのピアノ・ソロ作を謳ったアルバムが20年を経てリマスタリングされてみると、移ろいと変容のなかで坂本龍一が幻視し、あるいは夢想していた原景が、いまもって鮮やかにその揺らぎと脈動を明かすように聞こえてくる。現在が古いのか、過去が新しいのか、もともと新旧では測れない円環と曲線が、ここではひっそりと、個人的な佇まいをとって描かれている。