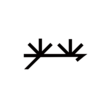新たなポップス〈tiny pop〉の胎動を伝えるオムニバス盤。惹句は〈ネット世代のDIY歌謡曲〉。監修は、提唱者でもあるアルト・サックス奏者/トラックメイカー/作曲家のhikaru yamada(hikaru yamada and the librarians)だ。詳細かつ資料性の高い本作のライナーノーツも、彼によって書かれている。
〈シーン〉〈ジャンル〉〈ムーヴメント〉……なんでもいいが、何か〈大きな〉括りを設けるには、tiny popという音楽はあまりにもささやかにすぎる。作家どうしは緩やかに繋がってはいるものの、意識的な共同性/協同性や帰属意識などは、ほぼまったくないと言っていいからだ。彼/彼女らは非意識的に、それぞれ独自の語彙でポップスを生み出し、インターネットの海に放っている。
では、〈tiny popとは何か?〉という問いにはひとまず、ネットで発表される小さな宅録ポップスだ、と答えておく。詳しくはyamadaと本盤に参加している西海マリ(mukuchi)へのインタビューを、補遺としてQJWebに掲載されている拙稿をあたってほしい。
重要なのは、〈tiny〉である=商業的なJ-Popなどと比べて小さく縮こまっていることよりも、〈pop〉としての巧みさや開かれた強度のほうにこそtiny popの核心がある、ということ。
トイ・ポップ的な意匠をガジェット系シンセサイザーの音色で置き換えたような曲を生み出すmukuchi、エレクトロニック・ダンス・ミュージックを背景に持つSNJO、ブラジル音楽からの影響が色濃いwai wai music resort、サイケデリックな日本語フォークや80年代アイドル歌謡を思わせるノスタルジアを携えたゆめであいましょう――バラバラで、優れた個性を持った4組を繫留するのは、〈pop〉であることに他ならない。
この『tiny pop – here's that tiny days』に収められた11曲のなかでも、ゆめであいましょうの“誰もが誰かに”とwai wai music resortの“Blue Fish”は、とりわけ聴く者に衝撃を与えるはず。いまにも壊れそうな美しさと繊細さとを持ち、時代から切り離されているがゆえに〈ゴーストリー〉な感覚さえ覚えるニュー・ミュージック歌謡の“誰もが誰かに”。そして、ノルデスチを意識したと作曲者のエブリデが語る、リズムの交差が陶酔的で誘惑的なアフロ・ブラジリアン調の“Blue Fish”。いずれも、まだ知られていない(はず)の才能とポテンシャルを十分に伝える、驚愕の曲だ。