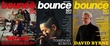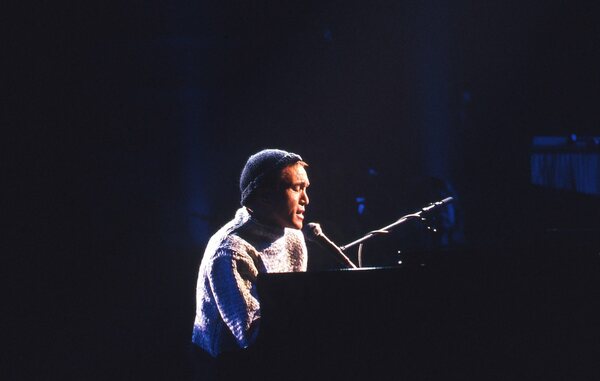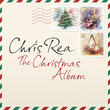Photo by Genesis Báez
エイドリアン・レンカーの鋭さ
――エイドリアン・レンカーの『songs』と『instrumentals』をお2人はどんなふうに聴きましたか?
高橋健太郎「ビッグ・シーフでは激しさのある音楽をやっているじゃないですか。そういうバンドのフロントマンがソロでフォーク的な音楽をやるとなると、音楽性や発声方法は優しいものになりがち。でも、彼女はソロでも鋭角な感性が強く出ている。
あと、アコースティック・ギターのミニマルなフレージングをかなり研究したんじゃないかなと思いました。スティーヴ・ライヒみたいな、ミニマル・ミュージックの感覚で弾いているように聴こえたりします。今回インストゥルメンタル・アルバムも出すのは、そのへんがあったんじゃないかと」

岡村詩野「健太郎さんが言うように、単なるソロ・ワークじゃなくて、バンドでは発揮されなかったギタリストとしてのプレイヤビリティーや特性が出ている。
近年、レオ・コッケが再評価されているじゃないですか。それ以前から、ジョン・フェイヒィも再評価されています。アコースティック・ギターで繊細な音を響かせる、刺繍をするかのようなプレイをするギタリストが再評価されているんです。エイドリアンのソロ作は、そういう流れとリンクしているように感じました」
――歌唱もバンドとちがって、内面の深いところを表現したヴォーカルに感じました。
高橋「僕は、パーソナルな感覚よりも、カッティングエッジでラディカルなものを感じましたね。現代、特にここ10年くらいは、フォークこそがエッジーな音楽だとする動きがあると思う。エイドリアンの音楽は静かで起伏もないんだけれど、その内奥に尖った感覚がむしろバンド以上にある。
フォーク的な音楽と一口に言っても、アメリカにはカントリーに接した音楽があるし、イギリスにはブリティッシュ・トラッドとアイリッシュ・トラッドに接したフォークがありますよね。でも、そういう伝統的なスタイルから一歩踏み出て、ロックよりもラディカルなフォークを追求する流れがあって、彼女の音楽もそういうものだと思う」
トラディショナルだけどエクスペリメンタルなサム・アミドンのフォーク
岡村「それは私も同意するところです。健太郎さんはなにがきっかけでフォークがラディカルだと思うようになったですか?」
高橋「ものすごくさかのぼっちゃうと、ボブ・ディランがエレクトリック・ギターを持って、〈ニュー・ポート・フォーク・フェスティヴァル〉で……」
岡村「そこまでさかのぼるんですか!?」
高橋「いや、このあいだザ・バンドの映画(『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』)を観たから(笑)。すごいでしょ、あのブーイング※を実際に映像で観ると? でも、ディランは演奏し続けた。あの時点で、フォークって一度置き去りにされたんですよ。つまり、ロックのほうがラディカルな未来の音楽で、フォークは古くて心優しい音楽だと。その関係は、あれ以降ずっと続いていた。
それがどこで逆転したか……。僕にとってすごく大きかったのは、サム・アミドンの存在かな。もちろんボン・イヴェールも重要だけど、彼はもともとロック的な感覚も強い。サム・アミドンは、ものすごくトラディショナルなフォーク・ミュージシャンなんだよね、バンジョーを抱えた。なのに、アイスランドへ行って電子音楽の人たちと一緒にやったり……。アコースティックだけど、姿勢はすごくエッジーですよね」
岡村「サム・アミドンは素晴らしいアーティストだと思います。日本でどうしてこんなに軽視されているかわかりません。彼はアメリカ人で、いまロンドンに住んでいますが、アメリカでの動きを視野に入れながら、折に触れてルーツを掘り下げている」
高橋「Bandcampとかをまめにチェックしていると、フォーク系の人たちって、みんなものすごく演奏が上手くて、一定のクォリティーを保った素晴らしい音楽をやっているんです。豊かな伝統の上で。でも、そこから頭一つ抜ける人って、一握りなんですよ。
サム・アミドンは〈これ、なんなんだろう?〉っていう抜きん出たものを最初から持っていた。トラディショナルな音楽を追求しながら、一方でものすごくエクスペリメンタル。そういう人たちが次々に出てきたのは、2010年代からじゃないかな」
岡村「ジム・オルークもそうじゃないですか。彼はジョン・フェイヒィとかロイ・ハーパーとか、フォークのアウトサイドにいた人たちを早い段階から再評価していました」
高橋「でもジムってさ、フォーク・ミュージシャンじゃなくない? サム・アミドンのベースには、〈バンジョーを弾いて歌う〉ということがあるから。
フォーク・ミュージシャンにはフォーク・ミュージシャンとしてのなにかがあるって僕は思うんだよね。一人で人前に出て行って生で弾いて歌っても、光るなにかを感じられるのがフォーク・ミュージシャン、っていう感じがする。音響派の流れでフォークをやるんじゃなくて、もうちょっとゴロっとした〈アコースティックなのに、なんだろう、これ?〉っていう音楽のほうが、いまの感覚ではおもしろいと思う」
アメリカとイギリスの交流が生んだフォークの革命
岡村「サム・アミドンも、最初はメイン楽器がバンジョーじゃなかったですよね。
90年代は、アメリカ音楽がルーツに回帰するきっかけとして、ハリー・スミスの『Anthology Of American Folk Music』のCD化(97年)がありました。それから、デヴェンドラ・バンハートとか、いわゆるフリー・フォークの人たちが出てきた、という流れがあります。サム・アミドンも昨年、ハリー・スミスにトリビュートした『Fatal Flower Garden EP (A Tribute To Harry Smith)』を発表しています」
高橋「う〜ん。ハリー・スミスってコレクターだよね。ミュージシャンに会いに行って録音するアラン・ローマックスのような人ではない。彼のコレクションは、1927年より後の音源しかないんです。1927年より後の音楽だけ聴いていたって、おもしろくないよ(笑)。〈ルーツ〉なんて言っても、そこで止まっちゃうんじゃないかな。レコードの歴史は、それ以前に少なくとも40年はあるから。
ハリー・スミスのコンピレーションがカルト化、古典化したせいで、彼がコレクトしたレコードを作った人たちがいるのに、その存在が忘れられがちなのはバランスが悪いなって思う」
岡村「そんなことはないと思いますよ。サム・アミドン以降では、誰が重要ですか?」
高橋「彼の交友関係を見るだけでも、すごくおもしろいよね」
岡村「ブレイク・ミルズとか?」
高橋「彼やベス・オートンもそうだけど、僕のなかですごく大きいのはジェスカ・フープ。彼女はカリフォルニア出身だけど、今はマンチェスターに住んでいる。サム・アミドンもそうだけど、ひとつ重要なのはイギリスを目指したことですよ。
これまた64年くらいにまでさかのぼると、アメリカン・フォークの重要なミュージシャンってみんなロンドンの文化の洗礼を受けて、アメリカに帰ってきて、すごい曲を書いてヒットさせている。ボブ・ディランも、ポール・サイモンも、ジェイムズ・テイラーも、みんなそう。その一方で、アメリカ人のジョー・ボイドがイギリスでインクレディブル・ストリング・バンドとかフェアポート・コンヴェンションとかを見つけて、ブリティッシュ・フォークの一大帝国を築いた。当時は英米間の交流がすごくあって、それがアメリカのカントリー・フォークやイギリスのトラッド・フォークから一歩踏み出したプログレッシヴなものを作り出していたんだと思う。
だけど、その後は〈アメリカはカントリー・フォーク〜アメリカーナ〉〈イギリスはブリティッシュ・フォーク〉みたいに固まっていっちゃった。でも、最近はまた、アメリカとイギリスがすごくクロスしていると思う」