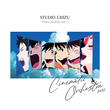傑作ドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」の音楽は、オペラのように「まめ夫」の音楽を支える屋台骨Ensemble FOVEの今を聴く〈ZINGARO!!!〉
ドラマ「東京ラブストーリー」から30年。日本を代表する脚本家として常に第一線で活躍してきた坂元裕二が、2021年に新境地を拓いてみせた「大豆田とわ子と三人の元夫」はテレビドラマ史に輝く、紛うことなき傑作となった。コメディを基調とした難解さとは無縁の物語でありながら、その笑いが小手先の面白みだけということは一切無い。ちょっとした行動や小噺のすべてが、キャラクター造形や物語の本質を描いた演出になっているから末恐ろしいのだ。ゲラゲラ大笑いしながらドラマを観ていると、無意識のうちに心をアイスピックで刺されまくっている……それが「大豆田とわ子と三人の元夫」(略称「まめ夫」)という作品である。
核となるスタッフ陣は2017年に話題を呼んだドラマ「カルテット」の面々を継承しているが、「まめ夫」という作品を次なる領域に引き上げたキーマンが、本作で新しく加わった作曲家・坂東祐大である。今年30歳になったばかりの若手でありながら、既にクラシック・現代音楽の領域で高い評価を獲得。更に米津玄師や宇多田ヒカルの楽曲での先鋭的なアレンジが識者を中心に大きな注目を集めている存在だ。
ある意味では坂元の脚本と同様、坂東の音楽もまた、表向きではポップで親しみやすいのに、実は裏でとんでもなく尖った表現をしていたりと、「まめ夫」という作品の本質を体現している。ドラマの放映が始まる前、3月上旬の時点で坂東は本作について、こう述べていた。

坂東祐大 『Towako’s Diary - from “大豆田とわ子と三人の元夫”』 コロムビア(2021)
「今回は本当に自由にやらせていただいています。台本の初稿からいただいて、ずっと並走しているんですけど、なるべく(場面々々にあわせて)当て書きをしたいのでスケジュールはギリギリですね。今回、音楽でやろうとしていることはオペラに結構近くて、ライトモティーフ的なことはそんなに使ってないですけど、基本は会話劇なので、そこに〈ゆるやかにナンバーを重ねる〉イメージといいますか……」
ここで坂東がナンバーと言っているのは、ミュージカルの〈ナンバー〉と同じ意味である。もともとは場面ごとに番号が振られたオペラ(ナンバーオペラ)に由来する言葉で、音楽の連続性よりも楽曲ごとの個性が際立つ傾向がある。
その最たる例が、2番目の元夫・佐藤鹿太郎とのなれそめが描かれる第3話で流れる“鹿太郎のワルツ”という楽曲だ。〈回想編〉では上野耕平のサクソフォンが、〈オフィス編〉では鈴木舞のヴァイオリンがフィーチャーされるのだが、つまり彼らは劇中人物の代わりに〈ナンバー(≒アリア)〉を歌っているというわけなのだ(更に深読みすれば、回想編からオフィス編への変化は、ラヴェルの“マ・メール・ロワ”における〈美女と野獣〉のワルツの展開をなぞっているかのようでもある!)。
「挿入歌ではなくて劇伴に歌を取り入れて心情描写をしたりもしています(※マイカ・ルブテの歌うシャンソン風の楽曲)。また作曲や録音現場のディレクションだけじゃなく、どの場面にどの曲をあてるのかという選曲までしているんですよ。曲が足りなかったらその場で書き足したりもしているので毎回凄く大変なんですけれど、脚本読んでるだけでも泣けるぐらい素晴らしい作品に関われて本当に光栄に思っています。自分自身も少しでもとわ子と三人の元夫のいる世界に浸っていたい、そんな気持ちです」
映画と異なり、テレビドラマでは通常、どこにどの音楽を当てるのかを最終的に判断するのは作曲家ではない。ところが本作では、その部分も坂東に任されているのだ(整音にまで立ち会っているという!)。ドラマの最終回は6月15日放送だったが、ツイートで確認できる範囲でも6月6日の早朝にレコーディングをしていたりと、本当にギリギリまでドラマにあわせた音楽づくりが続けられていたことが分かる。
こうしたクリエイティヴィティを支えているのが、豪華な演奏陣とのコラボレーションだ。グレッチェン・パーラト、LEO今井、マイカ・ルブテ、BIGYUKI、Banksia Trio(須川崇志、林正樹、石若駿)、鈴木大介……とジャンルの垣根など最初から存在しないかのように、多彩なミュージシャンを起用したことに目が惹かれる。しかし、それ以上に重要だと思われるのが、現在性という視点からのブラッシュアップに対応できるメンバーばかりだというところ。平易に言い換えれば、どれひとつとして〈ありがちなそれっぽい曲〉がないのだ。特定のジャンルと強く結びついた音楽(前述した“鹿太郎のワルツ”や“嘘とタンゴ”など)であっても、リズムや音色といった細部に注目すると、どの曲にも現代的な感覚が宿っているのは坂東のこだわりだろうか。