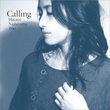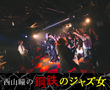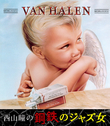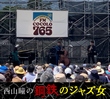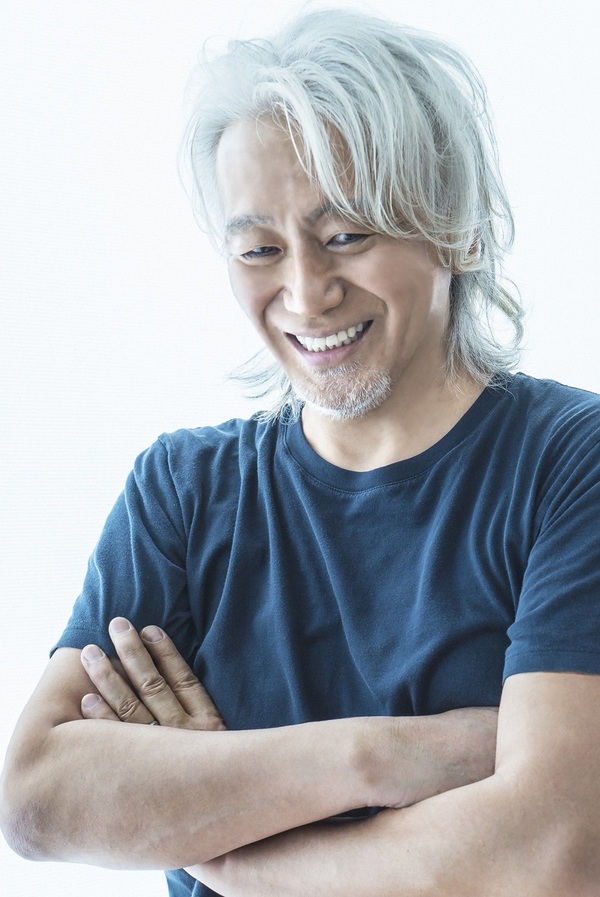――ビリー・シーンが好きになった頃って、周りはどんな感じだった?
「身の回りの社会人の人とか年上の人とかは、モータウンが好きだって人が結構いたんですけど、そっちは何が良いのかわからなかったんです。高校3年の時、同級生で音楽に詳しい人がまた別にいて、彼がマーカス・ミラーを教えてくれたんですよ。当時ちょうど『Live & More』(97年)っていうライブ盤が出て、それを貸してくれた。それをいっぱい聴いたんですけど、僕はビリー・シーンの方がカッコいいなって思って、マーカスのことは何とも思わなかった。で、その友達に〈マーカスを聴いて分らないんだったら、ジャコを聴いてみれば〉って言われて」
――来た!
「そんな時に、ジョン・ミュング(ベース)とビリー・シーンが表紙の中古の〈Player〉誌を買ったら、レジェンドを紹介するページがあって、そこに載ってたのが偶然ジャコだったんですよ。〈ああ、これがみんなの言ってる人か〉って思って見てみたら、見た目が格好いいじゃないですか。それで、カッコいいから聴いてみようかなって思って。
ジャコは87年に亡くなってるんですけど、当時『Birthday Concert』(81年録音・95年リリース)ってアルバムが発売されてて、それも買ったんですよ。僕のジャコの思い出の中で一番ドキドキしたのは、このアルバムのジャケットなんです。どんな音楽なんだろう?と思って聴いてみたら……やっぱり何とも思わなかったんですよね」
――ええっ!? そうなの?
「その頃、『ジャコ・パストリアスの肖像』(ビル・ミルコウスキーが記した書籍)を読んで、みんなジャコの演奏する“Donna Lee”を聴いて〈雷に打たれたような衝撃があった〉とか〈何の楽器か分からなかった〉とか言ってるから、それも聴いたんですけど、僕にはその衝撃が訪れなかった。何回聴いても分からない。俺、才能ないのかなって。ショックだったんですよ。なんかポコポコ言ってて、コンガとエレベで、ポコポコ、ドゥーンってやってて。よく分かんないな、ビリー・シーンの方がずっといいやって思ってたんです」
――ビリー・シーンって色んなバンドやってたけど、ナイアシンみたいに難解な方面のビリー・シーンも聴いてた?
「ナイアシンはブルーノート公演も観に行ったけど、よく分からなかったですね。ビリー・シーンはやっぱりポール・ギルバートとスティーヴ・ヴァイのどちらかとユニゾンして、パキパキにタッピングとかしてる方がカッコいいなって」
――その頃バンドはやっていた? 演奏することが楽しいって感覚は?
「友達と楽しんではいたし、たまにライブはあったけど、ギターの友人の家で適当に“Johnny B. Goode”とか適当にセッションしている方が楽しかったですね。洋楽を聴いていると、その頃までのハードロックの人たちって紫色やショッキングピンクのパンツに、腰巻とかしてたじゃないですか。当時、あれがカッコ悪いとか、ハードロックがダサいとか言われてて、ブルーハーツをやる人とかハイスタを聴く人とかはいたし、むしろ周りはそっちの方が多かったですよね。うちの高校は当時、ハイスタを好きな人たちが校歌をアレンジしてパンク風に歌うのが流行ってました。それが超カッコよくて、僕らみたいに〈BURRN!〉とか読んでるのは暗いな!みたいな感じ。ハードロックとかメタル好きな人って、パリピ系ではなくて、物語的な文系って感じでしたね。
僕も〈ハードロックはアメリカじゃないと〉とか思ってたし、今考えるとちょっと嫌な感じだったかも。でも、日本のLOUDNESSも聴いてたし、他にもドイツのハロウィンとかも含めて、広く洋楽のロックを聴いていたけど、やっぱりビリー・シーンにハマったんですよね」
――バンドじゃなくて、アーティスト個人にハマるんだね。
「そうなんですよ。音楽史の中でどういう立ち位置か、とかそういうことより先に、個人や奏法が気になる。あと、グッズを集めるのも好きで、90年代に出た『Ultimate BILLY SHEEHAN(アルティメイト・ビリー・シーン)』っていう本は、生い立ちとか昔の写真、持ってるベースとか、譜面の全てにタブ譜が大量に載っていて、それを見るのがとても楽しかったですね。
僕にとって大事なのが、ロックとかベースを始めるまで、そこまでオタク的にハマったことは一つもなかったんです。それまで何にもハマったことがなかったから、普通すぎて嫌だったんですよ。そして大学に入っていよいよジャコにハマるんですけど、〈俺、何かに夢中になれるんだ〉みたいなのはすごく嬉しかったです」
――ジャコに辿り着くところまではどんな流れで?
「ミスター・ビッグのツアーで初めて日本武道館に行って、感動的だったんですけど、〈Player〉誌で見たジャコのことが気になっていたんです。ポコポコ鳴ってるのが謎で、引っかかっていました。で、大学に入ったら、ロック研に入ろうと思っていたんですけど、その高校の友達のギタリストのお母さんが〈ジャズ研に入ったらいいわよ。みんな上手いし、ロックみたいなこともできるし、何でもできるよ〉って言ったんですね。
だから、入学してすぐジャズ研に行ったんですが、その時に〈誰か好きなベーシストいるんですか?〉って訊かれて、調子こいて、何も知らないし好きでもないのに〈ジャコっすね〉って言っちゃったんです。全然知らないのに、どうやらみんなが衝撃を受けたらしいだから、ジャコとか言っとけばいいのかなと思って。
〈じゃあ何かやろうよ〉って言われて“The Chiken”(ジャコ・パストリアスの愛奏曲)とかをやることになっちゃって、それでコピーしようとしたら、全然弾けないわけですよ。ワケがわからないし、難しいし。で、その難しさにハマったんです。弾けないじゃん!って思って。ビリー・シーンも弾けなかったんですけど、あちらは気合いで弾くみたいなところあるじゃないですか。ジャコは〈ムッチャ賢い人がやる音楽じゃん、弾けないじゃん!〉みたいな。“Teen Town”(ウェザー・リポート)ってあるでしょ。何この難しい曲!?って、弾けないことで燃えた」
「他にも、ジョニ・ミッチェルの“Shadows And Light”のライブとかを観て、この人めっちゃカッコいいじゃん!って。それからジャコにハマって、今まで22~3年、ずっと変わってないっすね。
さっきも言った『Ultimate BILLY SHEEHAN』っていう本にジェフ・バーリン(ビル・ブルーフォードやアラン・ホールズワースとの共演でも知られるベーシスト)、ティム・ボガート(ベック・ボガート&アピスのベーシスト)、ジャコ・パストリアス、ビリー・シーン。この4人のベーシストが一緒に写った写真が載っていて、この人たちはどういう縁なんだろうなと思ってました。ジャコは1951年生まれで、スタンリー・クラーク、アルフォンソ・ジョンソン、マーク・イーガン、小原礼(いずれもベーシスト)などと同い年なんですよ。ちなみにフェンダーが初めてエレキベースを発売したのが1951年で、1951年はベースの年なんです。
1953年生まれのビリー・シーンがウェザー・リポートの“Birdland”をナイアシンで演奏してたこともあり、何の繋がりでやってるんだろうと思ってたけど、〈ジャコのことは好きだ〉〈あいつはすごい〉みたいなことを言ってるインタビューがあって、そのうち徐々にジャコにハマってって感じですね。
とにかく僕にとってショックだったことは、ジャコを最初に聴いた時に感動しなかったってことなんです。みんなが涙が出たとか雷に打たれたような衝撃を受けたとか言ってるものが、ポコポコにしか聴こえなくて、よく分からなかった。ショックだったんですよ」
――音質の問題ってなかった? 私も今になったら思うけど、昔ハマらなかったものって音質の問題も相当あったと思うのよね。後に補完して聴けるようになると、めっちゃいい!って思うこともあるし。
「高校生の時にウェザー・リポート聴きました?」
――聴いてますけど、ハマらなかった。
「あれ、当時はいい音だと思ったことが一度もなかったんですよ。僕も最初CDで聴いた時は〈何か重要な楽器が入ってないんじゃない? ヤバいでしょ〉とか思ったけど、後々ジャズ喫茶でLPを聴いたら全然違うって思った。特に『Night Passage』(80年)は良いシステムのLPで聴くとジャズなんだって分かったんです」
――インプロビゼーションに興味持ったきっかけはジャコなの? それまで聴いていたビリー・シーンにはインプロ要素は結構あったの?
「大学でジャズ研に入る時のきっかけとして、セッションに参加したいから興味を持ったところがあって、ジャコきっかけというより、ジャズというものに参加している人がカッコよく見えて。
ビリー・シーンでも、バッキングはライブによって結構違うじゃんって思うことはありました。当時リッチー・コッツェン(ギター)、T.M.スティーブンス(ベース)とかも聴いていたし、あと、ジョー・サトリアーニ(ギター)とエリック・ジョンソン(ギター)。あの辺を聴いて、インスト側に寄ってったんですよね。ヴァイのアルバム『Fire Garden』(96年)にスチュアート・ハム(ベース)が入ってたことがあったでしょ。スチュアート・ハムがフュージョン系のインストをやってるアルバムも買ったりして、そっちにも興味あったんですよね。
セッションでブルースするっていうのはロックの人たちにもあることじゃないですか。97年にNHKで〈モントリオールジャズフェス〉の中継があって、レジェンズっていうセッションバンドが出てたんですよ。デヴィッド・サンボーン、ジョー・サンプル、マーカス・ミラー、スティーヴ・ガット、そこにエリック・クラプトンが入っていて」
「高校の時にクラプトンにも結構ハマってて、ヤードバーズとかクリームとかデレク・アンド・ザ・ドミノスとか時系列で聴く勉強はしてたんですが、そのレジェンズの映像で、クラプトンが金色のストラトで超渋いアドリブをしてたんですよ。
その高校のギタリストの友達のお母さんがピアノ教室をやってる人で、〈こういう人たちはね、こういうところに入ってもできるのよ〉みたいなこと言ってて」
――そのお母様、素晴らしいね。本当に音楽が好きな方だったのね。
「そのお母さんは芸大に行くような子の指導もするけど、ジャズも通っている人で、フレディ・マーキュリーの大ファンで〈クイーンの曲やりましょう!〉とか〈サンタナを聴いた方がいいよ〉とか言うんです。
その方が少し前に亡くなって、久しぶりにその頃の仲間と会ったんですけど、実はお父さんもドラマーで、ドラマーの友人に〈ドラムはレギュラーグリップがいい。レギュラーグリップだったら何でもできるから〉とか、音楽のことをいろいろ教えてくれたんですよ。その縁があって、スラップを初めて見たのもそこで観たサンタナのビデオだったし、ジャコのモントリオールでやってる82年のライブのレーザーディスクもあって、見せてもらったりしてました」
――いいご縁があったのね、出会わなかったらどうなってたか分からなかったね。
「そうなんですよ。チューバを静かに挫折して帰宅部で終わってたかもしれない。よかったですよ」