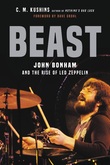世界一のモンスターバンド、フー・ファイターズ。〈FUJI ROCK FESTIVAL ’23〉のヘッドライナーを飾る彼らが、11作目のアルバム『But Here We Are』をリリースした。フー・ファイターズらしい力強さ、繊細さ、そして希望にあふれたエモーショナルな同作。とはいえそこには、悲痛な喪失の経験と覚悟もたしかに刻まれている。話題作の国内盤リリースにあわせて、音楽ライターの新谷洋子がアルバムに込められた思いと音を解説した。 *Mikiki編集部

二重の悲劇、それでも前進するしかない覚悟
フー・ファイターズの11枚目のアルバムのタイトル『But Here We Are』を日本語に置き換えるとしたら、〈俺たちはここまで来てしまった〉なのか。或いは、〈ここからどうする?〉に近いニュアンスなのだろうか。どちらにせよ、たくさんの想いが詰め込まれた〈But〉の3文字が、やたら目に強く焼き付く。それは例えば、深い悲しみと喪失感と混乱であり、まさかの展開がもたらした衝撃であり、それでも前進するしかないことを受け入れたバンドの覚悟なのかもしれない。
盟友テイラー・ホーキンスの急逝だけでなく、デイヴ・グロールの母ヴァージニアの死という二重の悲劇を受けて誕生した本作には、まさにこうした想いが交錯。パワーポップとハードロックが出会う王道のフーファイ節でアップビートにスタートするものの、全編が死の影にすっぽりと覆われている。そう、LAとロンドンで盛大に開催されたテイラーのトリビュートコンサートがパブリックな追悼だったとすると、こちらはバンドの、デイヴの、プライベートな弔いというべきか? 実際パーソネルも身内で固めており、共同プロデューサーには2017年の『Concrete And Gold』から3枚連続となるグレッグ・カースティンを起用。ゲストはデイヴの娘ヴァイオレットのみで、ドラムスは新ライブメンバーのジョシュ・フリーズではなくデイヴが自ら叩いた。
無防備で生々しい言葉と音
そのアップビートなオープニング曲“Rescued”で、完全に動転していた昨年3月のあの日の自分に想いを馳せ、以後率直極まりない表現でテイラーに、或いは母に、時に両者に同時に、切々と語り掛けているデイヴ。約30年前にバンドを始動させた時は、もうひとりの仲間の死に直接音楽で言及することはなかったが、今度は違う。無防備で生々しい言葉がとめどもなくこぼれ出ている。
それに生々しいのは言葉に限らず、音色も然りで、前作のポップエクスペリメントに対して今回は余計な音を入れずに、バンドアンサンブルを前面に押し出したメロディックなロックンロールを鳴らすことに専念。かつ、失ったものの大きさに呆然としている“Hearing Voices”ではポストパンクに転んだり、死者とのコネクションを再確認する“The Glass”はアメリカーナの匂いを漂わせていたりと、曲ごとにさりげなく取り入れたスタイルが実に多様だ。