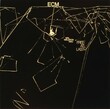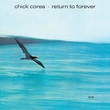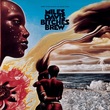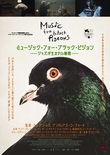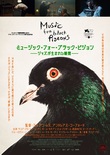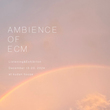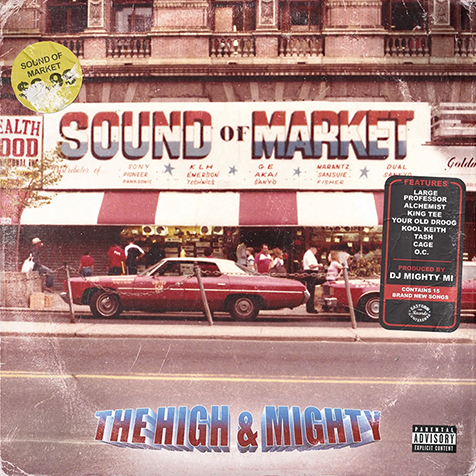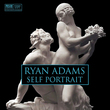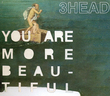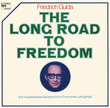©Colin Eick / ECM Records
以下の鼎談は、2008年に創立40周年を迎えたレコード会社、ECMがミュンヘンの美術館で開催した展覧会〈ECM - A Cultural Archaeology〉に際し、レーベル創立者、プロデューサーであるマンフレート・アイヒャーとレーベル・スタッフ・ライターであり、もう一人のイン・ハウス・プロデューサーであるスティーヴ・レイクを迎えて行われた鼎談の記録の全訳。この鼎談は記録され、展覧会で販売された同名の出版物に収録された。他にもECMの膨大なカタログへの考察、レーベルがレコーディングしてきた音楽の与えた影響を、サウンドトラックとして取り込んできた映画との関わりも含めて考察するさまざまなエッセイや、当時までに発売されたカタログの詳細、様々な機会に撮影されたスチールなどを掲載し、非常に大部の、百科辞典のような体裁だ。展覧会を機にこれ以外にも『Selected Signs』とタイトルされたCD 7枚組のボックスセットが制作された。このボックスに収められた音楽は、展覧会の会期中、展示場を満たした。
しかし、そもそもレコード会社の展覧会って何だ? カンヌで開催されていた〈MIDEM〉のような音楽の商品見本市、展示会の間違いなのではないか。レコードやCDは大量生産され、小売店で販売されている商品の一形式だし、店頭での展示や陳列は販売の一形式だ。どのような音楽が収録されていようと、こうしたメディアは商品で美術館の展示や鑑賞の形式方法に値するような美術作品ではないのではないか? キュレーターはバイヤーではないのでは? しかし、すでにマルセル・デュシャンが便器を「泉」と題してアート・オブジェとして発表して、このレディメイドのように展示方法自体が表現としても受け入れられてきた。時を経てクリスチャン・マークレーのようなヴァイナル・ジャケットやMVや映画を編集して作品を制作するアーティストも現れた。何でも商品化する時代では、あらゆるオブジェが鑑賞の対象となりアート化される。大量生産されるインダストリアル・デザインは、その流通方法も含めてアーティストの表現の一形式として定着した。それに今更、ではあるが、見る場所は聴く場所でもある。

レーベル発足当初からアルバムのデザインなどのアートワークに独自のセンスで取り組んできたECMの制作物は、そのサウンドだけでなく、制作現場のスチールやポスターに至るまで鑑賞の対象として十分に魅力的だ。それはブルーノートなどレコード会社の制作物についても同様だろう。しかし他と違って、ECMの制作全体のクオリティ・コントロールは現在に至るまで一貫していて、マーケットの経済原理に左右されることなく、驚異的な自律性を維持してきた。おそらくこの姿勢はキース・ジャレットやチック・コリア、パット・メセニーの成功がなくとも、変わらなかったんじゃないかと思う。だから、展覧会という機会を設け、展覧会開催当時、設立40年を迎えようとしていたレーベルの制作全体を俯瞰してみたくなるキュレーターが現れても不思議ではない。
レコード・レーベルであるECMは、映画、音楽を含むあらゆるアートの表現方法やアートの概念自体が大きな転換点を迎えていた1968年に設立された。設立者のマンフレート・アイヒャーは、コンテンポラリー・アート全般に関心を持ち、学生時代にコントラバスを学び、映画を貪るように観た。当時、コンセプチュアル・アート、ミニマル・アートやポップ・アートが産声を上げ、映画はヌーヴェル・ヴァーグの季節を迎えていた。現代音楽は、すでにクセナキスが“メタスタシス”を、ジョン・ケージとモートン・フェルドマンらが図形楽譜による作品を、カールハインツ・シュトックハウゼンやピエール・シェフェール、レジャレン・ヒラーらが電子音楽を、そして1967年には武満徹の“ノヴェンバー・ステップス”がニューヨークで初演され、作曲手法やメディアの多様化を迎えた、そんな時期にあった。ジャズはビバップやモード、フリー・ジャズが共存し、過激なインプロヴィゼーションによる演奏の正当性が議論され、エンターテインメントの足枷から抜けてアートとして市場原理からの解放を目指し、独自の表現を伝える手段として、持続的な制作インフラも含めて試行錯誤され始めていた。アフロ・アメリカンの音楽はアヴァンギャルドなジャズではない、実験的な音楽の前衛を目指して運動し始めていた。鼎談中、何度か話題になるジャズの十月革命(1964年10月1-4日)は、トランペット奏者のビル・ディクソンが開催した50名程度でいっぱいになるライヴハウス、セラー・カフェでの終演後、パネル・ディスカッション付きのイヴェントだった。彼はアーチー・シェップやセシル・テイラー、ポール・ブレイやカーラ・ブレイ、サン・ラに、メジャーなレコード会社のロジックに束縛されない、自律した新しい表現を可能にするインフラをアーティスト自身で組織し、運営しようと提案し、このイヴェントを計画した。チケットは完売し、この成功を受けて、その後に、参加したアーティストたちによってジャズ・コンポーザーズ・ギルドという擬似組合のような団体が立ち上がった。
ECMは発足当初ヨーロッパにあった既存のメール・オーダー・サービスを利用していた。同時期、ニューヨークでは、十月革命に参加し、ギルドのメンバーとなってミュージシャン自身による制作、運営、流通を目指していたカーラ・ブレイとマイケル・マントラーが、ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラを経てレコード会社WATTを設立し、アーティストが自主制作したアルバムの流通を手助けするニュー・ミュージック・ディストリビューション・サービス(NMDS)の立ち上げ(1972年)に向けて動き始めていた。後にNMDSは、ECMアメリカで最初に流通させた会社となる。同様にECMは、ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラを含めたWATTレコードの流通を担い、現在もその関係は続いている。NMDSはハリー・パーチ、ジョン・ゾーン、ギル・スコット・ヘロン、ローリー・アンダーソン、フィリップ・グラスらの米国内のレーベルに加えて、ECM、FMP、ブラック・セイントなどのヨーロッパの自主レーベルも扱った。ECM初期のヒット作の成功にも支えられてうまく走り始めたが、NPOとして立ち上げた団体の職員の労務負担をミニマムにしたいというカーラやマイケルの意向もあり、販売量が増えたレーベルは大手の流通に委ねるという方針が仇となり、次第に流通手数料が減り、組織運営を十分に支えられなくなり、1984年に破産する。
一方でECMは昨年、設立55年を迎えた。最初のアルバム、マル・ウォルドロンの『Free At Last』のリリースから数えて現在までに一体どれほどのタイトルが、音楽がカタログにあるのか。過激な完全即興の音楽に加えて、ステファン・ミカスのような民族楽器を使った即興音楽、北欧の音楽、1984年以降は現代音楽、クラシックなど、マンフレートが制作してきた音楽は、固有の生態系をECMというレーベル内に育んできた。それは固有の変異を遂げて、成長し続けるビオトークのようだ。そのあまりにも独自の生態系について、マンフレート本人が饒舌に語ることはあまりなかったと思う。アーティストが奏でるサウンドに耳を傾ければいいというそのあまりにもクワイエットな姿勢は、確かに沈黙の次に美しい。この鼎談から、その固有のエコロジーを産んだマトリックスが、本人の言葉で少し漏れ伝わってくる