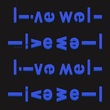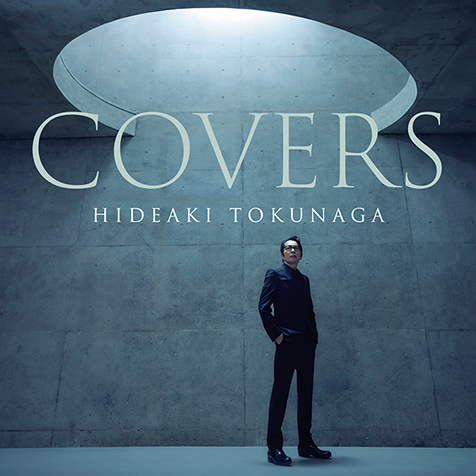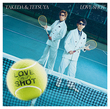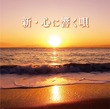ミニマルミュージックの泰斗スティーヴ・ライヒにも絶賛されたコンテンポラリーポップバンド、東京塩麹を率いる額田大志は、演劇カンパニー=ヌトミックを主宰するなど、演劇界でも注目の逸材だ。2022年の「ぼんやりブルース」で演劇界の芥川賞にあたる第66回岸田國士戯曲賞の最終候補作品にノミネートされ、演出家として第33回読売演劇大賞上半期ベスト5に選出されている。
そして、2025年11月22日(土)から30日(日)まで三軒茶屋シアタートラムで上演される「彼方の島たちの話」では、今年1月の吉祥寺シアターでの公演「何時までも果てしなく続く冒険」に続いて、生バンドが演奏を繰り広げる。メンバーは1月に引き続き、細井徳太郎(ギター)、渡健人(ドラム)、石垣陽菜(ベース)で、片桐はいりやヌトミック所属の俳優たちと共に舞台にあがる。額田が目指すのは〈新しい日本語の音楽劇〉とのことだ。そこで、SMTKやソロ、即興演奏の現場などで活躍する細井と額田に、互いの音楽観/演劇観や今回の舞台について語ってもらった。なお、大変濃密な対話となったため、前・後編にわけてお送りする。
柔軟な対応力が必要な現場で求められたギタリスト
――おふたりのなれそめから聞かせてください。
額田大志「最初は多分2019年。スガダイローさんと東京塩麹と対バンした時に、お客さんとして見に来てくれてた時ですかね」
細井徳太郎「厳密には誰かのライブをWWWに見に行って、入り口で共通の知り合いに紹介してもらったんだよ。びっくりするぐらいシャイなやつだな、という印象でした。すごく恥ずかしそうに、斜め45度下を見ていて(笑)」
額田「アハハ。そのあとにNHKのオーディオドラマ(NHK FMシアター『丘の上の干物屋』)の劇伴にギターで入ってもらったんだよね。
元々僕はプレイヤーというよりは作曲家なので、ライブの現場にいることが少ないんだけど、細井君は逆で、即興演奏も含めてライブが多いでしょう。今回のヌトミックの舞台で演奏してもらうことにしたのも、柔軟な対応力が必要とされる現場だから、それが即興演奏の技術と被る部分があると思ったからで。俳優さんの台詞や動きの機微みたいなものにちゃんとキャッチアップできるだろうと思ったんだよね。あとは、積極的に細井君のほうからアイディアも出してくれるし」
――エレキギターが欲しかった、というのと、細井さんが欲しかった、という両方がありますか?
額田「両方ですね。まず、電気楽器は出せる音色の幅が広いっていうのがありました。それと、台詞を言う俳優の声と帯域が合う楽器として、ギターがちょうどいいかな、というのと。
あと、僕らが今やろうとしていることは、過去の音楽劇の文脈をできるだけ接続しづらいものにしたいというのがあって。極端な話、三味線が入ったら日本的な文脈とどうしても結びついてしまうというか。あるいは、バイオリンとか弦楽器だったらオペラ的なものを連想させるかもしれない。楽器によってその音色が持ってるイメージが、固有の音楽劇と結びついちゃうことがある。そういう中で、ギターは比較的匿名性が高いってことが大きかったですね。それに、エレキギターってできてまだ歴史が浅いから、いかようにでも表現できる懐の広さが楽器自体にあるなっていうところですね」
細井「僕は1月の吉祥寺シアターの公演で初めてヌトミックでギターを弾いたけど、演劇に興味があるというよりは、額田大志という人がやっているヌトミックという劇団に興味があったんだよね。額田君が作るコミュニティであったりムーブメントであったりに興味を持った。こういうことをやってる同い年のヤツがいるんだって。
ただ、演劇だから特別いつもと違うというわけではなくて、いつも通りに演奏しているつもりで。僕はふだん音楽の現場で、即興音楽やジャズからオーバーグラウンドなポップスまでやっていますけど、それらと演劇に対しての距離って、自分が演奏する時のメンタリティや大事にしていることとの差はほとんどない。普段のライブと一緒」