1995年のある日、先輩方がおおかた出払ったランチタイムのレコード店にひとり店番でのこったアルバイトだった私はこのときばかりは聴きたい音楽が聴けると数日前にはいってきたばかりのアート・リンゼイの『曖昧な肉体』をかけるとかろうじて調性をもちこたえたギターのフレーズにつづきアート・リンゼイはこう歌う。「ひとつの空はオレンジで、いくつかの空は灰色もしくは濃紺、つまり青、それらがその名になる」オレンジ色を橙色というより茜色におきかえれば情景は夕焼け色に染まり、西の空を照らす夕日とそのまわりでは青空は暮れなずんでいても、すぐ外は灰青色で、頭をめぐらしてみやると東の空から夜がおとずれている、その階調はこれを書いたときのアートの目には四つの空と映った。わずかワンバースで私はアートの世界にひきこまれ、レジ前に魂の抜けた顔つきで突っ立っておったが、平日の昼さがりでお客さまはひとりもいらっしゃらない。『曖昧な存在』はやがて、その名のとおり曖昧さを際だたせながら、しかしいくらか退嬰的な曖昧ということばとは真逆の抽象化への厳しさを帯びながら進み、アルバム2周目の終盤にさしかかるまで結局誰ひとり客は来なかったが、昼メシを喰い終わられた諸先輩方は戻ってきて、松井秀喜を陰険にした感じの店長に、「こんな死にたくなるようなのかけんじゃない、お客さんが寄りつかないだろうが」とたしなめられた。私は彼が意外と本気でそういったのが意外だったけれども、そういわれてわれにかえりとっさに、「ああ、すみません」といったきり、止めようともしないのでまたお小言をくらった。「アートさん、もうしわけない」と心のなかでつぶやき私は『曖昧な存在』を止めたがこの曲を聴くたびのそのことを、歌のなかの風景と日常のそれの入れ子になった情景として鮮やかに思いおこすものの、それは懐中のノスタルジーほどあたたかくはない、記憶のなかで宙吊りになった奇妙な冷ややかな質感をともなっている。
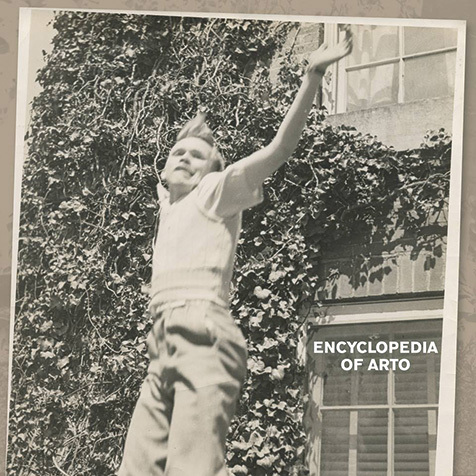
アート・リンゼイはその後、翌年から『ムンド・シヴィリザード』、『ヌーン・チル』と1年ごとに出したアルバムで宙吊りの高度を高め、99年の『プライズ』、21世紀にはいってからは『インヴォーク』(02年)を発表したが2004年の『ソルト』以降長い沈黙期間にはいった、その理由について「ブラジルに引っ越してすぐ病気をしたのがレコードをつくる作業が止まってしまった一番の理由です」と10月末のライヴで来日したアート・リンゼイはいった。『ソルト』のとき以来だから会うのはおよそ10年ぶり。昼さがりのホテルオークラのラウンジの壁一面の窓の外の中庭の常緑は秋めいてきた気候を忘れさせるがアートの白くなった髪と面差しは先の発言を裏づけるようにみえる。彼は2004年にニューヨークからバイーアに、2008年にはリオに移った。ブラジルに移住してすぐ息子が生まれ、体調を崩しはしたが終始療養していたわけではなかった。アートは「ブラジルでは新しいパレードのかたちを発明(Inventing)することに熱意を向けていたせい」で音楽作品からは自然と遠のいた。
バイーアでの最初のパレードは『プライズ』のアートワークにも参加したマシュー・バーニーとの共同制作だった。パレードをアート・フォームとして再定義するこのプロジェクトは伝統の批判的継承であるとともに、『プロジェクトFUKUSHIMA!』の盆踊りで大友良英がやろうとしている協(同)働の試みとも共通する、コミューナルでありながら開かれており地域性の偏差が色濃く影を落とす。アートはそれをバイーアからリオへ移り住む過程でもみいだすことになる。
「リオのカーニヴァルは美しいけれどもショービズ的で工業的だね。オスカー・ニーマイヤーがリオの真ん中にパレード用の街路をつくったせいでリオでのパレードはテレビの画角に収まるようなものになってしまったんだね。音楽的な自由度もそれによって損なわれてしまった。バイーアのパレードはスローな曲、スローな曲はセクシャルや、ときには政治的な意味をもつものだのだけど、そういった曲がある一方でテンポの速い曲になればモッシュピットさながらになる、ショービジネスと音楽と社会との狂ったミクスチャーなんだ、混沌として野獣的なんだ」
それがオモシロイ、とアートは日本語でいう。「日本語はムズカシイ。でもひさしぶりに日本にやって来て、ちょっとずつ私の日本語のヴォキャブラリーも戻ってきています。それでもたかだが10か15語くらいなんだけどね」といって笑うアートの、DNA時代から起算すると30年をこえる活動歴を、ニューヨークを根城にしたひとりのコスモポリタンがアイデンティティをもとめた道程だとすれば、歌とことばと音と人脈の粋を凝らした6枚のアルバムでブラジルという一点にゆるやかに集約していった力線は今後外側に反転しないともかぎらない。このベスト盤『Encyclopedia Of Arto』は集成というよりその転換点のではないか、と問うとアートは「それにこのベスト・アルバムは私の再スタートでもあります」と答えた。“アートの百科事典”と題したベスト盤は代表曲を編んだ1枚目と2011~2012年にかけてベルリンとニューヨークで録ったソロ・ライヴ音源との2枚組で、1枚目は6枚のアルバムからまんべんなく収録しライヴは弾き語りというよりノイズ語り。既発曲をアルバムに並べ直し、けれども物語性をよくばらない王道のベスト盤の流儀に則った構成は『Encyclopedia Of Arto』をアート界へのかっこうの入門編となるカタログに仕立てあげる、というより、門そのものかもしれない、二枚一対だし。
一歩足を踏み入れたらアート界が広がっていた。そこではソフト/ラウド、スタート/ストップ、サイレンス/ノイズの対立は解かれている。アートによればそれはメッセージではなくメソッド=方法であり方法は音楽を象る。そしてその方法は解決や止揚を結論しないので、一貫してアートの音楽の核にとどまりつづけた。彼は彼がそれをどう位置づけるかというよりリスナーのひとにそれを意識するきっかけにこのベスト盤はなってほしかった。それは美学の、または分析の問題である。だからシリアスな芸術なのだと眉間にシワを寄せるのはお待ちいただきたい。アートはまた、曲を選び直すにあたり6枚のアルバムを聴き通して、いちばん気になったのは歌だったともいった。「マジメな話、6枚ともバラバラというか印象がちがうね。ヴォーカルには満足いく部分とそうでないところがあった。ヴォーカルにはとくに厳しい自己採点になってしまう」のは彼がこれらの音楽を明確にポップソングと規定するからにほかならない。
「音楽をつくるにあたり批評的な部分はもちろんあるけど批評はさして重要ではなく、つくったものを、精神をクリアにして次の日客観的に聴き直すかが大切なんです。歌詞はまたちょっとちがって、批評的な行為が重要になる場合もあります。いかにことばを削ぎ落としていくか、そういうことを考えます」
ことばから音楽が生まれるんですか、あるいはその逆とか、と私は訊いた。
「ことばが先のときもあれば逆のときもあります。歌詞のインスピレーションの源になっているのは本を読むことですね。それは本のなかのワンフレーズということではなく粗筋でもなく、本全体がかもすものを瞑想にちかいかたちで汲みとる。ぼくにとって読書はとても大切です」
ではアート・リンゼイの座右の書はなんだろう。3冊あげてください。
私の質問にアート・リンゼイはしばし沈黙した。
「すごくむずかしいね。1冊目はロベルト・ムジールの『特性のない男』。それとジョン・ケージの『サイレンス』。そして――といってアートはホテルオークラの中庭に視線をさまよわせながらまたも沈黙する――いっぱいありすぎてどう答えたらいいかわからないから最近のにしよう。人生を変えたというほどではないけれどもロベルト・ボラーニョの『野生の探偵たち』だね」
いずれも翻訳本が出ているので気になる方は手にとられるといいと思うが、現実の記号性(特性)を拒絶し可能世界に生きる主人公の物語と非=物語ないまぜのムジールのそれにせよケージの代表的著書にせよ、チリに生まれメキシコに没したかつて詩人であった小説家の自伝の虚構化というべきボラーニョの一編にしても、きわめてアート・リンゼイ的なチョイスだとうならされた。これらの本では抽象と現実(というより現実の抽象化の態様)がブランショのいう「死」のなかでせめぎあい、かつこれがもっともアート的なところだが、いわくいいがたい官能とユーモアがそこににじんでくる。
「もうひとり加えていいならバロウズでしょうね。彼はケージと同じく卓越した物語の語り手であるとともにすばらしいユーモリストでもあった。私はバロウズもケージも何度か朗読会に参加して、彼らが読むのを聴きましたがそれはとてもすばらしい体験でした。私は詩人が自作を朗読するのを聴くのが好きです。作者は自作を朗読するとき、声のドラマに逃げない。ことばそのものをフローさせるんですね。ジョアン・ジルベルトもそういっていますね。音楽そのものに流れを任せなさい、と。しかし彼はかならずもそれをやっているかといえばいささかあやしい。年を重ねるにつれ、ジョアン・ジルベルトでさえ歌い方はドラマチックになってしまった。ところがボブ・ディランは『テンペスト』にいたるもそうはなっていない。ものすごくアブストラクトだ」
だからといってアートの音楽はかたくなにアンチ=ドラマを志向するばかりではない。ミニマル・ミュージックやドローン、メルツバウやマゾンナやサンO)))、『メタル・マシーン・ミュージック』がドラマを内包するようなやり方でドラマなのだとアートはいう。
もちろんこれはすべてが並列になったというバカのひとつおぼえともgoogle的網羅性ともビッグデータ的統計とも関係ない。『野生の探偵たち』で登場人物のひとりが言及する架空の小説家アルチンボルディが、のちの『2666』の作中でカフカと並び怪物的とみなしたデーブリーンの『ベルリン・アレキサンダー広場』やムジールのウィーンにジョイスのダブリンを重ね合わせるとき、『フィネガンズ・ウェイク』を音楽化したケージがたちあわれる、バベルの図書館の蔵書さながらに連結し増殖する“アートの百科事典”をリスナーおのおのがつくるということではないか。
DNAからアンビシャス・ラヴァーズを経てソロへ。ノーウェイヴからフェイク/ポップミュージック、カエターノ・ヴェローゾの薫陶を受け、ブラジルへ。アート・リンゼイの百科事典に奥付はない。10年ばかりの空白などいかほどのものでもないのである。
追記:私は〆切りに追われるあまり大切なことを書き落とすところだった。アートによれば来年秋を目標に新作の録音に春ごろから入るとのことである。
期待しています、という私にアートは訊いた。
「I’ll do my best」は日本語でなんていうの?
「がんばります」でしょうね。
「じゃあガンバリマス!」
アートはまたひとつ日本語のヴォキャブラリーを増やしてブラジルに帰った。
Arto Lindsay(アート・リンゼイ)
1954年、ニューヨーク生まれ。3歳から18歳までブラジルのレシーフェで過ごし、フロリダの大学に進学。70年代後半に「DNA」を結成し、ニューヨークの前衛音楽シーンで注目を集める。84年にアンビシャス・ラヴァーズを結成し3枚のアルバムを発表。また、80年代からはカエターノ・ヴェローゾ、ガル・コスタ、マリーザ・モンチなどブラジルのミュージシャンのアルバムプロデュースも手掛け、高い評価を得ている。日本においても坂本龍一、コーネリアス、テイ・トウワとの共同作品を発表。多くのアーティストとのコラボレーションを行っている。
寄稿者プロフィール
松村 正人(まつむら・まさと)
1972年奄美生まれ。編集と執筆。ロックバンド湯浅湾のベーシスト。2014年下半期は9月末に監修した『Progressive Jazz』を、10月末に編集した湯浅学氏著『てなもんやSUN RA伝 音盤でたどるジャズ偉人の歩み』、11月末に同じく編集を担当した保坂和志氏と湯浅学氏の対談本『音楽談義』を出した。





























