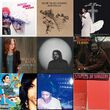パブリック・エナミーとアンスラックスのライヴを観てバンドの結成を決意した。グループ名は車で通りかかった公園から拝借した。ラップ・メタル景気に乗じて一気にスターダムを駆け上がった。すぐにバブルは崩壊した。でも、彼らは動じなかった。リンキン・パーク──浮き沈みの激しい音楽シーンをサヴァイヴしてきた6人の侍。熱い心と冷静な頭で聴き手の予想を裏切り続けてきた彼らが、次に仕掛けるサプライズとは? これはゴールなのか、さらなる栄光へのステップなのか……
★Pt.2 リンキン・パークの過去作を徹底解説&ジェイ・ZやノトーリアスBIGへの偏愛見せてきたマイク・シノダのヒップホップ観
★Pt.3 リンキン・パークはどう愛されてきたのか? ONE OK ROCKからリアーナまで、ミクスチャーの変革者巡るピープル・トゥリー

〈リンキン・パークの魅力を紹介してほしい〉とのことで、この原稿を書いている。確かに僕はリンキン・パークが好きだし、仮に好き嫌いを脇に置いたとしても、素晴らしいバンドだと思う。だがしかし、〈グループとしての魅力は何?〉と改めて尋ねられると、なかなか気の利いた言葉が浮かんでこない。なぜか。それは、評論家の方々から非難されるかもしれないけれど、たぶん僕が感覚的に音楽を聴くリスナーだからだろう。彼らを好きになった理由を挙げるとするなら、〈カッコイイと思ったから〉とか〈グッと来たから〉、〈感情を揺さぶられたから〉、あるいは〈曲が良くて声が良いから〉といったようなものだし、人に好意を持った時、気付いたら好きになっていたのと同じで、理屈でどうこうというものではない。
でも、それでは話が終わってしまうので、この機会にリンキン・パークの魅力を端的に表す言葉はないか探してみたら、相応しいと思えるものがふたつ見つかった。それは〈批評精神〉と〈チャレンジ精神〉。考えてみたら、後者はともかく前者に関しては、過去に好きになったグループにそんなことを感じた例はなかった。後にブルックリン勢を中心に、〈知性〉とも呼べる同様の感覚を持った集団が数多く登場してくることを考えても、ゼロ年代産のバンドの特徴のひとつだったのかもしれない。そういえば、メンバーに初めて対面インタヴューを行った際、学者を連想させる風貌のマイク・シノダを筆頭に、みんな礼節を弁えた真面目で聡明そうなナイスガイたちで、予想とのギャップに少なからず面喰らったことを覚えている。〈セックス、ドラッグ&ロックンロール〉などもはや虚構であり、愚の骨頂というわけか……と思って、当時、日本で流行っていた〈草食系男子〉の話題を向けてみたら、逆に凄く喰いついてきておもしろかったのだが、その話は別の機会に。

新たなミレニアムの幕開けと共に
チェスター・ベニントン(ヴォーカル)、マイク・シノダ(ヴォーカル/キーボード/ギター)、ブラッド・デルソン(ギター)、デイヴ“フェニックス”ファレル(ベース)、ロブ・ボードン(ドラムス)、ジョー・ハーン(ターンテーブル)の6人により、90年代後半にLAで結成されたリンキン・パークは、ミレニアムの2000年にファースト・アルバム『Hybrid Theory』でメジャー・デビューを果たした(リリース直前にフェニックスが一時脱退するもすぐに復帰。なお、日本デビューは翌年のこと)。当時のロック・シーンと言えば、〈ラップ・メタル〉や〈ニュー・メタル〉と呼ばれ、まさに雨後の筍状態で乱立していたヘヴィー・ロック勢が、やや失速を見せはじめた時期。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのザック・デ・ラ・ロッチャが、「リンプ・ビズキットが売れてこのジャンルは死んだ」という言葉を残してバンドを離れたのも、2000年のことだった。その後、淘汰されながら枝分かれしていくラウド・ロック・シーンにあって、もっとも大きな成功を掴んだリンキン・パークが同年に表舞台へ飛び出したというのは、運命的な巡り合わせとでも言おうか、何とも象徴的だ。
『Hybrid Theory』で彼らが提示したのは、メタルもインダストリアルもグランジもヒップホップも、エレクトロニカをも自在に横断しながら、そこから美しいメロディーを紡ぎ出し、さらには激しいスクリームと鋭利なラップを炸裂させるという、ミクスチャーの在りようを2000年代ヴァージョンに更新したような重たいサウンドであり、歌の世界だった。これぞまさしくハイブリッド。別枠に各アルバムの紹介があるので、内容についてはこれ以上深く触れないが、もともとのグループ名だったハイブリッド・セオリー(同名バンドが存在したために改名)が、そのままタイトルに掲げられていることも、自信に満ちたメンバーのステイトメントに思えてならない。
続いて2003年にリリースした2作目『Meteora』では、さらに重度と強度を増し、研ぎ澄まされたヘヴィー・ミクスチャーを確立。前作を上回るほどの熱烈な支持を集め、リンキン・パークは一躍モダン・ロックのトップ・アクトへと登り詰める。同時に『Hybrid Theory』と『Meteora』の2枚のアルバムは、彼らのサウンドのスタンダードとして認識されることとなるのだった。大きな衝撃と称賛を持って迎えられた作品という意味で、位置付けとしてはウィーザーの初作『Weezer』、UKならオアシスの初作『Definitely Maybe』や2作目『(What's The Story)Morning Glory?』に通じるものがあると思う。

挑戦し続ける姿勢
さて、ここからが、冒頭で述べた〈批評精神〉と〈チャレンジ精神〉の話。最初の2作品で栄光を手にしたリンキン・パークは、次作でそれを返上するかのように大胆な音楽性の転換へ打って出る。2007年の3作目『Minutes To Midnight』では、それまでのラウドでハードでドライヴィンなギターは鳴りを潜め、ミクスチャー感も極度に減退。代わって、オーガニックで温かみのあるサウンドが奏でられ、深みのあるメロディーでチェスターの叙情味たっぷりなヴォーカルを前面に押し出している。みずから築き上げ、ワールドワイドなブレイクをもたらした音楽スタイルを捨て去って、彼らは時にU2さえ彷彿とさせるヴォーカル・オリエンテッドなロック・バンドへと姿を変え、しかも日本を含む世界30か国以上のチャートを制覇してみせたのだ。ちなみに、1~2作目の意味合いがウィーザーとオアシスの最初期作品に近いとしたら、この3作目はレッド・ホット・チリ・ペッパーズにおける『Californication』に相当すると言えるのではないだろうか。
自分たちに対する、また時代の趨勢やシーンの動向に対する批評的なリアクションとも、チャレンジとも受け取れる6人のこの姿勢は、続く2010年の4作目『A Thousand Suns』でも強固に貫かれた。彼らは前作のバンド・サウンドを、いとも簡単に解体してしまう。そして、繊細なアコギにアンビエントなピアノ、狂気のスクリーム、科学者や政治運動家らの演説など、さまざまな音要素をコラージュした実験的なニュー・サウンドを聴かせるのだった。


リスナーの予想を裏切るという点では、2012年の5作目『Living Things』も然り。『Minutes To Midnight』と『A Thousand Suns』でそれぞれ別方向へと大きく舵を切ったバンドは、一旦スタート地点へ戻って己の飛距離を確かめるかのように、〈リンキン・パークのスタンダード〉と呼ぶべきミクスチャー・サウンドを、自身の表現力をアップデートさせたうえで果敢に鳴らしている。前2作に迷いや逡巡があったのかと言えば、決してそうではない。しかし彼らには、ここで自分たちが発明したミクスチャーのニュー・スタイルと真正面から向き合い、それを対象化させる必要があったのだろう。〈その先〉へと挑戦し続けるために。
メンバーが〈その先〉に見い出したもの、それはメタルやパンクといった暴力的とも破壊的とも言えるヘヴィーなサウンドだった。2014年の6作目『The Hunting Party』──〈狩猟集団〉を意味するタイトルを冠した同作で、6人はそれこそ自分たちが実は〈肉食系〉であることを標榜したかったのかもしれない。もしくは、キャリアを長く重ねてきて、このあたりで一度、キッズの頃のように怒りやフラストレーションを音楽で爆発させたかったのかもしれない。いずれにせよ、しばらくロックのメインストリームに欠けていたサウンドを体現してみせるあたり、やはり批評的で挑戦的なアティテュードを感じる。

こうして改めて、彼らの現在までのキャリアを振り返ってみて、俄然、湧き上がってくるのが次なるニュー・アルバムへの期待感だ。しかもその『One More Light』がまた、とんでもないことになっているではないか。リンキン・パーク、恐るべし。そして、愛すべし。キャリア17年超えで、これだけワクワクさせてくれるバンドには、そうそう出会えるものじゃない。 (文/鈴木宏和)
リンキン・パークのライヴ盤を紹介。