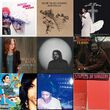彼らは野心的に踏み込んできた。それは時に革命のようでもあり、時としてある種の宗教のように映ったかもしれない。いずれにせよ確かなのは、独特のムードが徐々に南下し、やがて列島の興味が北上したということ。情熱と傷みを身に刻みながら愛と別れの20周年を迎えたTHA BLUE HERB、その魅力の根源とは……
ラッパーのILL-BOSSTINO(以下BOSS)とトラックメイカーのO.N.O、ライヴDJのDJ DYEの3人から成るTHA BLUE HERB。BOSSいわく「缶ビールを開けて、(O.N.Oと)飲みながら喋って、それを飲み終わる前にはもう決まっていた」というグループ名は、BOSSがかつて好きだったTHE BLUE HEARTSをもじってノリでつけたものだという。少なくとも彼らの地元・札幌から遠く離れた人間にとっては突如として現れたかに見えたその音楽の衝撃は、もっともピュアな形でファースト・アルバム『STILLING, STILL DREAMING』(98年)にパッケージされている。時代々々、アルバムごとに少しずつ音楽の形を変えながら、彼らは常に聴き手と真っ向から対峙する楽曲とライヴを通じて幅広くファンを増やしてきた。そしてまた彼らは、インターネット全盛となる以前に、地方でもインディペンデントなビジネスが成り立つことを、同業者たちにいち早く身を以て示してきた。その牙城は、キャリアの深まりと共にヒップホップというフィールドの中でますます揺るぎないものとなっている。
北から来たカリスマ
BOSSとO.N.Oの縁は、90年代の初め、当時ダンサーだったBOSSが、DJとして駆け出しだったO.N.Oのアパレルショップに、ダンス用のミックスを頼みに行ったことから始まった。同い歳(共に71年生まれ)の2人はそこで意気投合し、すぐに「ほぼ毎日つるむように」(O.N.O)なったという。そんな両者が、1MC+1DJとしてキャリアをスタートさせるのは93、4年頃のことだ。ごく身近で活動していたB.I.G. JOEとDJ TAMA(現在はS.P.C.で活動中)の姿や、NYのヒップホップに触発され、2人はコンビとして歩みはじめた。
「B.I.G. JOEとTAMAがコンビ組んでたのが俺たちの中ではデカくて、俺はB.I.G. JOEのラップを見てカッコいいと思って始めたから、それがひとつの型としてあったし、NYのヒップホップにどんハマリだったから、俺らは。1MC+1DJっていえばギャング・スターやピート・ロック&CL・スムースもそうだし、そこにすごい憧れて、NYのインストに乗せてラップをしたりだとか、最初はほぼ真似事だったね」(BOSS)。
「あの頃は俺もDJでNYのヒップホップばっかりかけてたし、普通にヒップホップはこういうもんだっていう感じだった。最初の頃は一晩のクラブ・プレイの合間にマイクを入れるって感じが強かったね」(O.N.O)。

程なくして楽曲制作を始めた2人は、その共同作業をデモテープやカセット・アルバムに仕上げていく。だが、いくつかのコンピへの参加こそあれ、いずれかのレーベルから声がかかるのを待っていた彼らに契約の誘いは届かなかった。BOSS THE MC & DJ ONOという名義で活動していたコンビがTHA BLUE HERBを名乗りはじめたのもその頃だ。「当時の俺らにしてみればかなりの借金だったから、それで背負うもの、気持ちの入れ方も変わった」というO.N.Oの言葉を待つまでもなく、やむなく消費者金融からの借金などで何とか漕ぎ着けたレーベルの立ち上げ~音源リリースという状況が、先述したファースト・アルバムにおける表現に影響を及ぼしたことも間違いないだろう。ファースト・シングル“SHOCK-SHINEの乱”(97年)からアルバム『STILLING, STILL DREAMING』へと至る1年足らずの間に覚醒したBOSSのラップは、いま聴いても劇的に響いてくる。
「最初のシングルは思っていたよりも良い出来だったんだけど、自分でも力が入りすぎてるのはわかったし、〈やりたかった音楽を作れた〉っていう感覚ではなかった。でも、『STILLING, STILL DREAMING』の“ONCE UPON A LAIF IN SAPPORO”を録った時に、何か見えたんだよね、自分の中で。トラックもドラマティックな展開ではない、ドープで淡々としたトラックで。その中でライミングを転がしながらグルーヴを作っていくコツみたいなのを掴んだ記憶がある。こうやればカッコいいんだなっていうのが」(BOSS)。
歌詞の対訳を読み込んでBOSSがその身に染み込ませたナズのクラシック『Illmatic』よろしく電車の音をSEに使った“THIS '98”から始まる『STILLING, STILL DREAMING』は、当時のラップ・シーンの中心=東京から遠く離れた札幌で抱えるフラストレーションをストイックかつハードボイルドに自家培養し、シーンに戦いを挑む自分たちの姿を多岐に渡るヴォキャブラリーでリリカルに昇華。そのスタイルと表情を崩さぬラップ、独特なトラックは、本作を彼ら最初の金字塔たらしめ、多くのフォロワーを生むこととなった。それと共に、DJ KRUSHが誰よりも早く彼らを見い出し、アルバム・リリース以前から“知恵の輪(THIRD HALLUCINATION CHAOS)”を(日本のみならず世界で)プレイしていたこともグループには追い風となった。そして、ヒップホップ的な文脈を切り離してなお残る、確信に満ちたある種の哲学的/人生訓的なBOSSの言葉の広がりとラップの強度は、当時のカリスマ的なライヴ・パフォーマンスも手伝い、アンダーグラウンドな音楽シーンから共有され、広く受け入れられていく。
ライフ・ストーリーへ
しかし、アルバムの反響を現場で肌で感じはじめていたBOSSに対し、その頃ライヴDJをDJ DYEに譲ったO.N.Oは違う思いを抱いていた。O.N.Oは言う。
「アルバムを出して、俺らはもっとすぐレスポンスが来ると思ってたんだよね、〈みんなが聴きたかった日本語のヒップホップ・グループが出たぜ〉って。でもそれがそんなに、っていうか、全然来なくて」。
ファーストから4年を経て発表したセカンド・アルバム『SELL OUR SOUL』(2002年)は、O.N.Oにとってその鬱憤を晴らすべく制作に向かった一作だ。NY産ヒップホップの影響下で「狙って作るっていうところまで突き詰めていけなかった」と語るファーストへの彼なりの反省がここでは音になっている。
「ファーストはヒップホップ・ファンを強く意識してたんだけど、そんなこと無視して、〈これ聴いて死ね〉ぐらいのつもりで、いま自分が作りたい音を突き詰めようっていう気持ちがすごい強かった。だからもう、ソウルとかレアグルーヴからただフレーズ持ってきて切って貼ってっていう作り方じゃないなと思ったし、サンプリングでできることをギリギリまで詰めてやろうっていう」(O.N.O)。
そんな音と共に、リリック面でもグループの初期設定たる初作からさらに複雑さを極めた本作について、BOSSがさらに話を続ける。
「俺もO.N.Oもあの頃それぞれ世界中を長い期間かけて旅していたから、トラックに関してはそこが大きく影響してると思うし、リリックも札幌の街から見てた世界とは違って、旅先で書いてたから。まあ、あの時は俺自身ブッ飛んでたからね。11か月の旅の間ずーっとブッ飛んで、ブッ飛んだ世界のまま帰ってきて、それが醒めない状態で作ったから。ファーストもそうだし、全部の段階で言えるんだけど、毎回毎回違う状況の中の一番純度の高いものを残すっていう意味で、あれほどまでにブッ飛んでリリック書いて音作って、曲を仕上げて録音する時期はもうないだろうね。だから、あれはあれでオリジナルなアルバムになった」(BOSS)。

そうした『SELL OUR SOUL』のテンションを落ち着かせるかのようなサントラ盤『HEAT』(2004年)を挿み、前作から5年で発表した3作目『LIFE STORY』(2007年)は、自分たちが勝ち上がってきたラップ・ゲームのメンタリティーをなお拠りどころとしながらも、現実の生活に根を下ろす世界に彼らがシフトしはじめたことを物語る作品だ。そこには、私生活での結婚を含めた周囲の環境の変化が大きく関係していた。
「その頃はもう日本全国に行っていて、47都道府県の各地に帰るべきハコも仲間もできてたし、その中でどう関係を深めていくかだったからね。30代中盤で、ただ遊びや楽しいっていうことだけでヒップホップを続けられるような時代でも世代でもなくなってきて、それはお客さんもいろんな面でそうだし……ってなると、いわゆるライフ・ストーリーというか、それぞれの生活だったり暮らしの中のことを歌っていく心情になっていったんだよね」(BOSS)。
サンプリング・ベースの制作から、打ち込みや手弾きへとトラックの軸足を移し、フィジカルな音楽性を高めた『HEAT』の延長で、O.N.Oの音はここでも進化の跡を見せている。
「楽器を弾くようになって、BOSSの感情を自分のイメージでコントロールできるのも、BOSSが感情を乗せることで曲のストーリーがさらに変わっていくのも、すごくおもしろかった。セカンド以降トリッキーに極めた技術を使いながらシンプルに聴かせるものをめざしたし、鳴りからビート感、グルーヴもライヴで映えるトラック作りをしたいなっていうのはあったね」(O.N.O)。
さらに、2012年の4作目『TOTAL』は、前作から4年の間に起こった東日本大震災で一変した〈3.11〉以降の時代の空気にみずからを重ね、改めて戦いへと鼓舞するものに。時代に並走するアルバムとしては過去3作の上を行く、かつてない説得力を手にした。エレクトロニックなトラック捌きをますますシンプルに研ぎ澄ませ、壮麗な旋律で自在に曲のムードを操る巧みなサウンドは、『LIFE STORY』以降O.N.Oが活発化させていたソロの動きと無縁でないはず。その完成度は、また一つ上の到達点を示している。
「『LIFE STORY』は広がったり良くなっていく時代観なんだけど、『TOTAL』は俺らの仲間も亡くなったり、〈3.11〉以降の狭まって悪くなっていく感じが見えてきた時代の中でどうやって生き残っていくか、考えるタイミングだったと思う。それぞれの苦悩や葛藤があるなかで、そういった負の感情をどうやって上げていくかという感覚だったと思うよ」(BOSS)。
「ソロでライヴして回る機会もすごい増えてたからそれがよりいっそう出たのと、THA BLUE HERBのライヴもさらにたくさん観て曲の作り方もまたさらに突き詰めてったから、全体に力強くなってるし、コード感も使いこなせるようになってきてる。ソロとはまた違う、ヒップホップの枠の中で新しいものを作るのもおもしろかったね」(O.N.O)。

俺らはこういう奴らだよ
こうしたリリースは言うに及ばず、多くのシングル曲、それぞれのソロやユニットの作品、客演活動に、日々のライヴやDJプレイと歩み続けたTHA BLUE HERBは、今年で結成20周年を迎えた。「ミュージック・ビジネス自体を自分たちで成立させてきた20年だから、長かったし、濃密だったなとは思う」とBOSSは振り返るが、その道は半ばだ。「もっと長く続けてる先輩とかいるからさ、それを考えると別に大した数字でもない。ホントただの過程だよ」(BOSS)――その思いを胸に、また新たに記すTHA BLUE HERBの一歩が、先月の2枚組ミックスCD『THA GREAT ADVENTURE - Mixed by DJ DYE』に続いて4年ぶりに発表する新曲集『愛別 EP』だ。タイトルは北海道に実在する町の名前であり、ジャケのメンバー写真も、同名の駅舎を背にしたもの。その字面から転じた〈出会い(=愛)と別れ〉は、今回のEPのモチーフだ。

「札幌と俺らがよく行く北見の間に、愛別って駅があるんだよ。そこをよく通ってる時にこの2文字がいいなあと思って、いつかここで写真を撮って作品に落とし込みたいな~とずっと思ってた。それとこの20年を重ねたんだ」(BOSS)。
今回のEPを制作していくうえで、まず取っ掛かりとなったのが、3曲目に収められた“20YEARS, PASSION & PAIN”だった。
「EP全体の大まかなテーマみたいな感じで“20YEARS, PASSION & PAIN”のイメージをもらってたから、今回はそこに合わせて作っていった。いつもは1曲に対して1トラックっていうのが多かったんだけど、今回はトラックをどんどん作っては渡してって、意見をやりとりしながらガッツリ作っていったし、そのやりとりはいつもより多かったね」(O.N.O)。
センティメンタルな鍵盤に彩られた収録の3トラックは、「コード感はそれぞれ変わってくるけど、ライヴで持ってくことをイメージして、広がりがある感じで」(O.N.O)作ったというもの。人として、またアーティストとして歩んできた20年と〈愛と別れの狭間を生きてく〉これからに思いを馳せる“20YEARS, PASSION & PAIN”を締めに、それに先立つ“ALL I DO”と“BAD LUCKERZ”では、彼らの音楽を支持し続けるオーディエンスのみならず、去っていったオーディエンスにもメッセージを向け、いまなおここに立つ彼らの矜持を示すものともなった。
「“20YEARS, PASSION & PAIN”こそアレだけど、今回のEPも基本的に〈またカッコいい曲作ろうぜ〉っていう感覚でスタートしてるし、カッコいい曲を作りたいっていうだけの話だよ。“ALL I DO”にしても、〈俺らはこういう奴らだよ〉っていうTHA BLUE HERB節の最新版だよね。EPとしてもバッチリだと思う」(BOSS)。
「満足してるね。いままで俺らTHA BLUE HERBを聴いてくれてた人があたりまえに聴いてたようなことを再確認できるっていうか。リリックに関してもそうだよね。俺たちがこういうグループだったんだぜっていうことはみんなも忘れちゃいないだろうけど、そこをあえて触ってくるっていうのはホントにいいなあと思った。新しく聴く人たちもそうだけど、ずっと聴いてくれてた人たちももう一回確認できるっていうかね。俺自身も自分の好きだったTHA BLUE HERB像が全部あるっていうのを今回すごく感じるね、作品として」(O.N.O)。
このEPリリース後、10月には日比谷野外音楽堂での20周年記念ライヴも予定されている。野音は、BOSSがかつてオーディエンスとしてSIONのライヴで訪れた思い出の地。来たるべきそのライヴに水を向けると、「まだ全然わからない。昨日もライヴで、今日もライヴだし、そこまで考えられないね」とBOSSは笑った。“ALL I DO”で歌われるように、〈なりふり構わず生身で体当たる 魂の会話〉を繰り返してきたのがTHA BLUE HERBだとすれば、そうした言葉もむべなるかな。その先に見る景色がどんなものかは知る由もないが、野音のライヴと共に、彼ら自身が新たな作品でどんな景色、生き様を見せてくれるのか、いまは待つのみだ。
THA BLUE HERB RECORDINGSからのコンピ。
メンバーの参加した2017年の作品。
DJ DYEのミックスCD。