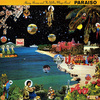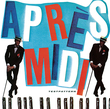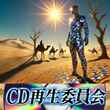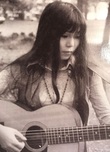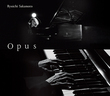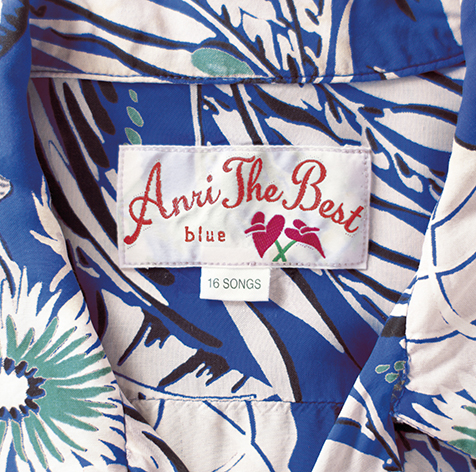〈いまの耳〉にも新しいサウンド観
40年の時を経て、新たにグっとくるポイントについて挙げていこう。ファースト・アルバムに入っている坂本龍一作“東風”のイントロは、星野源の今年の大ヒット曲“アイデア”(TVドラマ「半分、青い。」主題歌)の冒頭に引用された。“東風”のアジア性豊かなメロディーに乗ったテクノ・ポップ・リズムは不滅の輝きだ。細野との親交が深い星野の音楽には、YMOのジャストなポップ・サウンドが骨の髄まで溶けこんでいる。YMOが日本の音楽を塗り替えるまで、日本の歌謡曲、ポップスは旧来のロックやジャズ、クラシックのミュージシャンによって作られていた。それは欧米の後追いだったので、世界に並ぶことは考えられなかったが、YMOは日本のポップスを世界水準に引き上げた。星野源のような弾けるポップスが生まれる背景には、そんなYMOの威光があるのだ。
US版『Yellow Magic Orchestra』は、スーパーヴァイザーにトミー・リピューマ、ミックス・エンジニアにマイケル・フランクスなどを手掛ける往年のA&Mサウンドの名匠アル・シュミットが起用されているという、洋楽マニアにとっては奇跡の組み合わせもポイントだ。日本版ファーストとは趣を変えたバキッとしたフロア・サウンドはぜひ押さえておきたい。“東風”には吉田美奈子のヴォーカルが加えられていることも特筆すべきところ。
『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』は、シンセサイザー・メインで描かれた巨大な近未来空間の迫力がすごく、まるでキューブリックの映画「2001年宇宙の旅」のように古びないSF感覚に、いま聴いても震えがくるほどだ。“テクノポリス”は〈トキオ!〉というヴォコーダー声がカッコイイ! Perfumeのケロケロ声はオートチューンというエフェクターによって作られるが、その先祖はこのヴォコーダー。初音ミクと比べてもカッコイイこの音色は絶品。このようにロボットやAIのような近未来的イメージは、YMOがリーダーとして先導した。ニュー・アカデミズム、構造主義のような哲学の新潮流とも合流し、軽薄ではない、含蓄が深く強い文化ムーヴメントを作り出したことは忘れられない。『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』には、“ライディーン”のようなキャッチーなナンバーが入っていて楽しさには事欠かないが、いま聴くと全曲の粒立ちに驚く。先日の細野晴臣ロンドン公演で1曲だけYMOが再結集してやった“アブソリュート・エゴ・ダンス”のアンドロイドな琉球メロディーや、“キャスタリア”のようなエッジーな無機質ポップの先鋭性がジワジワと耳を突く。ブライアン・イーノやデヴィッド・ボウイと並んで一線に立っていたことが思い出される。
今回リリースされた編集盤『NEUE TANZ』は、DJとしてのテイトウワの腕が冴え渡った名盤となったが、その中心となるリズム感覚にはYMOのとてつもない未来性が引き出された。1曲目“開け心─磁性紀─”はフジカセットのCMのために作られた曲だが、この曲にはすでに次作『BGM』で試されるミニマル・テクノの萌芽がある。すなわち、90年代にデリック・メイやジェフ・ミルズ、日本では電気グルーヴによって世界に吹き荒れるフロア・テクノの予言的音楽性だ。当時は比較的単調なリズムぐらいに思われたが、この曲が『BGM』からの“バレエ”、さらに坂本龍一の“ライオット・イン・ラゴス”に繋げられるこの盤の鮮やかさは凄まじい。『NEUE TANZ』の前半を聴けば、YMOは90年代や2000年代のサウンドを予見していたことが明瞭にわかるだろう。
さらに『BGM』からの“千のナイフ”での坂本のシンセサイザー・ソロ音、“スポーツマン”における細野のテクノ・パーカッション音など、鍛え抜かれた音色が砂原良徳の渾身のマスタリングによって引き出されていることも特筆すべき。〈いまの耳〉によってこれだけ現代性が出る、まさにYMO音源は無限の可能性を秘めた日本最高の財産なのである。 *サエキけんぞう
文中に登場した作品を紹介。
〈Collector's Vinyl Edition〉と銘打った45回転アナログ盤2枚組でリリースされるYMOの初期3作。