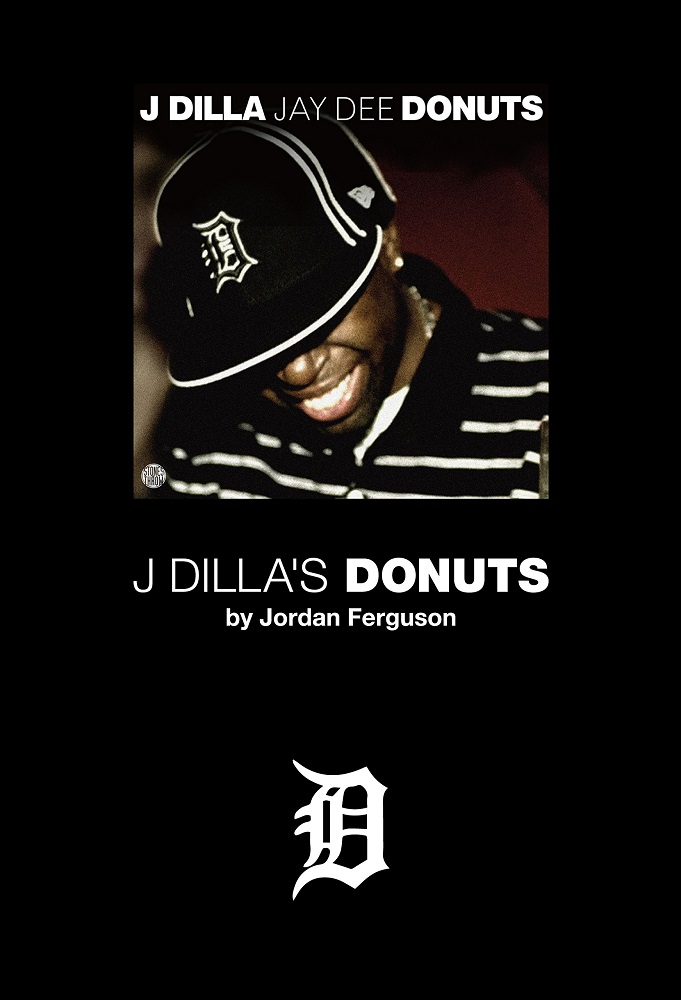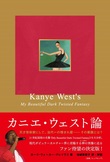J・ディラの革命的なクラシック・アルバム『Donuts』(2006年)の魅力や謎を解き明かそうと試みるジョーダン・ファーガソンの著書が、批評家でビートメイカー/ラッパーの吉田雅史による翻訳で届けられた。底本となっているのは、一枚のアルバムについて掘り下げる書籍シリーズ〈33 1/3〉から、「J Dilla's Donuts」。ちなみに、〈33 1/3〉は英ブルームズベリー出版(以前はコンティニュアム出版)の人気シリーズで、〈ピッチフォーク〉が〈33 1/3のベスト書籍33〉という選書もしていたりもする。
今年も2003年作『Ruff Draft』がオリジナル・ミックスでリリースされるなど、話題の尽きないJ・ディラ。言うまでもないことだが、彼の生んだ音楽の影響力は、ヒップホップ/ラップ・ミュージックの世界に留まらず、もっとも有名なところではジャズ・ドラマーのクリス・デイヴのプレイ・スタイルに多大な影響を与えるなど、広範囲に及んでいる。そんなディラの遺作にして、大いなる謎をはらんだアルバム『Donuts』が、本書では丁寧に、詳細に解きほぐされていく。
ディラの盟友、ピーナッツ・バター・ウルフの序文からして泣かせるのだが、前半ではディラの生い立ちやキャリアをしっかりと紹介しつつ(特に初期の不明瞭なキャリアが整理されていてわかりやすい)、彼の出身地であるデトロイトの音楽史をサマリーしている点も興味深い。実は、デトロイトには90年代初頭までヒップホップが根付いていなかったのだとか。アメリカ音楽史の知られざる一端を垣間見るかのようだ。
中盤はディラのLAへの移住と彼を死に至らせた病について綴られ、彼を取り巻いていた同地のラッパー/プロデューサーたちの証言から、『Donuts』のサウンドとディラの音楽が浮き彫りになっていく。結局、具体的な制作過程は謎めいたままなのだが、病院で動けなくなっているディラが7インチやPCを病室に持ち込んでいたというエピソードが衝撃的だ(著者は、ディラが病室で『Donuts』を作り上げたのではなく、最終的なミックスなどを行っていたのではないかと推測している)。
そういったジャーナリスティックな側面ももちろん重要なのだが、本書がユニークなのは、もうひとつ別のところにある。というのもファーガソンは、医師であるエリザベス・キューブラー=ロスの〈死の受容のプロセス〉理論(医療・看護・介護関係者は必ず知っている有名な説)を『Donuts』のサウンドと比較してみたり、さらにはトルストイやカミュ、果ては哲学者のアドルノまでを持ち出して同作を論じたりしている。これはまさしく『Donuts』に対するフレッシュな批評であり、このいびつで奇妙で不可思議なインストゥルメンタル・ヒップホップ・アルバムにどうにかして言葉を与えようとする営為にほかならないだろう。
エモーショナルで、ドキュメンタリー的で、ジャーナリスティックで、だがぶっ飛んだ、驚きの論も展開される。そんな「J・ディラと《ドーナツ》のビート革命」を読み終え、エンドレスにループする『Donuts』の謎はますます深まったような感覚をおぼえる。本書を読むことは、ディラの音宇宙の果てしなさを再確認する作業でもあるのだ。吉田による、ビートメイカー的視点からディラのサウンドをしっかりと言語化した〈ボーナス・トラック〉(解説)も必読。