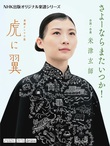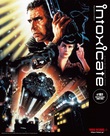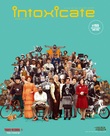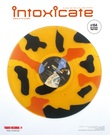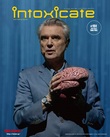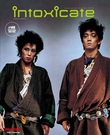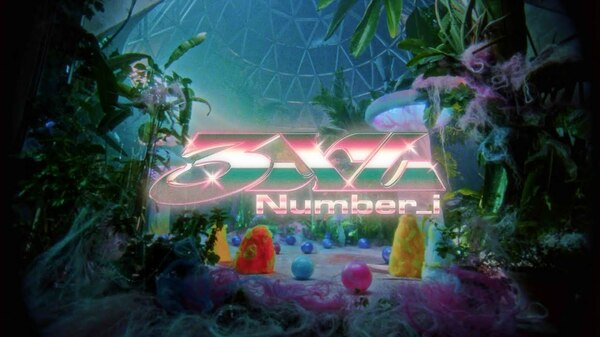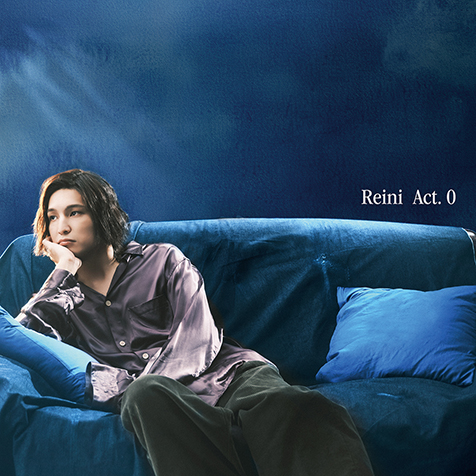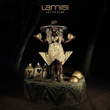DC/PRGをはじめとする菊地成孔とのコラボレーションや、大塚広子、守家巧らとのRM jazz legacy、原田知世のレコーディング/ツアー・メンバーとしても知られるキーボーディスト/作曲家の坪口昌恭。80年代末からスタートしたその活動は多岐に渡るが、彼は95年の坪口昌恭Project名義での『M.T.Man』以来、数多くのリーダー・アルバムをリリースしている。
今回、そうした自身の名前を冠した諸作から、菊地と始動した東京ザヴィヌルバッハまで、廃盤のものも多く含む坪口のリーダー作18タイトルがSpotifyやApple Musicなどの配信/ストリーミング・サーヴィスで入手できることになった。ここでは作品をリリース順に追いながら、ジャズとエレクトロニクスをユニークな形で融合させてきた坪口のキャリアをじっくりと辿ってみた。
ヤマハ講師もホコ天も経験したアマチュア時代
――まず、プロ・デビュー以前のお話から伺います。福井大学のご出身でしたね?
「はい。その頃にやっていたのはジャズというかフュージョンで、社会人バンドに加入してジョー・サンプル、デイヴ・グルーシン、リチャード・ティー、渡辺香津美さん、24丁目バンド、スティーヴィー・ワンダーとかをやり、学生バンドではオリジナルもやっていました。バンドのコンテストでいくつか賞を取ってからはさらにいろんなところから誘われるようになり、北陸地区ではイヴェント演奏の仕事もたくさんこなしていましたね。85年にはバークリー(音楽大学)の目黒セミナーに参加して、大西順子さんとも知り合いました。
で、87年に大学を卒業して、すぐに上京したんです。早稲田大学に通っていた親友がライヴを東京で企画してくれたんですね。彼が青山円形劇場をキープして、東京に来たらバンドを組んでライヴをやってよ、と。東京ではいきなりヤマハのキーボード講師をしました。福井時代に講師の資格を取っていたので、すぐできたんです。あとバブル期だったこともあり、企業の広告とかイヴェントでの演奏とかもふんだんにありましたね。バンドのほうは、最初はアマチュア精神というか、原宿のホコ天に出たり。ホコ天唯一のインスト・バンドでしたね(笑)」
――東京のミュージシャンとはどうやって知り合っていったんですか?
「先ほどの親友の伝手もありましたが、ドラマーの池長一美さんがヤマハの講師仲間で、彼の紹介で88年にギタリストの内橋和久さんに出会いましたね。ドラムの芳垣安洋さんは内橋さんのバンドにいたので、彼ともそこで。菊地成孔さんに出会ったのはその後です。彼のソプラノ・サックスの音の良さとMCのおもしろさに衝撃を受けて(笑)、バンドに誘ったんです。ま、(菊地は)ピットイン界隈の知り合いですね」

ピットインの顔になりそこねた?
――坪口昌恭Projectの結成が89年、芳垣さんと菊地さんも参加された最初のアルバム『M.T.Man』のリリースが95年ですね。
「『M.T.Man』はバンドを組んでからずいぶん長い時間が経ってから作りました。でも、いま思うと作るのに焦ったのかな。もっと室内楽的なほっこりとした音楽をやっていたのに、音源ではハードコアなプログレっぽい音になっちゃって。その頃聴いて好みだったオレゴンに似ないように意識したのもありますが」
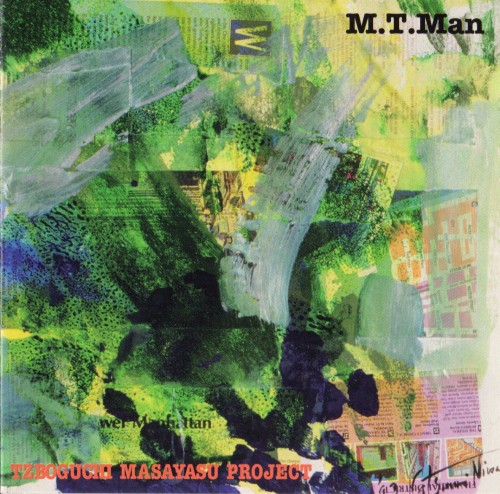
――ある意味バンドっぽい音ですよね。若いサウンドで。ところでこのアルバムではフェンダー・ローズを弾いていませんね。
「当時ローズは人気がなくって。90年代はフュージョンくささを払拭することが課題で、ローズを使うのはありえない、みたいな時代だったんです。当時はデジタルでいいローズの音を出せなかったし。でも、ジャミロクワイとかドナルド・フェイゲンの『Kamakiriad』(93年)にローズが使われているのを聴いて、やっぱりかっこいい!と思いましたね」
――いまのスマートな坪口さんからは出てこないタイプの曲もありますね。“ガングリ音頭”とか。
「うーん、ピットインの匂いのせいなのかな。あるいは梅津和時さんらの影響があった、とか。このアルバムには他にもスティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスなどのミニマル・ミュージック、今堀恒雄さんたちのティポグラフィカ、フランク・ザッパやヘンリーカウなんかに影響された曲、ドレミでマーチっぽくシンプルに作った曲とか、いろいろ収録されていて。この路線をずっと続けていたら、僕はピットインの顔みたいな存在になったかもしれませんよね」