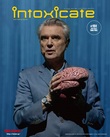花道に至るエピソード
〈アブストラクトなジャズ、しかも変拍子でクラバー達を踊らせる〉
〈DCPRG〉立ち上げ当時、菊地成孔が提唱したアイデンティティーであるが、筆者が菊地雅章氏(以下プーさん)と最も関連づけられるのはアルバム『SUSTO』の1曲目“CIRCLE/LINE”のカヴァーであろう。この曲のためにヴィンテージ・アナログ・ポリシンセProphet5を新調して臨んだくらいモチベーションの高まる楽曲であった。
80年代初頭といえば日本人ジャズメンもフュージョン真っ盛りであったが、“CIRCLE/LINE”ほど一線を画して聴こえたものは無い。7/8拍子で繰り返されるミニマル・ビートの上で多彩なシンセ・サウンドがちりばめられているが、調性も良くわからずなんとストイックなんだ!と。
その頃のスタジオ写真を見ると、主にOberheim、KORGのシンセや、YAMAHAのオルガンがガレージのようなスタジオに所狭しと並べられていて、膨大な時間をかけて音作りしインスピレーションのままに重ねられていった様子がうかがわれる。マイルス・デイヴィスの『Bitches Brew』『On The Corner』からの影響が色濃いことは明かだが、プーさんが独特なのは和のテイストがあること。クラスター・オルガンのサウンドが雅楽の笙を思わせるだけでなく、音色にも音価にも独特の滲みと斑(ムラ)を感じるのだ。必ず何か別の音色と混ぜたり、倍音にもサスティンにも余分な施しがされている。音の切りどころもわざと揺らがせて、あえてグルーヴを曖昧にしているとも思える。それが日本人古来の〈雅(みやび)〉な印象を植え付けるのだ(そう言えば、菊地家のファースト・ネームには全員〈雅〉が継承されている)。
この音に対するこだわりが、3月に発売される、晩年のピアノ・ソロ・アルバム『ラスト・ソロ~花道』にも色濃く聴かれ、本作は聴き慣れたスタンダードに取り組んでいるので尚更その妙を味わう事ができる。具体的には、和音にフィットするスケール以外の音をぶつけるだけでなく、ある和音から次に移る際に、わざと指やペダリングで一部の音を残す。そういったレゾナンスを巧みにコントロールすることで、ある種耳障りな音を加味するわけだが、その〈滲み〉が息づかいやうなり(実際にもうなり声を上げるが)にも聞こえ、美しさだけでなく心の痛みや闇を刺激し、作品としての強度が生じる。